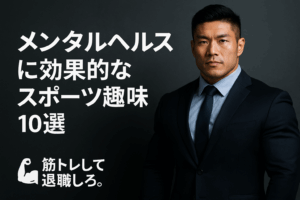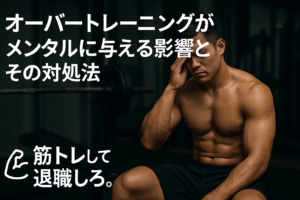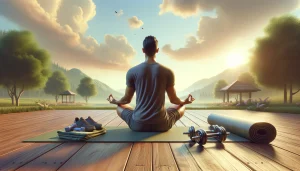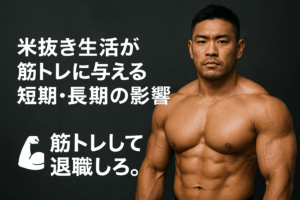感情に名前をつけるだけで脳の反応が落ち着き、ストレス反応が下がる行動科学ベースの技法。
上司の暴言や理不尽な要求で心が揺れた瞬間に言語化すると、感情に飲まれず次の行動を選びやすくなる。
日記・メモ・独り言で毎日ラベルを付けると、自己理解とメンタル耐性が同時に上がり、大事な判断もブレにくくなる。
はじめに
今回の記事では、心理学で「感情ラベリング(英:affect labeling)」と呼ばれる手法のメリットについて解説します
 カワサキ
カワサキ感情ラベリングとは、自分の漠然とした感情を具体的な言葉で表現することです。
たとえば



「今、私は怒っている」
「とても悲しい」
などと感情に名前をつける(言語化する)ことで、ネガティブな体験への対処がしやすくなると以前から考えられてきましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



『感情ラベリング』のメリット5選
この記事では『感情ラベリング』のメリット5選について、下記の内容で触れます。
① ストレス・不安を軽減出来る
感情ラベリングは、恐怖や不安といったネガティブな感情反応を抑える効果が示されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
実際に、2012年に米国UCLAの研究者キルカンスキーらは、クモ恐怖症の被験者を対象に感情ラベリングの効果を検証しました。



被験者がクモへの恐怖を言葉にして表現するグループは、1週間後に別のクモに触れるテスト時の皮膚電気反応(不安反応)が他の対照グループよりも有意に低下し、不安感が緩和されたと報告されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
同様に、2015年のUCLAの研究では、公開スピーチ恐怖症の被験者がスピーチ後に自分の感情をラベル付けしたところ、ラベリングを行わなかった対照群よりも心拍や皮膚電気活動などの生理的興奮が大きく減少する結果となりましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



特に感情ラベリングを多く用いた参加者ほど効果が大きかったことから、自身の恐怖や不安を言葉にすることが生理的なストレス反応を鎮める助けになると考えられますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
これらの結果は、「自分が不安に感じていることを声に出してみる」「ノートに今の感情を書き出す」といった簡単な行為でも、不安感を客観視して落ち着かせる効果が期待できることを示唆しています。
ただし、感情ラベリングはあくまで補助的な手法であり、根本的な不安要因を解決するものではありません。
恐怖症実験で示された効果
2012年UCLAの研究では、クモに対する恐怖を逐一言語化させるグループが、1週間後のテストで皮膚電気反応(SCR)という客観的指標で他群よりも低い数値を示しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
この実験では、被験者が「怖い」「気持ち悪い」と感じていることを具体的に言葉で表現しながらクモを見ており、その結果、言語化なしで慣らしをした対照グループよりも生理的恐怖反応が抑えられたのですpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



このように、自分の恐怖心を“今、こんな気持ちだ”と可視化することで、不安対象への生理反応が低減することが示されています。
具体策としては、 日常生活でも嫌な出来事やストレスを感じたとき、「怒っている」「イライラする」など、今の感情を言葉にする習慣を取り入れるだけでも、心理的な負担を軽減する一助になります。
限界としては、 この実験でも不安が完全に消失したわけではなく、あくまで反応が緩和されたにすぎません。



深刻な恐怖症やパニック症状に対しては、感情ラベリングだけで十分とは言えず、専門家の治療と合わせて用いることが推奨されます。
露出療法への応用
2015年の別のUCLA研究では、公開スピーチ恐怖症の治療の効果を高めるために感情ラベリングを組み合わせました。
その結果、感情を言葉にしながら治療を受けたグループは、通常の治療グループに比べて生理的な興奮レベルがより大きく低下しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
興味深いことに、元々の感情調整力が低く感情制御に苦手意識のある患者ほど、ラベリングを含む介入からより大きな効果を得ていましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



これは、感情表現が苦手な人にとっても、感情を言語化することがストレス耐性を高める助けになることを示しています。
具体策としては、 たとえばプレゼン前に「緊張している」と自分で確認する、または上司や同僚に「少し焦っているかも」と伝えるなど、場面での感情ラベリングを実践してみるとよいでしょう。
限界としては、 心理的な性格や状況によっては言葉にしづらい感情もあり、全員に万能というわけではありません。



また、この研究でも自己申告の不安レベルには有意差が見られなかったため(客観指標の低下が確認された一方で主観的な感じ方は同程度だった)、感情ラベリングが必ずしも即座に自覚的な安心感をもたらすわけではない点に留意しましょうpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
② 脳の反応が変わる
感情ラベリングは、脳内の反応を変化させることも分かっています。
UCLAのLiebermanら(2007年)は機能的MRIを用いた実験で、感情を言葉で表現するときに脳の扁桃体(恐怖や怒りなどの感情反応を司る部位)の活動が低下し、代わりに前頭前野の活動が増加することを発見しましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



具体的には、感情ラベリング条件では扁桃体やその他の辺縁系領域の反応が抑制される一方、右側下外側前頭前野(RVLPFC)の活性が高まりましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
さらにRVLPFCと扁桃体の活動は逆相関しており、中前頭前野(MPFC)を介する前頭前野から扁桃体への抑制パスウェイが働いていると考えられていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



言い換えれば、感情に言葉を与えることで、高次の前頭前野による情動の抑制が促進され、結果的に感情反応が落ち着きやすくなるということですね。
このことから、日常でも



「今、自分はこう感じている」
と言葉にしてみることで、理性的な思考を司る脳領域が活性化し、衝動的な感情反応をコントロールしやすくなる可能性があります。
具体策としては、 短い瞑想や呼吸法の際に自分の感情を確認して



「心臓がドキドキしてる」
「少し怒りがわいてる」
などと声に出してみると、冷静さを取り戻しやすくなります。
限界としては、 これも万能ではなく、脳活動の変化が心理的な快・不快のすべてを決定するわけではありません。



意識的な言語化が脳に変化を与えるとはいえ、状況によっては依然として強い感情に引っ張られることがありますので、ラベリングは「感情の一時停止ボタン」のように活用するとよいでしょう。
扁桃体・前頭前野の反応変化
Liebermanらは、ネガティブな感情刺激に対してその感情をラベリングすると、扁桃体の活動が低下し、代わりに前頭前野の活動が増加することを報告していますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
実際の実験では、「怒り」「悲しい」などのラベルを使って画像を見せる条件で扁桃体反応が抑制され、同時に感情制御に関与する前頭前野の活動が高まっていましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



この脳科学的エビデンスは、感情を言葉にすることで神経回路が活性化し、過剰な情動反応が抑えられる可能性を示唆しています。
具体策としては、 ストレスを感じた時に「今、この状況は私にとって○○なんだ」と紙に書いてみるなど、外部化するアプローチが有効です。
限界としては、 脳活動の抑制があっても体験自体が楽になるわけではなく、繰り返し練習しないと効果が薄れることがあります。



また、激しい感情や身体的な恐怖には専門的ケアが必要な場合もあります。
③ 自己認識力が高まる
感情ラベリングは、自分が何を感じているのかをより明確に理解する助けにもなります。
「感情の細分化(emotion differentiation)」と呼ばれる能力が高いほど、情動を適切にコントロールし、精神的に健康でいられることが知られています。
2021年のハーバード大学の研究レビューによれば、自分の感情をより精細にラベリングできる人ほど、ネガティブな感情に対して適応的な対処ができると報告されていますfrontiersin.org。
実際、多くの研究で感情識別能力の高い人はうつ病や不安障害などの発症リスクが低いことが示されていますfrontiersin.org。
具体策としては、 毎晩その日の感情を振り返り「今日は○○という気持ちだった」と日記に書いたり、スマホのメモアプリに感情を記録したりする方法があります。



感情ラベル一覧(例:喜び、安堵、怒り、悲しみ、不安など)を準備しておくと、言葉にしやすくなります。
ただし、限界としては、 表現できる感情語彙が乏しい場合や、あまりにも複雑な心境では適切な言葉が見つからないこともあります。



また、感情ラベリングはあくまで「自分の感情を客観的に見る手段」であり、感情そのものが生じる原因を直接変えるものではない点は注意が必要です。
感情識別能力の向上
複数の研究によれば、自分の感情を精緻に言語化できる人は、精神的にも安定しやすいことが示されていますfrontiersin.org。
特にFrontiers in Psychologyのレビューでは、感情のグラニュラリティ(細かい感情区別)の高い人ほど、強いストレスやネガティブな感情に対してうまく対処できると報告されていますfrontiersin.org。
具体策としては、 カウンセリングや自己分析の場で「私は今、○○を感じている」というフレーズを使い、感情にラベルを付ける練習をするのが有効です。
限界としては、 感情識別力が向上しても、すべての感情が即座にポジティブに変わるわけではありません。



負の感情を認めるプロセスの一環として捉え、他者への説明や解決策と組み合わせて活用することが重要です。
④ ポジティブ感情が増す
感情ラベリングはネガティブな感情だけでなく、ポジティブな感情体験を増幅する効果も報告されています。
2025年に日本の名古屋市立大の藤井らが行った研究では、ポジティブな画像を見せながら自分の感情や刺激そのものにラベルを付けてもらう実験が行われました。
その結果、ラベリングを行った参加者は、ただ画像を見る場合に比べてより強いポジティブ感情を主観的に感じたと報告されていますjstage.jst.go.jp。



また、中性画像(特に何も感じない絵)をラベル付けした条件では、瞳孔の拡大が抑制されるという生理反応の変化も見られ、ポジティブだけでなく「普通の」刺激への反応もラベリングによって変化することが示唆されましたjstage.jst.go.jp。
これらの結果は、嬉しい出来事や楽しい経験を言葉にして記録すると、そのポジティブさをより強く実感できる可能性を示しています。
具体策としては、 日常の中で小さな良いことに気づいたら、「今日は○○できて嬉しい」「いい運動ができて気分がいい」などと声に出してみると効果的です。



アルバムやメモに「今日のいいこと」を書き留めるのもよいでしょう。
限界としては、 ポジティブ感情の増幅はあくまで主観的なものであり、状況によっては期待ほどの喜びを得られない場合もあります。



過度にポジティブシンキングに傾くのではなく、ラベリングはあくまで心のバランスを取る一手段と捉えましょう。
ポジティブラベリングの効果
藤井らの実験では、ポジティブな写真を見ながら「嬉しい」「楽しい」など感情ラベルを使って言語化すると、単に見るだけの場合よりも主観的に感じる喜びが高まることがわかりましたjstage.jst.go.jp。



実験参加者は、自分のポジティブな感情に言葉をあてることで、その感覚が増幅したと報告しています。
また、何とも思わない中性画像に対して「なんとも思わない」などラベルを付けたところでは、生理的に興奮が抑えられる変化が観察されましたjstage.jst.go.jp。
これは、感情ラベリングがポジティブな場面をより意識的に捉えるのに役立つことを示しています。
具体策としては、 たとえばスポーツや趣味でうまくいったときに「うまくできた!楽しい」と言葉にすることで、達成感や喜びを強く感じられます。
限界としては、 すべてのポジティブ体験で劇的な効果があるわけではありません。



ラベリングで得られる喜びの増幅は個人差が大きいため、気軽に試してみて効果が弱ければ他の楽しみ方も併用しましょう。
⑤ 感情調整力が強化される
感情ラベリングは長期的なレジリエンス(回復力)の向上にもつながります。



前述の研究から、もともと感情調整が苦手な人ほど感情ラベリングを伴う訓練で効果を得やすいことが示されましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
これは、自己認識力が低いほど自分の感情状態を認識する機会が増え、徐々に感情制御技術を身につけやすいことを意味します。



感情ラベリングを継続して行うことで、日常的なストレス状況にも「何を感じているのか」がわかりやすくなり、冷静な対処の選択肢が増えます。
具体策としては、 ストレスフルな場面であえて「今、私は○○を感じている」と言語化してみる練習を積むとよいでしょう。
たとえば仕事でミスをしたときに「悔しい」と言えるか、部下に叱られた後に「悲しい」と感じていることを認めるかなど、感情にラベルを付けて受け止めてみます。



最初は照れくさいかもしれませんが、続けるうちに自分の情動パターンが見えてきて、対処法を考えやすくなります。
限界としては、 感情の言語化に慣れていない人や、強い感情が抑えきれない場面では、効果を感じにくいことがあります。



また、感情ラベリングはあくまで自己内での認識向上策であり、実際の問題解決や外部環境の改善までは直接つながらない点には注意が必要です。
感情制御が苦手な人への効果
2015年の研究では、もともと感情制御が苦手(emotion regulation deficit)の被験者ほど、感情ラベリングを組み込んだ介入で大きな効果を得ていましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



つまり、自分の感情にラベルを付ける経験を積むことが、感情に振り回されやすい人ほど大きな改善につながるわけです。
この結果は、感情ラベリングが未熟な自己制御能力の補助になることを示唆しています。
具体策としては、 日常生活でネガティブな感情を抱いたら、すぐに「怒ってる」「焦ってる」「不安だ」というラベルをつける習慣を持つとよいでしょう。



短いフレーズでも構いません。
限界としては、 言葉で表現するのが苦手な人や、もともと言葉での表現に抵抗がある人には取り組みにくい場合があります。



無理せず、初めは簡単な言葉から始めることが大切。
まとめ



いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
この記事のまとめ
- 感情ラベリング:感情に名前をつけるだけで情動の強さを一段落させる心理学的スキルです。 扁桃体の反応が下がり、前頭前野が働きやすくなることが海外のfMRI研究で示されています。
- ストレス対策との相性:ブラック企業のように環境をすぐ変えられない場面でも、自分の反応だけは先に落とせます。 「いま怒ってる」「これは怖さだ」と言語化すると、次に取る行動(証拠を残す・退職代行を検討する・筋トレでリセットする)が選びやすくなります。
- 自己認識の向上:感情を細かく分けて言える人ほどメンタルが安定しやすいと報告されています。 日記・メモ・独り言などアウトプットと組み合わせると日常のトレーニングになります。
- ポジティブの増幅:良かった出来事を言葉にするだけで、主観的なポジティブ感情は高まりやすくなります。 筋トレ後の「今日はこれができた」を書き残すと、行動の定着にもつながります。
- 万能ではない:トラウマやPTSD、深刻なハラスメントがある場合は専門家との併用が安全です。 感情ラベリングは“落ち着くまでの橋渡し”と捉えておいてください。



今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 感情ラベリングは本当にストレスや不安を下げる効果がありますか?
-
あります。脳の扁桃体の反応が弱まり、前頭前野が働きやすくなることがfMRI研究で確認されています。 クモ恐怖やスピーチ不安でも、生理的な緊張の低下が報告されています。言葉にするだけでも意味があります。Frontiers+2PMC
- ブラック企業のように理不尽な環境でも感情ラベリングは使えますか?
-
使えます。外部環境をすぐ変えられないときでも、自分の感情を先に可視化すると反応が一段落ちます。 「今は怒り」「今は恐怖」と切り分けることで、次にとる行動(退職相談・記録・証拠保全)を選びやすくなります。PMC
- 感情ラベリングと「ただ気をそらす」やり方はどこが違いますか?
-
感情ラベリングは感情を認めてから処理する点が、注意そらしと決定的に違います。 そらす方法は一時的には楽ですが戻るとまたつらくなります。Frontiers
- 感情ラベリングはうつや不安の予防にもなりますか?
-
なりますが万能ではありません。感情を細かく区別できる人ほどメンタルが安定しやすいというデータがあります。 2024〜25年のレビューでも、感情の細分化が低いとストレス場面で崩れやすいと報告されています。必要なら専門家にもつなげてください。ResearchGateTaylor & Francis Online
- 感情に名前をつけるだけでポジティブ感情まで増えるのはなぜですか?
-
ポジティブな出来事にもラベルを付けると注意がそこに固定され、主観的な喜びが強まるからです。 日本語の実験でも、画像を見て「嬉しい」と書くだけで見ただけの群より得点が上がりました。日報や筋トレログに一言添えると効果が残りやすいです。Taylor & Francis Online
- 感情ラベリングはどのタイミングでやるのが一番効果的ですか?
-
感情が高ぶった直後〜数分以内が最も効きやすいと報告があります。 2022年の研究では強度とタイミングで効き方が変わるとされ、早すぎても遅すぎても弱くなります。スマホのメモにすぐ書く、トイレでつぶやくなど「即時性」を意識してください。PMC
- 感情ラベリングと「再評価(リアプレイザル)」はどちらを優先すべきですか?
-
強く揺れているときは先にラベリング、落ち着いたら再評価です。 2024年の研究では順番によって前頭前野の動きが変わるとされ、いきなり考え直そうとすると処理が複雑になるケースが示唆されています。感情→意味づけの順でやれば混乱しにくいです。BioMed Central
- 感情ラベリングを習慣化するにはどうすればいいですか?
-
1日1回、固定のフォーマットで書くのが一番続きます。 2024年のオンライン訓練でも、感情語を学ぶだけで分化が高まり、後日のストレス低下に寄与していました。日記アプリに「出来事→感情→強さ→次にやること」をテンプレ化するとブラック職場でも回せます。PLOS
- マインドフルネスや筋トレと一緒にやる意味はありますか?
-
あります。注意を「今ここ」に戻すマインドフルネスが、感情を細かく言語化する力を底上げするからです。 2025年の報告でも、短期のマインドフルネス介入で感情分化が上がるとされています。筋トレ後のクールダウン時に今日の感情を3語書くと相乗効果が出やすいです。Frontiers
- PTSDや強いトラウマがある人が感情ラベリングを使っても大丈夫ですか?
-
大丈夫なケースが多いですが、強いトラウマには専門家と一緒に使うほうが安全です。 2024年のPTSD向けパイロット研究でも、コンピューター上の感情ラベリングが症状軽減に使える可能性が示されましたが、反応が強い人もいたので独力で無理しないでください。FrontiersPMC
その他の質問はこちらから: