この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
 カワサキ
カワサキ逆ギレしてこっちのせいにしてくる奴いますよね?
そいつのその行動・手法にはDARVO(ダルヴォ・ダーヴォ)という名前がありますよというお話。
加害者が自分の非を否認し、攻撃し、被害者の立場を奪う心理的戦略である。
DARVOはブラック企業やモラハラ上司において頻発し、被害者の訴えをねじ曲げるために使われる。
被害者は冷静な記録と第三者の支援を活用し、自分を守る戦略的対応が必要である。
職場でパワハラやモラハラを受けたのに、なぜか自分がこっちが悪者にされる…そんな理不尽な経験をしたことはありませんか?



わ た し は あ り ま す 。
それ、もしかしたら相手が使っているのは「DARVO(ダルヴォ)」という心理戦略かもしれません。



結果として、本来いじめを受けていた側が逆に加害者扱いされかねない状況に追い込まれてしまいます。



加害者が自分の非を否認し、攻撃してきて、最終的に「自分こそが被害者だ」と主張する――それがDARVOです。
この記事では、DARVOの定義から職場での具体例、加害者の心理的特徴、そしてあなた自身が巻き込まれたときの対処法まで、信頼性のある研究をもとにわかりやすく解説します。



職場のハラスメントやブラック企業から脱出したい方、自分を守る知識を身につけたい方はぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
DARVO(否認・攻撃・被害者ヅラ)とは何か
DARVO(ダーウォ)とは、Deny(否認)・Attack(攻撃)・Reverse Victim and Offender(被害者と加害者の立場を逆転させる)の略で、加害者が自分の非を指摘されたときによく示す反応パターンを指しますjjfreyd.com。
具体的には、「そんな事実はない」と行為自体を否認し、指摘してきた相手の人格や信用を攻撃し、挙句の果てには「自分こそが被害者だ」と主張して被害者ヅラ(立場の逆転)をするのが特徴ですjjfreyd.com。
例えば本来はパワハラ加害者である人物が



「自分は部下に濡れ衣を着せられている被害者だ!」
と振る舞い、告発者である被害者を「嘘つき」「加害者」扱いするようなケースですjjfreyd.com。
このDARVOという言葉は米国の心理学者ジェニファー・フレイド氏が1997年に提唱した概念で、主に性的暴行やDVなどの文脈で加害者が責任追及を逃れるために使う戦略として知られてきましたjjfreyd.com。
臨床心理学や精神医学の分野でも、ガスライティング(被害者に自分の正気を疑わせる心理操作)の一種として注目されており、心理的虐待を行う者がよく使う典型的な操作手法だと指摘されていますen.wikipedia.org。



被害者からの告発を握り潰し、責任を回避する目的で用いられるため、結果的に被害者の心に深いダメージを与えたり、周囲からの支援を妨げたりする点で非常に悪質です。
職場におけるDARVOの具体例
ブラック企業のような職場では、パワハラやいじめが横行するだけでなく、いざ加害行為を指摘すると逆ギレされる…といった経験はありませんか?以下に職場で起こりがちなDARVOパターンの具体例を挙げてみます。
上司によるパワハラの例
部下が上司からの暴言やモラハラを勇気を出して訴えたとします。
すると上司は



「お前にそんなことを言った覚えはない」(否認)
と開き直り、



「むしろお前の態度が悪いから注意しただけだ!」
と部下のミスや性格を責め立てます(攻撃)。
挙句の果てに



「部下にハラスメント加害者扱いされるなんて心外だ。俺の方が被害者だ!」
と怒鳴り、あたかも自分が不当な責めを受けている被害者であるかのように振る舞います(被害者ヅラ)。



まさに立場を逆転させてしまう典型的なDARVOの展開です。
同僚によるいじめの例
同僚から陰で悪口を言われたり仕事を妨害されたりしている人が、その加害者同僚を上司に報告したケースを考えます。加害者の同僚は上司に対し



「自分は何もしていません。誤解です」(否認)
と言い逃れします。さらに



「あいつが勝手に被害妄想しているだけだ。職場の雰囲気を乱して困る」(攻撃)
と被害者を問題人物扱いします。
そして最終的には



「こんな嘘の告げ口をされて迷惑している。私こそ精神的苦痛を受けた被害者です」(被害者ヅラ)
と主張します。
これらは一例ですが、職場におけるモラハラ・パワハラの現場では、加害者が追及を受けた途端にこのような「否認→攻撃→被害者アピール」のコンボを繰り出す場面が少なくありませんworkplacebullying.org。
事実、職場でいじめやハラスメント行為を訴えると、多くの場合に加害者や組織からの強い反発(報復)が起こり得ることが知られていますworkplacebullying.org。



DARVOはまさにそうした場面で「よくある典型的な反応」なのです。
DARVOを使う加害者の心理・特徴
なぜ加害者はDARVOのような振る舞いをするのでしょうか?



そこにはいくつかの心理的特徴や動機が考えられます。
責任回避と自己防衛
最大の目的は、自らの非を認めず責任追及を逃れることです。
指摘されると自身の評判や立場が脅かされるため、パニック的に自己防衛に走ります。



「そんなはずはない、悪いのは相手だ」
と信じ込むことで、自分は悪くないと安心したい心理もあります。
権力者の特権意識
特に職場の権力者(上司など)であれば、



「自分が間違っているはずがない」
「部下ごときに非難される筋合いはない」
という特権的な思い込みがあることも。
プライドが高く弱みを見せられないタイプは、指摘を受けると逆上して相手を攻撃しがちです。
実際、自己愛傾向(ナルシシズム)が強い人や他者を操作するマキャベリズム傾向のある人はDARVOを使いやすいとの指摘もありますjjfreyd.com。



そうした人々は他者への共感に欠け、批判されると過剰防衛しやすいためです。
被害者非難の価値観
DARVOを使う加害者はしばしば「被害者のくせに訴える方が悪い」「大げさに騒ぐ方がおかしい」といった被害者非難の価値観を持っています。
最新の研究でも、DARVO対応をする人ほどセクハラ加害経験があったり、被害者を責める考え方(レイプ神話の受容)が強かったりする傾向が示されていますjjfreyd.com。
つまり、そもそも他者へのハラスメント行為を正当化し、罪悪感を抱きにくい人格傾向があるのです。
このような加害者は



「自分は悪くない」
「悪いのは常に相手だ」
という歪んだ信念を持ち、問題が発生するとその信念を守るために攻撃と被害者ポジション取りを行います。
学習された戦略
DARVOは非常に効果的な攻撃的自己防衛戦略でもあります。
過去にそれで責任を逃れられた経験があると、加害者は「この手は使える」と学習してしまいます。
周囲もそれに慣れてしまい、



「あの人を批判すると逆に自分が悪者にされる」
と思って誰も指摘できなくなる悪循環が生まれます。
組織内で暗黙に成功してしまったDARVO戦略は、加害者本人の中では「自分を守る正当な方法」くらいに認識されているかもしれません。



いずれにせよ、DARVOを用いる加害者は自責の念や良心の呵責が希薄である点が共通しています。
ある専門家は、こうした反応は「加害者や企業の臆病さの表れ」であり、本来取るべき責任から逃げるための卑怯な行為だと述べていますworkplacebullying.org。
彼らは自らの行為の責任を決して認めようとせず、追及されれば被害者を攻撃してでも自分の非を覆い隠そうとします。



その背景には、高慢さや特権意識、共感の欠如など加害者の深層心理が潜んでいるのです。
被害者がDARVOに巻き込まれたときの対処法
もしあなたが職場でDARVO戦略に直面してしまったら、どのように対応すればいいのでしょうか?



以下に具体的な対処法とポイントをまとめます。
まずは冷静に「これはDARVOだ」と見抜く
相手の過剰な否定や攻撃に直面すると、こちらも感情的になってしまいがちです。
しかし



「この反応パターンはDARVOだ」
と知っているだけで状況を客観視しやすくなります。
専門家もDARVOという予測可能なパターンを知っておくことで、加害者からの報復的な攻撃を個人的に受け止めずに済むと指摘していますworkplacebullying.org。
これは



「自分が悪いのではない、相手が典型的な戦術に出ているだけだ」
と理解することでもあります。
実際研究でも、DARVOに晒されると被害者は自分を責める気持ちが強まりがちですがjjfreyd.com、



「これは典型的な心理操作だ」
と気づけば自責の念に飲み込まれにくくなるでしょう。
事実関係の記録と証拠集め
加害者は平気で事実を捻じ曲げて否認しますから、客観的な記録を残すことが重要です。
日時・場所・内容をメモする、メールやチャットでのやり取りは保存する、可能なら会話を録音するなど、後から検証可能な証拠を集めておきましょう。



第三者に相談する際や、正式に問題提起する際にも記録があるのと無いのとでは信頼性が違います。
信頼できる同僚や専門機関に相談する
職場に頼れる同僚や先輩がいれば状況を共有しましょう。



客観的な意見や裏付け証言が得られるかもしれません。
また、社内の人事・コンプライアンス部門や産業医に相談できる場合もあります。
ただしブラック企業では社内の対応が期待できないことも多いため、社外の労働相談窓口や労働組合、弁護士に相談するのも有効です。
近年はハラスメント相談窓口を自治体や厚生労働省が設けており、無料でアドバイスを受けることもできます。



自分一人で抱え込まず、第三者の力を借りることが大切です。
反論よりも距離を取る
加害者と直接やり合っても泥仕合になりがちです。
特に相手が上司の場合、感情的に言い返すとさらなる攻撃材料を与える恐れがあります。



可能であれば会話は記録に残る手段(メール等)で行い、対面で議論しないようにしましょう。
どうしても対話が必要なら信頼できる第三者(例えば別の上司や労組代表)に同席してもらうと安全です。



相手の土俵(怒鳴り合いなど)に乗らず、静かに事実だけを指摘してそれ以上踏み込まないなど、自分の心の安全距離を確保してください。
自分を責めない・メンタルケアを優先する
DARVOの怖いところは、被害者自身が



「あれ、もしかして自分が悪いのかも…」
と感じてしまう心理効果にありますjjfreyd.com。
これを防ぐためにも、



「相手の言い分は典型的な加害者の戦術だ」
と再確認し、自分の感じた被害を信じることが重要です。
必要に応じて心理カウンセリングや医療機関のサポートを受け、自分の心身を守りましょう。
睡眠や食事をしっかり取り、趣味や運動でストレス発散するなどセルフケアにも努めてください。



あなたが健全な判断力を保つことが、結果的に最善の対応策につながります。
周囲にもDARVOを周知する



「実は加害者の典型的な反応パターンがあって…」
とDARVOについて共有してみましょう。
直接「あなたはDARVOを使っている」などと加害者本人に言うのは火に油ですが、第三者にはこの概念を知ってもらう価値があります。
研究でも、DARVOについて学ぶことでその策略の効果を弱められる可能性が示されていますjjfreyd.com。



周囲が真実を見抜く助けとなれば、被害者への不当な非難を和らげることができるかもしれません。
周囲の人がDARVOに気づくためのサイン
職場で第三者として状況を見ている人々(同僚や人事担当者、上司など)も、DARVOの構図に早く気づくことが被害者の救済につながります。



では、周囲の人はどんなサインに注意すればDARVOを見抜けるでしょうか?
指摘に対する反応が異様に攻撃的・被害者的
何か問題行動を指摘されたとき、普通であれば反省や弁明をするものです。
しかしDARVO加害者は、指摘の内容そっちのけで激昂し、



「酷い言いがかりだ!」
などと被害者ぶるリアクションを示します。



事実関係より感情的な自己防衛に終始している場合は要注意です。
告発した人がいつの間にか悪者扱いされている
本来問題行動を受けた被害者が名乗り出たのに、なぜか周囲から「あの人にも非があるのでは?」「トラブルメーカーではないか」などと見られ始める場合、それはDARVOが進行している可能性があります。
被害者が孤立し、加害者の言い分(「自分は悪くない、あいつが悪い」)が周囲に浸透し始めたら危険信号です。



まさに「被害者」と「加害者」の役割が入れ替わっている状態と言えます。
権力者側の一方的なストーリーになっている
特に上司 vs 部下のような関係では、上司の発言力が強いために上司側の主張ばかりが通っていないか注視しましょう。
例えば上司が



「自分は部下に裏切られた被害者だ」
と涙ながらに訴え、人事や他の上司もそれに同情して部下を非難し始めるような場合です。



本来立場の弱い部下の訴えがかき消され、立場の強い人が被害者ポジションを独占しているようなら、その構図には疑いを持つべきです。
問題提起後、組織が安堵して動かなくなる
周囲の管理職や会社が「どうやら誤解だったようだ」「大したことではなかった」と早合点して対応を打ち切ろうとするのもサインです。
もし加害者の



「自分は無実でむしろ傷ついた」
という主張を鵜呑みにして、会社が「騒ぎ立てる被害者側に問題があるのでは?」といった姿勢を見せたら要警戒です。



加害者の狙い通り周囲が動かなくなるのは、DARVO戦略が効果を発揮している証拠だからですworkplacebullying.orgjjfreyd.com。
同様のパターンが繰り返されている
その人物が過去にも誰かに非を指摘されて逆ギレし、結局相手を悪者にしてきた前例がないか確認しましょう。
もし「あの人は指摘すると必ず相手のせいにして騒ぐ」という評判があるなら、まさにDARVO常習者かもしれません。一度や二度の誤解ではなくパターンとして繰り返される行動である点にも注目です。
周囲の人間がこれらのサインに気づき、



「もしかしてこれは被害者が悪いのではなく、典型的なDARVOではないか?」
と疑うことは被害者救済の第一歩です。
研究でも、DARVOが行われると第三者(傍観者)は被害者を信じにくくなり加害者を擁護しがちだと示されていますjjfreyd.comjjfreyd.com。
だからこそ、傍観者自身が意識的に冷静さを取り戻し、



「加害者の過剰な自己防衛に惑わされていないか?」
と自問する姿勢が大切です。



会社の人事担当者や経営陣も、感情に流されず事実関係を公平に調査し、被害者と加害者からそれぞれ話を聞くなど慎重な対応が求められます。
学術的な裏付け:DARVO戦略の研究知見
DARVOについては近年、心理学・社会学の分野で徐々に研究が蓄積されつつあります。



その中で明らかになっている興味深い知見やデータをいくつか紹介します。
DARVOは加害者によく使われる
2017年の研究では、加害行為を指摘された加害者の多くがDARVO的な反応を示したことが報告されましたjjfreyd.com。
要するに、「自分が責められたときにDARVOで切り返す」のは珍しくないということです。



この研究では特に、女性の被害者が訴えた場合に男性より高い頻度でDARVOに直面したことも示唆されていますjjfreyd.com。
DARVOは被害者の自己非難感を高める
前述の2017年研究では、DARVO対応に遭った被害者は「自分が悪かったのかもしれない」という自責の念を強めてしまう傾向があることが示されましたjjfreyd.com。
加害者の否認・攻撃によって被害者が萎縮し、



「自分のせいでこんな事態になったのでは」
と感じてしまうのです。



これはDARVOが被害者の沈黙を生み出す一因であり、加害者が被害者を黙らせる手段として有効に機能してしまうことを意味しますjjfreyd.com。
DARVOは周囲の人の認知も歪める
2020年の実験的研究では、第三者がある加害事例を読む際に、加害者がDARVO対応をしている場合とそうでない場合で反応が比較されましたjjfreyd.com。
結果、DARVO対応があると第三者は被害者を信じにくくなり、逆に被害者を責める傾向が強まることが分かりましたjjfreyd.com。



つまり、DARVOは傍観者から見ても加害者を擁護したくなるような錯覚を生み、被害者の信用を低下させてしまう効果があるのです。
教育や啓発でDARVOの効果を弱められる可能性
上記の2020年研究では、事前にDARVOという概念を教わっていた第三者は、そうでない人に比べて加害者の言い分を鵜呑みにしにくくなったという興味深い結果も報告されていますjjfreyd.com。
DARVOについて知識があるだけで、



「この加害者の開き直りは例のアレかも」
と察知でき、被害者の話にも耳を傾けようという姿勢が出てくるのです。



これは職場でのハラスメント研修などでも活用できる示唆であり、DARVOを知ること自体が被害者保護に繋がる可能性を示しています。
DARVOを使う加害者の思想傾向
2024年の研究では、DARVO対応を取る人ほどセクシャルハラスメントなど他者への加害行動を起こした経験があったり、被害者を非難する風潮(例えば「性被害に遭う方にも落ち度がある」等)を受け入れていたりする傾向があると報告されましたjjfreyd.com。



要するに、DARVOを多用する人は他者への攻撃的行動を正当化しやすく、自分の非を認めない価値観を持っているということです。
また別の発表では、ナルシシズム(自己愛)やサイコパシーといった「ダークトライアド」と呼ばれる人格特性との関連も示唆されていますjjfreyd.com。



これらは、DARVO加害者の心理的特徴を裏付けるデータと言えるでしょう。
職場ハラスメントの多さ(背景事情)
そもそも職場でハラスメント被害に遭う人はどの程度いるのでしょうか。



国内外の統計を見ると、その多さが浮き彫りになります。
日本の厚生労働省の調査(2023年)では、直近3年間にパワハラを受けた経験のある労働者は19.3%(5人に1人)にも上りましたmhlw.go.jp。
海外でも数字に差はあるものの、概ね10~30%程度の労働者がいじめ・嫌がらせを経験しているとの報告がありますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
これほど多くの職場でハラスメントが起きている背景では、加害者が自己弁護に走る場面も必然的に多くなると考えられます。



DARVO戦略は、そのような職場ハラスメントの隠蔽・継続を支える要因の一つとして、学術的にも注目されているのです。
以上のように、DARVOに関する研究はまだ新しいながらも、既に「あるある」として実感されていた現象をデータで裏付けつつあります。



被害者への心理的影響や周囲への波及効果まで明らかになり始めており、職場環境を考える上でも無視できないテーマとなっています。
職場改善か退職か:DARVOを踏まえた判断
ブラック企業でハラスメントに遭いDARVOで切り返されるような状況では、「この職場で戦い続けるべきか、それとも退職すべきか」と悩むのは当然のことです。



最終的な決断は各人の状況によりますが、DARVO戦略が横行する環境という視点から、判断のヒントとなるポイントを挙げます。
組織の対応姿勢を見極める
まず、あなたの職場(会社)がハラスメント問題に真剣に取り組む姿勢があるかを冷静に見極めましょう。



上層部や人事が被害訴えに耳を傾け、公平な調査をしてくれる見込みがあるなら、社内改善の道も模索できます。
しかし、もし会社自体が「そんな訴えは会社の恥になるからやめてくれ」と隠蔽に走ったり、組織ぐるみで被害者を攻撃・無視するようないわば「Institutional DARVO(組織的DARVO)」の兆候があるなら、内部での解決は非常に困難ですjjfreyd.com。



例えば訴え出た途端に左遷されたり、逆にあなたが懲戒処分を検討されるような事態になれば、社内改善より退職や法的手段を検討すべき深刻なサインと言えます。
自分の心身の健康を最優先に
どんなに仕事が好きでも、健康を損ねては元も子もありません。
研究が示すように、職場いじめの被害はメンタルヘルス不調や深刻なストレス反応を引き起こしpmc.ncbi.nlm.nih.gov、場合によっては仕事を続けられなくなるほど追い詰められることもあります。



DARVOによる追い打ちは被害者の精神的負担を一層重くし、うつ症状やPTSDのリスクも高めかねませんjjfreyd.com。
もし現在の職場にいることであなたの心と体が限界に近いなら、迷わず「自分を守るために退職する」選択肢を検討してください。



これは逃げではなく、身の安全を確保する大切な判断です。
法的・社会的支援を活用する
日本では2020年よりパワハラ防止法制が整備され、企業にハラスメント対策が義務付けられています。
にもかかわらず改善されない職場に対しては、労働局の相談コーナーや弁護士などを通じて法的措置を検討することもできます。
証拠がしっかり揃っていれば、労働審判や訴訟で慰謝料・未払賃金の請求、加害者の処分要求なども不可能ではありません。
ただし法的闘争は時間と労力がかかるため、あなた自身がそれに耐えられるか、メリットが見合うかを慎重に考える必要があります。



社内に味方が皆無で完全に四面楚歌な場合は、無理に戦わず一旦退職して心身を休めてから次の行動を考えるのも賢明です。
退職のタイミングと戦略
仮に退職を選ぶ場合でも、「辞め方」は重要です。
感情的に



「もう今日限りで辞めます!」
と突然去るより、次の仕事探しの準備や証拠集めを済ませてから計画的に退職した方が、あとあと有利になります。
実は職場いじめの被害者の多くは最終的にその職場を去るケースが統計的にも多いのです(ある調査では被害者の67~77%が最終的に職を失ったとのデータもありますworkplacebullying.org)。



それ自体悲しい現実ですが、裏を返せば「辞める」という選択は決して珍しくなく、あなた一人の敗北ではありません。
むしろ自分を大事にする積極的な決断と捉えてください。専門家の中には、「正式に社内告発するなら外部に退職後、安全な立場から行った方が良い」と助言する声もありますworkplacebullying.org。
在職中に闘うと報復人事や経済的不安で追い詰められるため、転職先を決めてから安全圏で声を上げる方がリスクは低いという考えですworkplacebullying.org。



このように先手を打っておくことで、退職後に労基署や弁護士を通じて然るべき措置を求める余裕も生まれるでしょう。
職場を去ることは「負け」ではない
ブラック企業に勤めていると、



「ここで逃げたら次でも通用しないのでは」
「自分が我慢すれば丸く収まるのでは」
と自分を追い込んでしまうことがあります。
しかし、度を越えたハラスメントが横行し改善意欲もない職場環境を個人の力で変えるのは非常に困難です。
環境を変えられないなら自分が環境を変える(=職場を変える)しかありません。
退職は決して敗北ではなく、新しい健全な環境で力を発揮するためのリスタートです。



「自分が悪かったわけではない。悪いのは環境だ」
と割り切り、次のステップに踏み出しましょう。その際、今回経験したDARVOの知識はきっと無駄にはなりません。
次に職場を選ぶとき、面接や社風を見る中で「この会社は大丈夫か」の判断材料になるでしょうし、万一またトラブルに遭っても



「これはあのパターンかな?」
と早めに対処できるかもしれません。
まとめ



いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
この記事のまとめ
- DARVOとは何か:加害者が非を否認し、相手を攻撃し、最終的に自分を被害者のように装う心理的防衛戦略。
- 職場でのDARVO事例:パワハラを指摘すると逆ギレされる、いじめを報告すると悪者扱いされるなど、ブラック企業で頻発。
- 加害者の特徴:責任回避傾向、自己愛、共感性の欠如、特権意識、過去の成功体験による学習効果などが背景にある。
- 被害者の対処法:DARVOだと気づくこと、証拠を残すこと、信頼できる第三者へ相談すること、感情的な応酬を避けることが重要。
- 第三者が気づくべきサイン:加害者の逆ギレ、被害者の孤立、権力構造の歪み、組織による隠蔽の兆候に注目。
- 学術的根拠:DARVOに関する研究では、被害者の自己非難や傍観者の認知の歪みを引き起こすことが明らかになっている。
- 退職判断のポイント:組織の対応姿勢、自身の心身の状態、法的選択肢の有無を踏まえて、自分を守る決断を優先すること。



今回の記事は以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 上司が明らかにDARVOを使ってきます。どう対応すればいいですか?
-
まずは冷静に状況を把握し、感情的な反応を避けましょう。次に、事実を客観的に記録することが重要です。メールや会話の内容を記録し、可能であれば証拠を保存してください。また、信頼できる同僚や人事部門に相談し、第三者の視点を得ることも有効です。必要に応じて、外部の専門機関や労働相談窓口に相談することも検討しましょう。
- DARVOを使う人は自覚しているのでしょうか?
-
多くの場合、DARVOを使う人は無意識にこの戦略を用いています。自分の非を認めたくない心理や、自己防衛の本能が働いていることが多いです。しかし、意図的に相手を操作しようとするケースも存在します。相手の意図を見極めることは難しいため、自分自身の感情や反応に注意を払い、必要に応じて距離を取ることが大切です。
- 同僚がDARVOの被害に遭っているようです。どうサポートすればいいですか?
-
まずは同僚の話を傾聴し、共感を示すことが大切です。被害者は孤立感を感じていることが多いため、信頼できる存在であることを伝えましょう。また、具体的な証拠の収集や、適切な相談窓口の紹介など、実務的なサポートも有効です。無理に解決しようとせず、専門機関の助けを借りることも検討してください。
- DARVOとガスライティングの違いは何ですか?
-
DARVOは、加害者が自分の非を否認し、被害者を攻撃し、自分を被害者のように装う戦略です。一方、ガスライティングは、相手の現実認識を歪め、自己疑念を抱かせる操作的な行動です。両者は異なる戦略ですが、同時に用いられることもあり、被害者の混乱を深める要因となります。
- 組織全体がDARVO的な対応をしている場合、どうすればいいですか?
-
組織全体がDARVO的な対応をしている場合、内部での解決は難しいことが多いです。まずは外部の労働相談窓口や専門機関に相談し、客観的なアドバイスを得ることが重要です。また、退職や転職を視野に入れることも、自分自身を守るための有効な手段です。
- DARVOの被害を受けると、どのような心理的影響がありますか?
-
DARVOの被害を受けると、自己肯定感の低下や不安、抑うつなどの心理的影響が生じることがあります。また、自分自身を責める傾向が強まり、問題の本質を見失うこともあります。早期に専門家のサポートを受けることで、心理的なダメージを軽減することが可能です。
- DARVOを使う人に共通する特徴はありますか?
-
DARVOを使う人には、自己中心的な傾向や責任回避の傾向が見られることが多いです。また、他者への共感が乏しく、自分の立場を守ることを最優先する傾向があります。ただし、すべてのケースが当てはまるわけではないため、個別の状況を慎重に判断することが重要です。
- DARVOの被害を受けた場合、法的な対応は可能ですか?
-
DARVO自体は法的な用語ではありませんが、その行為が名誉毀損やハラスメントに該当する場合、法的な対応が可能です。証拠の収集や専門家の助言を受けながら、適切な手続きを進めることが重要です。また、労働基準監督署や労働組合などの公的機関に相談することも有効です。
- 証拠を集めたいのですが、バレずに記録を残すにはどうすればいいですか?
-
ボイスレコーダーで会話を録音したり、日付入りのメモを残したりするのが有効です。
スマートフォンの録音アプリでも十分ですが、音質が悪いと証拠能力が下がるため注意が必要です。PC上のチャットやメールはスクショやPDF保存しておきましょう。相手にバレると対立が激化することもあるので、慎重に行動してください。 - 「自分こそが被害者だ!」と主張する上司に、どう言い返せばいいですか?
-
感情的に反論せず、事実ベースで返すのが鉄則です。
「私はあくまでこの事実について確認したいだけです」と冷静に主張し、個人的な感情や人格攻撃に巻き込まれないよう注意してください。言い返すよりも、“記録に残す”ことを意識した対応が重要です。 - 社内に相談できる人がいない場合は、どうすればいいですか?
-
外部の専門機関や退職代行サービスを活用するのも選択肢です。
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」や弁護士による無料相談、労働組合系の支援団体などがあります。孤立して戦う必要はありません。退職を視野に入れているなら、証拠をもとに安全に抜け出すためのサポートも検討してください。 - 周囲が加害者の言い分ばかり信じて、孤立しています。どうすれば?
-
“一時的な孤立”はあっても、事実と向き合う人は必ず現れます。
周囲がDARVOに流されるのはよくあることです。被害者が「やっぱり自分が悪かったのかも…」と誤解しないためにも、客観的な記録を残し、専門家に相談して支えてもらいましょう。孤立は永遠ではありません。 - 自分がDARVOを使ってしまっているかもしれません。改善できますか?
-
自覚できた時点で、変われる可能性は十分あります。
責任逃れや自己弁護のクセに気づいたら、まずは事実と感情を切り分けて見つめ直しましょう。心理カウンセリングやアンガーマネジメントの学習が効果的です。謝罪と修復の姿勢を持つことも重要です。 - 「あの人には絶対に逆らえない」という空気があって声を上げづらいです。
-
組織に“恐怖支配”が蔓延している場合、無理に声を上げるよりも退職戦略を考えるのも一手です。
パワーバランスが極端な職場では、正論を言うことが逆効果になることも。無理に正すより、心身の安全を守ることを優先し、証拠を整えた上で外から動くほうがリスクは少ないです。 - 「私の方がつらい」と訴えてくる上司に罪悪感を覚えてしまいます。
-
それは“情に訴える型”のDARVOで、心理的な支配の一部です。
あなたの訴えは無効ではありません。相手の“つらさアピール”に同情する前に、自分が本当に受けた被害を見つめ直してください。対話ではなく操作の可能性もあるため、感情の揺さぶりに巻き込まれないことが大切です。 - 「お前こそ問題だ」と言われ続けると自分が悪いように思えてきます。
-
“自分を責めすぎる”傾向はDARVO被害者に共通して見られます。
被害者が自責感情を抱くのは典型的な心理的影響です。事実と印象を切り分け、録音や記録に基づいて冷静に状況を判断してください。あなたが受けた苦しみを軽視せず、感情と向き合うことも忘れずに。 - 弁護士に相談するほど大ごとじゃない気がして、ためらっています。
-
“相談=訴訟”ではなく、あくまで助言を得るための手段です。
法律の専門家に話を聞くことで、自分の状況を客観的に整理でき、選択肢が広がります。無料相談も多くありますし、「まだ訴える気はないんですが…」というスタンスでOKです。早めに話を聞いてもらう方が損しません。 - ブラック企業を辞めた後、DARVO的な人がいない職場をどう見抜けばいいですか?
-
面接時に「自己責任論を強調しすぎる」「チームより個人の成果を重視する」発言が多い場合は注意です。
社員の定着率や口コミサイトの評価も参考にしてください。前職のハラスメント対応について質問したときに、曖昧な回答しか返ってこない企業も警戒すべきです。入社前の情報収集が、自分を守る第一歩です。 - パワハラの証拠を集めているのがバレたら逆に不利になりますか?
-
相手に知られることで逆上されたり、証拠隠滅を図られるリスクはあります。
録音や記録は「違法な手段」ではありませんが、できるだけ目立たない形で集めるのが基本です。特に上司や同僚が攻撃的な性格なら慎重に行動し、信頼できる第三者や専門家と連携しておくのが望ましいです。 - DARVOの加害者が「普段は良い人」なので周囲に信じてもらえません。
-
典型的な“二面性型加害者”です。外面が良い人ほど、信じてもらえないのはよくあることです。
加害者が「人当たりの良さ」で周囲を味方につけている場合、被害者の話は誤解や嘘だと扱われがちです。だからこそ、客観的な記録や第三者の視点を重視し、感情的な対立ではなく“事実”で周囲の認識を変えていく必要があります。 - 心理学的に見て、DARVOを使う人は変わる可能性がありますか?
-
可能性はゼロではありませんが、本人が自覚して努力する姿勢がない限りは非常に難しいです。
特に、自己愛傾向や支配欲が強いタイプは、責任を他人に押しつける行動が根付いていることが多いため、改善には専門的なカウンセリングが必要になります。職場で変わるのを待つより、距離を取る方が現実的な対策になるケースがほとんどです。 - ハラスメント窓口に相談したら、逆に報復されたという話を聞いて不安です。
-
その不安は現実的であり、事前にリスクと対策を把握することが重要です。
相談窓口の対応レベルには差があり、内部リークや加害者との癒着が起きるケースも報告されています。相談する際は「記録に残す」「外部窓口も並行して活用する」「退職準備を進めておく」といったリスク管理が鍵になります。 - 被害者側が“問題児扱い”されやすいのはなぜですか?
-
DARVO戦略の影響で、声を上げた側が“厄介者”に見えてしまう構図が作られるからです。
特に日本の職場文化では「波風を立てる方が悪い」という空気が強く、被害を訴える行動そのものが嫌がられる傾向にあります。これは制度や文化の問題であり、あなたの責任ではありません。孤立感を感じたときこそ、冷静に外部の支援を求めてください。 - 「そんなの被害妄想じゃない?」と言われて深く傷つきました。
-
その一言は、DARVOの拡散効果による二次加害かもしれません。
被害者の言葉を軽く扱い、問題をなかったことにしようとする周囲の言動も、心理的には十分な加害となります。あなたの感じた違和感や恐怖は“事実”として尊重されるべきです。否定されたことに責任を感じる必要はありません。 - 転職活動で「前職でのトラブル」はどう伝えたらいいですか?
-
詳細に語る必要はありません。「方向性の違い」「より健全な職場環境を求めて」といった形で伝えるのが無難です。
元職場の悪口に聞こえないように注意しつつ、前向きな転職理由を中心に構成しましょう。どうしても説明が必要な場合は、「組織体制とのミスマッチ」など柔らかい表現が有効です。 - 「我慢が足りない」と言われてしまうのが怖いです。
-
“我慢が正義”という価値観自体が、ブラック企業文化の温床です。
健全な職場では、問題提起は歓迎されます。むしろ「我慢できた人だけが正しい」とする発想は、自己犠牲と搾取の再生産につながります。あなたの決断を否定する権利は誰にもありません。 - 「自分の方が弱いから標的にされた」と思うと、情けなく感じます。
-
弱さが悪いのではなく、“その優しさ”や“真面目さ”が利用された可能性があります。
DARVO加害者は、自分を正当化しやすく、言い返してこなさそうな相手を狙う傾向があります。情けないどころか、あなたのまっとうさがターゲットにされた証でもあるのです。強さとは、逃げずに立ち向かおうとする意志そのものです。
その他の質問はこちらから:



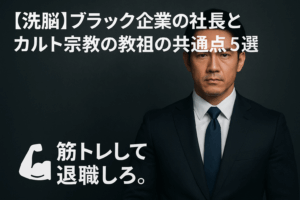


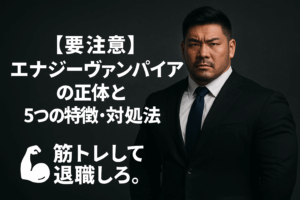

とは?特徴と対処法-300x200.png)


コメント