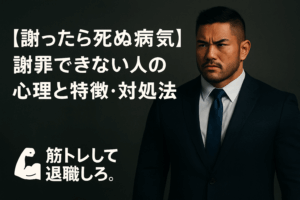自分のミスを他人のせいにする人間は、職場の信頼関係を崩壊させる。
暴言や陰湿な嫌がらせをする人間がいると、有能な人材から職場を去っていく。
部下を常に管理・監視しようとする人物は、職場の自主性と創造性を奪い取る。
はじめに
職場には、周囲の人々を疲弊させ、組織そのものを崩壊寸前に追い込んでしまう厄介な人物が存在します。
そうした人物は一見するとただの「嫌な人」「困った人」に思えるかもしれませんが、実は共通する特徴や心理傾向があります。
本記事では、ブラック企業を渡り歩いた当サイト管理人の実体験も交えながら、職場を崩壊させる人の特徴10選を科学的エビデンスとともに解説します。
 カワサキ
カワサキ「職場のヤバい人」に悩む方はぜひ参考にしてください。
職場を崩壊させる人の特徴10選
この記事では 職場を崩壊させる人の特徴10選 について、以下の内容で解説します。



データや研究結果を引用しながら、それぞれの特徴が職場に及ぼす悪影響を探っていきます。
① 責任転嫁する人



まず挙げられるのは、自分のミスや問題が起こった際に他人に責任を押し付ける人です。
こうした人は決して自分の非を認めず、トラブルのたびに「○○のせいだ」と周囲の誰かをスケープゴートにします。
一見自己防衛本能の表れにも思えますが、頻繁な責任転嫁は職場に深刻な悪影響を及ぼします。
例えば、責任のなすり付け合いが常態化した職場では心理的安全性が損なわれ、社員同士の信頼関係が崩壊します。



実際、2018年の研究ではこのような「責任追及(ブレーム)文化」が職場に蔓延すると、社員のモチベーション低下や離職率増加、組織パフォーマンスの低下につながることが示されていますpyrrhicpress.org。
当サイト管理人の過去の職場でも、



「とにかくお前が悪いことにして頭を下げろ」
と上司から指示されるケースがありました。
常に誰かを悪者にする環境では、真面目な人ほど疲弊し、健全な議論や改善提案も生まれなくなります。
② 暴言・モラハラをする人



暴言を吐いたり嫌がらせ行為(モラルハラスメント)をする人も、職場崩壊の大きな要因です。
上司や同僚から日常的に罵声を浴びせられたり、人前で執拗に批判されたりすると、被害者のメンタルヘルスは著しく悪化します。
日本の厚生労働省が2020年に実施した調査でも、過去3年間にパワハラ(権力による嫌がらせ)を1度以上受けた労働者は約31.4%にも上りましたg-office.or.jp。
さらに、そのようなハラスメント被害を受けた人のうち約13%が結果的に退職に至ったというデータもありますkaiketsu-j.com。
これは同調査でのセクハラ被害による退職率7%や、カスタマーハラスメントによる退職率3%を大きく上回る深刻な数字ですkaiketsu-j.com。



つまり、暴言やいじめを行う人物がいると、職場から有能な人材がどんどん去っていき、組織の崩壊につながりかねないのです。
科学的な分析でも、部下を怒鳴りつけたり嫌がらせをする上司のもとでは社員の仕事満足度が低下し、燃え尽き(バーンアウト)症状や退職意向が高まることが分かっています。
2017年にアメリカで行われた複数研究のメタ分析では、上司の暴言など「攻撃的なリーダーシップ」は部下の仕事満足度や組織へのコミットメントを有意に低下させ、心理的ストレスや離職意向を高めることが報告されていますqic-wd.org。
「毎日上司の怒鳴り声が聞こえるだけで胃が痛くなる」という状況は当サイト管理人も経験しましたが、そのような職場では社員は委縮して実力を発揮できず、生産性もだだ下がりになります。



暴言・モラハラをする人は組織の士気と生産性を破壊してしまうのです。
③ 過剰に支配的な人



必要以上に部下や周囲を支配・コントロールしようとする人も要注意です。
いわゆるマイクロマネジメント型の上司や独裁的な同僚は、細部に至るまで他人の行動を監視・干渉し、自分の思い通りに動かそうとします。
例えば毎時間の業務報告を強制したり(実際、管理人の元職場では「1時間に一回、この1時間の行動を社長に電話報告しろ」という異常な指示がありました)、業務時間外のプライベートな行動まで制限するケースもあります。
研究もこれを裏付けています。例えば権威主義的なリーダーシップ(部下に絶対服従を要求し、権限を集中させるタイプの上司)は、部下のパフォーマンスを下げたり職場環境を悪化させることが多いとされていますlink.springer.com。
2020年に中国で行われた研究では、上司が部下の感情を抑えつけるような独裁的手法を取ると、職場の雰囲気が悪化し部下の努力が削がれることが報告されていますlink.springer.com。
さらに権威的な上司の下では離職意向が高まることも指摘されていますlink.springer.com。



つまり、過剰に支配的な人物が上に立つと、人材の定着も難しくなり組織の存続自体が危ぶまれるのです。
管理人も経験しましたが、支配欲の強い上司の下では「とにかく上司の機嫌ばかり伺って仕事する」状態に陥りがちで、本来の業務に集中できなくなります。



過剰に支配的な人は組織の活力と健全性を蝕む存在と言えるでしょう。
④ 自己愛的・自己中心的な人
いわゆるナルシシスト(自己愛性人格)の傾向が強い人は、常に自分が賞賛の的でなければ気が済まず、他人の功績を横取りしたり失敗は他人のせいにする傾向があります。
部下や同僚より自分を優先し、共感や思いやりに欠けるため、周囲との信頼関係を築けません。
例えば、当サイト管理人の元同僚にも自己愛性パーソナリティ障害的な上司がおり、「社長を神様のように崇拝せよ」という謎ルールを部下に強要していました。



自分が常に称賛される状況を作り出したかったのでしょうが、部下からすればたまったものではありません。
部下も血の通った人間。
科学的には、自己愛的なリーダーの下で働く部下は、仕事満足度や幸福感が低く、ストレスや離職意向が高まることが示されています。
2020年にパキスタンの銀行員310人を対象に行われた研究でも、ナルシシストな上司を持つと部下の仕事満足度とウェルビーイング(心理的な幸福度)が有意に低下し、逆にストレスや「仕事を辞めたい」という意向が強まることが報告されていますfbj.springeropen.com。
一方で仕事のパフォーマンス自体には有意な影響が見られなかったとのことですがfbj.springeropen.com、自己愛的な上司は部下の心身を追い詰め、組織へのロイヤリティを下げてしまうのです。
さらに研究者は、自己愛の強い人は批判されると激しく攻撃的になったり(※後述の短気な人の特徴とも関連)、失敗時には他人を平然とスケープゴートにすると指摘していますfbj.springeropen.comfbj.springeropen.com。
まさに周囲を振り回し職場を混乱に陥れる典型的人物像です。
⑤ 倫理観が欠如している人



法律や規則を無視し、平気で不正行為に手を染める人も職場崩壊の引き金になります。
例えば、部下に無理なノルマ達成のため違法な手段を使うよう強要したり、労災隠し・帳簿改ざん・架空請求などコンプライアンス違反を指示する上司がこれに当たります。
当サイト管理人の過去の職場でも、「当日出勤していない社員の人件費を顧客に架空請求する」という明確な不正行為が横行していました。
それに異を唱えた直属の上司は上層部から圧力を受け、最終的には



「大金をもらったら犯罪をしてしまっても仕方ない」
と洗脳されてしまったほどです。



こうした倫理なき行動は、一歩間違えれば会社全体が社会的信用を失い経営破綻に至りますし、働く社員の心も離れていきます。
研究でも、上司の不誠実・非倫理的な行動は部下の精神的健康を害することが指摘されています。
2022年に発表されたある研究では、上司の非倫理的な言動が部下に強いネガティブ感情(怒りや不安)を引き起こし、その結果として部下の幸福度やメンタルヘルスを間接的に低下させることが確認されていますresearchgate.net。
さらに興味深いのは、上司からのサポート(支援)が手厚い環境であっても、上司が不正・非倫理的な振る舞いをしていると部下のストレスはむしろ増幅されてしまうという報告ですresearchgate.net。
これは「サポートしてくれる上司が不正をしている」状況が部下にとって大きな心理的葛藤・負荷になるためと考えられます。
要するに、倫理観の欠如した人が職場にいると、その悪影響は周囲の善良な社員にまで波及し、組織全体の雰囲気が悪化してしまうのです。



不正行為を平気で行う人物とは一線を画し、自分の身を守ることが大切でしょう。
⑥ プライベートに干渉する人



勤務時間外のプライベート領域に過度に踏み込んでくる人も要注意です。
上司や同僚で、あなたのSNSや私生活に土足で入り込んできたり、休日や深夜でも平気で仕事の連絡をして「すぐ対応しろ」と要求してくるようなタイプです。
管理人の経験では、元上司が社員のプライベートSNSにまで介入し、投稿内容に口出ししてくるケースがありました。
こうした境界線を尊重しない行為は、社員のストレスを大きく高めます。
研究でも、就業時間外にメールやチャットで「常に応答を求められる状態」に置かれると、従業員のストレスホルモンが上昇し睡眠障害やメンタル不調をきたすとされていますeurekalert.org。
米国の研究では、勤務時間後にスマホで職務連絡が鳴り続けると、ネガティブな反芻(仕事の嫌なことが頭から離れない状態)や情緒不安、睡眠不足などの悪影響が出ることが報告されていますeurekalert.orgeurekalert.org。



逆に上司が「しっかり休んでいいよ」とワークライフバランスを尊重してくれる場合には、こうしたストレスが緩和されるという結果も出ていますeurekalert.orgeurekalert.org。
つまり、プライベートへの干渉が激しい人が職場にいると、社員は24時間仕事に縛られている感覚に陥り、心身の休息やリフレッシュができなくなります。
当たり前ですが、人間はオンオフの切り替えがないとパフォーマンスも落ちていきます。
実際、管理人も深夜に上司から電話が鳴り続けた経験がありますが、翌日は疲労困憊で仕事どころではありませんでした。



勤務時間外は本人の自由。
この基本的な線引きを侵してくる人物には注意し、必要であれば毅然と距離を置くことも検討すべきです。
あなたの人生はあなただけのものです。
⑦ 平気で嘘をつく人



平然と嘘をついたり隠し事をする不誠実な人も、組織を内側から壊していきます。
例えば「下請けは一切使っていない」と社外には嘘をつきつつ、実際には裏で下請け業者にやらせていたり、顧客との約束を破ってごまかすようなケースです。
管理人の以前の職場でも、



「当社は顧客情報の管理を徹底しています。」
とクリーンさを世間にアピールしながら、実際には中の人が同じ別会社へデータを横流ししていたといった嘘が横行していました。
このような二枚舌や隠蔽体質がまかり通ると、社員同士も次第に「誰も信用できない」と疑心暗鬼になり、チームワークは崩壊します。



信頼が損なわれた職場では、コミュニケーションも断片的になり、生産性の低下やミスの多発につながります。
研究によれば、職場における信頼は組織のパフォーマンスや従業員エンゲージメントに直結する重要な要素です。
米ギャラップ社の調査では「リーダーへの信頼」は従業員エンゲージメント(仕事への熱意)の最大の決定要因の一つであり、信頼が低下するとエンゲージメントも著しく下がると報告されていますgallup.com。
エンゲージメントの低下はイコール生産性の低下や離職増加を意味します。
平気で嘘をつく人が身近にいる状況では、この「職場の信頼貯金」がどんどん目減りしていくのです。
逆に、上司が部下に対し誠実で透明性のある対応をしている職場では、社員の仕事満足度や業績が向上する傾向があることも知られていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



職場を守るためにも、「嘘つき」は決して許容してはいけない存在なのです。
⑧ 短気ですぐキレる人



感情のコントロールができず、些細なことで激高する人も職場を壊す危険人物です。
例えば、部下のちょっとしたミスに対してすぐ怒鳴り散らしたり、会議で自分の意見が通らないと机を叩いて怒り出すようなタイプです。
こうした短気な人物が上司だと、部下たちは常に萎縮しビクビクしてしまい、自由に意見を言えなくなります。
当サイト管理人の元職場の社長も非常に短気で、オフィスで笑い声が上がっただけで社長室のドアを蹴破って出てきて灰皿を投げつける…という理不尽な光景がありました。



結果、社員は笑うことすら恐れて委縮し、職場の空気は最悪でした。
神奈川県のとあるリフォーム会社です。
心理学的にも、怒りっぽいリーダーは部下からの信頼と尊敬を失いやすいことが分かっています。
2018年に発表されたリーダーシップ研究では、職場で怒りを頻繁に表出する上司は部下から「信用できない」「非効果的だ」と見なされ、職場の機能不全を引き起こすことが報告されていますioatwork.comioatwork.com。
一方、まったく怒りを見せない上司が最も有能だと評価される傾向も示されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



つまり、理不尽にキレ散らかす上司ほど評価が下がり、周囲のパフォーマンスも低下するのです。
短気な人がいる職場では、部下は委縮して報連相(報告・連絡・相談)が滞りがちになります。
その結果、問題の発見や共有が遅れ、ミスやトラブルが拡大してしまう恐れもあります。



短気ですぐキレる人は、その場の雰囲気だけでなく組織の信頼関係や問題解決能力まで壊してしまうのです。
⑨ 他人を見下し尊重しない人



同僚や部下を平気で見下したり、人を人とも思わない言動をする人も要注意です。
例えば部下の意見を聞かず「どうせお前には無理だ」などと侮辱したり、陰で「あいつは使えない」などと他者を格付けするタイプです。
こうした人は根底に他者への共感やリスペクトが欠けており、結果としてパワハラや差別的言動にもつながりやすい特徴があります。
管理人の過去の職場でも、社長が気に入らない社員に対し人前で「お前は本当にバカだな」などと罵倒し、挙句の果てにはある同僚のズボンを皆の前で無理やり下ろすという人格否定的な辱めを行ったことがありました。
他人を人間として尊重しない行為は、その場にいた周囲の社員の心にも深い傷を残し、職場全体の士気を大きく下げました。



その同僚は結局その翌日に出社しなくなりました。
学術的にも、上司から軽蔑的・侮辱的に扱われた経験は被従業員のメンタルヘルス不調やPTSD症状のリスク要因になると指摘されています。
また、同僚間でも誰かを見下す風潮がある職場では、チームの協調性が損なわれ生産性が低下することが分かっていますpyrrhicpress.org。
人は自分を尊重してくれる相手に対しては協力的になりますが、見下してくる相手には心を閉ざしてしまうものです。
他人を見下し尊重しない人が社内にいると、優秀な人ほど嫌気がさして辞めていき、残ったメンバーも互いに不信感を抱えてギクシャクしてしまいます。



「どんな相手に対しても基本的な敬意を払う」というのは職場では当たり前のマナーですが、それができない人間が一人いるだけで組織全体の和が乱れてしまうのです。
自分より立場が弱い人にも思いやりを持てるかどうかは、その人の人間性を測る重要な指標と言えます。



職場では上下関係に関わらずお互いをリスペクトすることが大切ですが、それができない人物は組織にとって大きなリスクとなります。
⑩ 部下を消耗品扱いする人



最後に、部下や同僚をあたかも消耗品のように扱い酷使する人です。
いわゆる「人使いが荒い」上司で、部下の能力や限界を無視して常軌を逸した長時間労働や無休出勤を強要します。
当サイト管理人自身、180日間連続勤務を強いられ心身ともにボロボロになった経験がありますが、まさに部下を歯車扱いするブラック上司の下ではこのような無茶がまかり通ります。



過労死(Karoshi)という言葉が国際的にも通じるほど、長時間労働の弊害は日本社会でも深刻。
厚生労働省と国際機関の共同研究によれば、1週間に55時間以上働く労働者は、標準的な35~40時間労働の人に比べ脳卒中のリスクが約1.3倍に高まるとされています。
また精神面でも、長時間労働はうつ病発症リスクを高めることが多くの研究で報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
例えば日本の研究では、週80~99時間勤務する人は週60時間未満の人の約2.8倍、週100時間以上働く人は約7倍もうつ病になるリスクが高いことが明らかになっていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



これは驚くべき数字ですが、裏を返せば「それだけ過度な労働は人間を壊す」という現実を示しています。
部下を消耗品扱いする人がトップにいる職場では、社員は疲弊し切って正常な判断もできなくなり、最悪の場合命を落とす危険さえあります。
さらに、無理な長時間労働下では生産性も低下しミスや事故が増えるため、企業にとってもデメリットしかありません。
にもかかわらず「根性論」で部下を酷使する人がいる場合、その職場は長く続かないでしょう。
管理人の古巣でも、激務に耐えかねた「まともな人ほどすぐ辞める」状態で、新人も定着せず常に人手不足→さらに残った人にしわ寄せ…という負のスパイラルに陥っていました。
一人ひとりの限界や健康を無視し、数字や利益のためだけに働かせ続ける人物は、組織をじわじわと崩壊へ導く存在です。



働く側としては、自分自身が消耗し尽くされてしまう前に然るべき対処(部署異動の相談や転職など)を検討することを強くおすすめします。
まとめ
職場を崩壊させる人の特徴を10個挙げましたが、いかがでしょうか。
いずれの特徴も、程度の差こそあれ



「自分さえ良ければ」
「目先のことさえ上手くいけば」
という利己的で近視眼的な思考に根ざしているように思えます。
こうした人物が組織に存在すると、真面目に頑張る周囲の人ほど大きなストレスを抱え、心身を病んでしまいがちです。
もしあなたの職場にも今回挙げたような「ヤバい人」がいて、自分の努力ではどうにもならない状況なら、決して無理をせず然るべき行動を取ってください。
社内の信頼できる人事や上司に相談する、産業医や労働組合に相談する、あるいは退職・転職も選択肢に入れるべきです。
あなたの心と体は何にも代えがたい大切な財産です。
職場は本来、皆が安心して力を発揮できる場であるべきです。



それを壊すような人とは適切な距離を保ち、自分自身を守ることが何よりも大切です。
よくある質問
- なぜ「責任転嫁する人」が職場にいると組織が崩壊するのですか?
-
責任転嫁は職場の信頼関係を破壊し、改善の機会を奪うからです。
責任を押し付けられた側は不信感を抱き、チーム内に疑心暗鬼が広がります。2018年の実証研究では、「責任追及文化」が従業員満足度や心理的安全性を大きく損なうことが示されています。信頼と建設的な対話がない職場は、いずれ崩壊の道をたどります。 - モラハラや暴言が与える心理的影響にはどのようなものがありますか?
-
暴言・モラハラはPTSDやうつのリスクを高め、離職を促進します。
システマティックレビュー(2021)では、職場での精神的暴力にさらされた従業員は、うつ症状・睡眠障害・身体的不調を訴える確率が有意に高いと報告されています。日本でも、モラハラが退職理由の上位に位置しています。 - 支配的な上司の下で働くと、なぜ自主性が失われるのですか?
-
過剰な監視は内発的動機づけを削ぎ、学習性無力感を引き起こすためです。
2020年の中国の研究によれば、権威主義的リーダーの下では部下の心理的リアクタンス(反発感)が強まり、生産性と満足度が低下します。支配型マネジメントは短期的な成果には寄与する場合もありますが、持続的な組織成長を妨げます。 - 自己愛が強い人はなぜ職場を混乱させるのですか?
-
自分の評価を守るために他人を貶める傾向があるからです。
自己愛的パーソナリティは、批判に極端に過敏で、ミスを認めず責任を他者に押しつけます。2020年のパキスタンの研究では、自己愛の強い上司の下では部下のバーンアウトやストレスレベルが顕著に高いことが示されています。 - 非倫理的な行動をする人がいると、なぜ周囲にも悪影響が出るのですか?
-
倫理的逸脱は模倣され、職場全体のモラル低下を招くからです。
メタアナリシスによると、不正を行う上司や同僚の存在は、観察者にも「どうせバレない」という認知の歪みを広げ、不正行動の連鎖を引き起こすとされています。結果的に、組織の評判・法的リスク・内部崩壊につながります。 - なぜプライベートへの干渉が職場崩壊の一因になるのですか?
-
勤務外の束縛はメンタル回復の時間を奪い、燃え尽きに直結するためです。
米国の研究では、オフタイムへの仕事の侵入(例:夜間メール)は、情緒不安や睡眠障害の発生率を約1.6倍に高めると報告されています。ワークライフバランスを尊重しない文化は、人材流出の温床になります。 - 嘘をつく人が職場に与える実害にはどのようなものがありますか?
-
信頼の喪失はチームワークや生産性に深刻な悪影響を与えます。
米ギャラップ社の調査では、「上司を信頼できるかどうか」は従業員のエンゲージメントと正の相関があり、信頼が低い職場は離職率が20%以上高まる傾向があるとされています。透明性は組織の基盤です。 - 感情をすぐ爆発させる上司に対して、部下はどう反応するのでしょうか?
-
恐怖による萎縮が起こり、報連相や挑戦的意見が出にくくなります。
リーダーの怒り表出に関する2018年の研究では、怒鳴る上司は「非効果的」「信頼できない」と評価されやすく、問題報告やリスク共有を回避する傾向が強まるとされています。これが組織の事故や炎上の引き金になります。 - 他人を見下す人がチームにいると、何が問題なのでしょうか?
-
心理的安全性が損なわれ、協働が困難になります。
Googleが行ったプロジェクト・アリストテレスでも、チームの成功に最も重要なのは「心理的安全性」だとされました。見下される環境では誰も発言しなくなり、知識共有・創造性・迅速な対応すべてが損なわれます。 - 部下を消耗品扱いする人が組織に与える長期的な損失は?
-
離職・過労・事故率の上昇により、組織全体のコストが膨らみます。
WHOとILOの共同調査(2021)では、週55時間以上働く人は、心疾患で死亡するリスクが約1.35倍に高まるとされています。また、日本の研究では、週100時間超の勤務でうつリスクが約7倍に達するとの報告もあります。 - 職場に1人だけ崩壊させるような人物がいても、全体に影響は出るのでしょうか?
-
1人の有害な人物でも、周囲6人以上に悪影響を与えるという研究結果があります。
2005年の米スタンフォード大学の研究では、いわゆる「toxic worker(有害な従業員)」が1人いるだけで、チームの生産性が最大30〜40%低下することが確認されています。これは職場のムードやコミュニケーション効率が間接的に破壊されるためです。 - 有害な同僚に直接注意すると、さらに関係が悪化しませんか?
-
相手の性格特性を見極めずに注意すると、逆効果になることもあります。
特に自己愛傾向が強い人に対しては、直接の指摘が攻撃へのスイッチとなりやすいとする心理学研究があります(DSM-5-TR, 2022)。職場の対人トラブル対応では「境界線を引く」「証拠を残す」「第三者を挟む」が基本です。 - モラハラを訴えるにはどのような証拠が必要ですか?
-
録音・日付入りのメモ・メールのやり取りなど、客観的記録が重要です。
厚生労働省のハラスメント対策指針では、記録の重要性が明記されています。特に音声記録は効果的で、裁判や労基署申告の際にも証拠として採用される可能性が高くなります。内容に一貫性があることもポイントです。 - なぜ「まともな人ほど早く辞める」現象が起きるのでしょうか?
-
職場の不正や異常性を正しく認識できる人ほど、早期に離脱する傾向があります。
倫理的感受性や価値観のギャップが強くなると「組織と自分は合わない」と判断しやすくなります(Ethical Climate Theory, Victor & Cullen, 1988)。反対に、長く残ってしまう人ほど環境に順応(あるいは無関心)してしまっている場合もあります。 - なぜ自己愛の強い人は表面的には評価されやすいのでしょうか?
-
初期段階では自信やカリスマ性に見えるため、上層部から誤認されやすいのです。
自己愛性パーソナリティは魅力的に映る「自己演出スキル」が高いという研究があります(Back et al., 2010)。しかし長期的には共感性の欠如や責任回避行動が明らかになり、チームへの悪影響が顕在化します。 - 管理職が「短気ですぐキレる」場合、部下はどう対処すればよいですか?
-
“機嫌管理”ではなく、“刺激を減らす距離感”を優先してください。
アンガーマネジメント研究では、怒りっぽい上司に対し部下が自律神経を過度に使いすぎて疲弊する傾向があると報告されています。可能であれば間に他者を介在させ、直接の衝突を減らす環境設計が有効です。 - 不正行為を目撃した場合、告発するか黙認するかで迷っています。どうすべきですか?
-
法令違反や倫理違反に関わる場合は、社内通報窓口や外部機関への相談が推奨されます。
OECDの「内部告発保護に関する指針」では、通報者保護が国際的に強調されています。日本でも2022年に「公益通報者保護法」が改正され、一定の条件下では身元保護と報復禁止が法的に定められました。 - 境界を越えてくる上司(SNS・休日連絡)にどう対処すべきですか?
-
「業務連絡の時間帯・頻度の限度を明示する」ことが心理的負荷の軽減に有効です。
EUでは「つながらない権利(Right to Disconnect)」が法制化される国も出てきました。研究でも、就業時間外の連絡に一貫して対応する人ほどバーンアウトのリスクが2.1倍高くなることが報告されています。
その他の質問はこちらから:
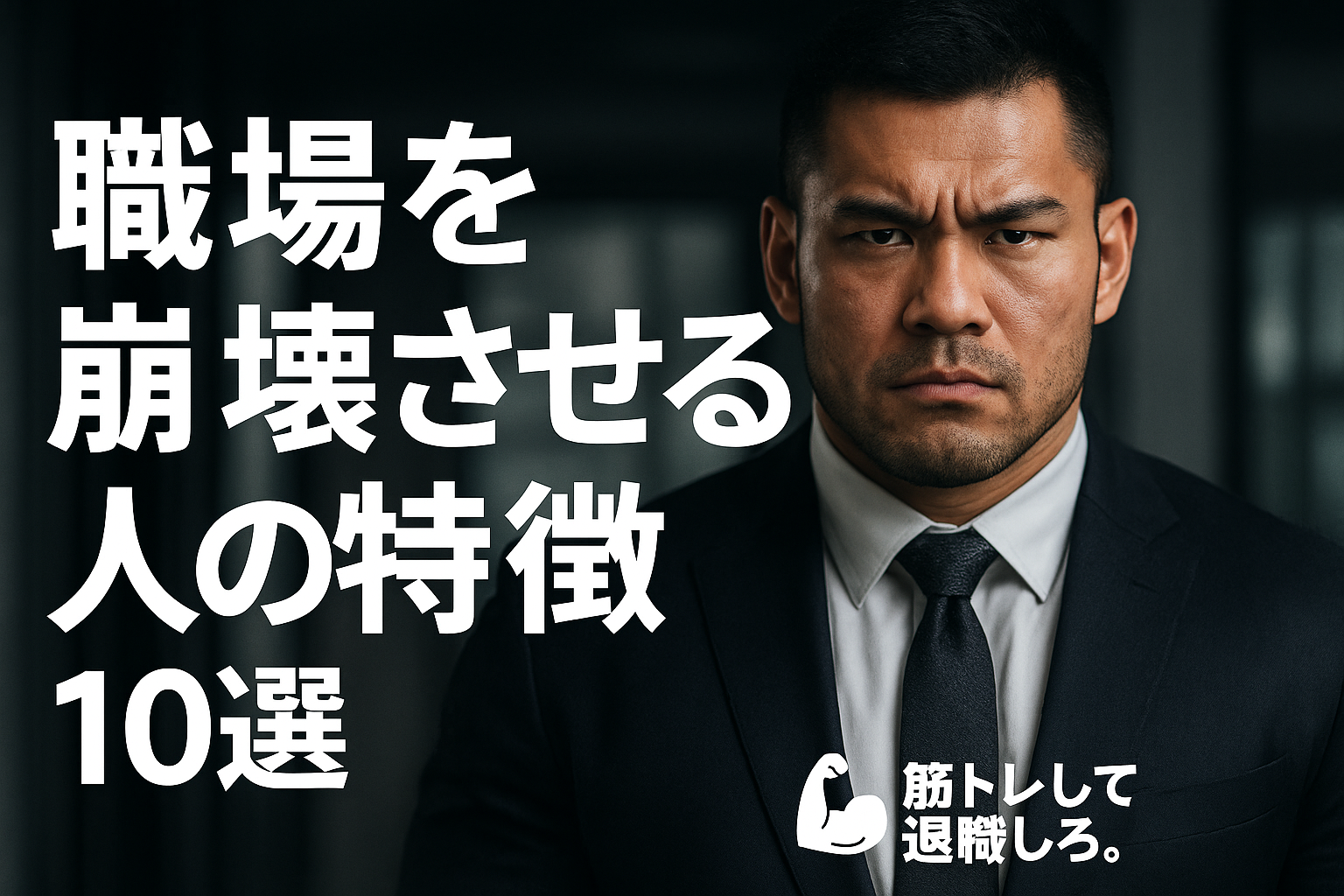




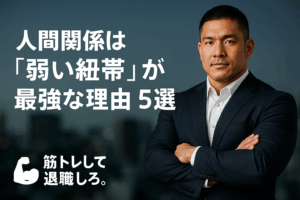
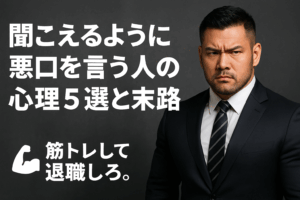



と孤立(isolation)の違いについてわかりやすく解説-300x200.png)