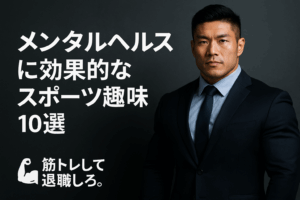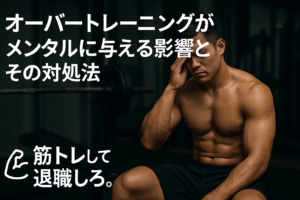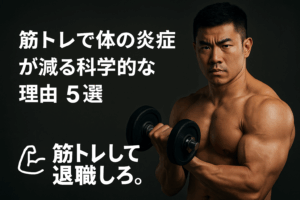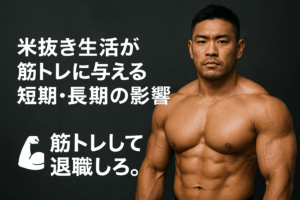エネルギーの単位であり、食品表示のkcalは1000cal、1 kcal=4.184 kJである。
糖質4 kcal/g・タンパク質4 kcal/g・脂質9 kcal/g・アルコール7 kcal/gで、タンパク質の食事誘発性熱産生は約20〜30%と高い。
基礎代謝が総消費の中心で、活動と食事誘発性熱産生を加えた総消費と摂取の差が体重変化を決め、20〜60歳の総消費は概ね一定である。
カロリーってそもそも何?その正体と意味を知ろう
20代から30代のほとんどをブラック企業で過ごしていた管理人のカワサキです。
当時は違法な180日連勤などで心身ともに疲弊し、食事もおざなりで「カロリー」のことなど深く考える余裕もありませんでした。
しかし筋トレを始めてから、改めてカロリーって何?と疑問がわいたのです。
実は「カロリー」という言葉は日常的に使われますが、その正体を正確に理解している人は多くありません。
 カワサキ
カワサキここではカロリーの本来の定義から、エネルギー代謝や栄養素との関係まで、科学的根拠をもとにわかりやすく解説します。
まず結論から言うと、カロリーとはエネルギーの単位です。
1カロリー(cal)は本来、「1グラムの水の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量」と定義されたものですbritannica.com。



ただし、食品などで使う「カロリー」は通常この1000倍の単位(キロカロリー:kcal)を指しますbritannica.com。
例えば「100 kcal」と書かれたおにぎりは、本当は100,000 cal(小カロリー)に相当するわけですね。
ところでカロリーという単位は国際的な標準単位(SI単位)ではジュール(J)に置き換えられています。
1 cal = 約4.184 Jであり、現在の日本の計量法でも1 calを正確に4.184 Jと定義していますja.wikipedia.org。



日本では1999年の計量法改正により、カロリーという単位は「人や動物が摂取・消費する熱量」を測る場合に限り使用できる特殊単位として認められておりja.wikipedia.org、主に食品のエネルギー表示など栄養分野で使われ続けています。
カロリーと代謝の関係 – 基礎代謝とエネルギー消費
人間が1日に消費するカロリーの大部分は、実は何もしていなくても使われています。
安静にじっとしていても心臓を動かし呼吸し体温を維持するなど生命活動にはエネルギーが必要です。



この生命維持に最低限必要なエネルギー消費を基礎代謝といいます。
基礎代謝量は個人差がありますが、成人では1日に男性で約1500 kcal、女性で約1100 kcal前後になりますmed.or.jp(30〜49歳の平均)。
これだけで1日の総消費エネルギーの50〜70%を占めるとも言われていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



残りが日常の活動や運動による消費、そして食事の消化吸収に使われるエネルギーです。
例えば厚生労働省の基準では、30〜49歳の男性(70 kg)で基礎代謝約1570 kcal/日、女性(53 kg)で約1170 kcal/日とされていますmed.or.jp。
これに活動レベルを掛け合わせて1日の総消費カロリーを見積もります。
活動レベルが低い(座り仕事中心)の場合は基礎代謝の約1.5倍、適度に体を動かすなら1.75倍、肉体労働や激しい運動習慣がある人は2倍程度ですmed.or.jp。



下表はその例です。
●成人男女における基礎代謝と活動レベル別の1日カロリー消費量(目安)
| 活動レベル | 30〜49歳男性 (70kg) | 30〜49歳女性 (53kg) |
|---|---|---|
| 基礎代謝 (安静時) | 約1570 kcal/日 | 約1170 kcal/日 |
| 低い (座位中心) | 約2350 kcal/日 | 約1750 kcal/日 |
| ふつう (適度に動く) | 約2750 kcal/日 | 約2050 kcal/日 |
| 高い (肉体労働・運動) | 約3140 kcal/日 | 約2340 kcal/日 |
※厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に基づく推定値med.or.jpmed.or.jp。
なお、基礎代謝量は筋肉量や年齢によって変わります。



筋肉が多い人ほど基礎代謝が高く、逆に加齢とともに筋肉が落ちると基礎代謝は下がりがちです。
ただし「歳を取ると急に太りやすくなる」というイメージは必ずしも正しくありません。
2021年に世界29カ国・6421人を対象に行われた国際研究では、20〜60歳の間は男女とも総消費エネルギー(体重あたり)がほぼ一定で、その後60歳以降に緩やかに低下することが報告されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



つまり中年期の「代謝の落ち」は従来考えられていたより緩やかで、日々の活動量や食生活の変化の影響が大きい可能性があります。
また、食事をすると消化や吸収にもエネルギーが使われます。



これを食事誘発性熱産生(Thermic Effect of Food; TEF)と呼び、1日に消費されるエネルギーの約10%程度を占めますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
意外かもしれませんが、食品の種類によってこの消化に使うカロリーの割合は異なります。
一般にタンパク質は食べたエネルギーの約20〜30%が熱として消費され、糖質では約5〜10%、脂質はわずか0〜3%ほどですpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



例えば同じ100 kcalでも、脂質メインの食事よりタンパク質メインの食事の方が消化にエネルギーを使う分、正味で利用されるエネルギーはやや少なくなります。
栄養素ごとのカロリーの違い – 糖質・脂質・タンパク質
食品のカロリーは、その中に含まれるエネルギー産生栄養素(三大栄養素)によって決まります。
炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質はそれぞれ体内でエネルギー源となりますが、1グラムあたりのカロリーは異なります。
おおよそ糖質は4 kcal/g、タンパク質も4 kcal/g、脂質は9 kcal/gですajinomoto.co.jp。
この数値は19世紀にアメリカのウィルバー・オリン・アトウォーター氏によって様々な食品を燃焼させて測定されたもので、アトウォーター係数と呼ばれますja.wikipedia.org。



ちなみにアルコールは1 gあたり約7 kcalあります。
脂質はグラムあたりのカロリーが高いぶん摂りすぎに注意が必要ですが、だからと言って「カロリー=悪者」ではありません。
体に必要なエネルギーや栄養素をバランスよく摂ることが大切です。
例えば糖質は脳や筋肉の主要なエネルギー源、タンパク質は筋肉や臓器の材料、脂質はホルモンの合成や細胞膜の構成に不可欠です。



それぞれ適量を確保することが健康維持には重要です。
カロリーと体重管理・筋肉づくりの関係 – エネルギー収支の基本
トレーニーにとってカロリー管理はダイエットや筋肉増量の鍵です。
シンプルに言えば、摂取カロリーが消費カロリーを上回れば体重は増え(余剰エネルギーは脂肪として蓄えられる)、逆に消費が上回れば体重は減るというエネルギー収支の原則がありますnhs.uk。
このエネルギー収支の考え方は、多くの研究で一貫して支持されています。



実際、カロリーを減らせば体重が減少することは数多くの研究で示されています。
例えば、2014年にアメリカで行われた53件のRCT(無作為化比較試験)を統合したメタ分析では、どのようなダイエット法でも摂取カロリーを制限すれば体重が減少し、その効果に有意差はないと報告されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



つまり、糖質制限でも脂質制限でも「食事から減らしたカロリー量」が減量幅を決めていたのです。
とはいえ、栄養素のバランスや筋肉量も無視できません。
極端なカロリー制限だけでは筋肉まで落ちて基礎代謝が下がってしまい、リバウンドしやすくなります。
またタンパク質を十分に摂ることで筋肉を維持しやすくなり、先述の通り消化時の消費エネルギーも増えるため減量中の助けになりますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
よくある質問
- カロリーとkcal・Calの違いは何ですか?
-
カロリーはエネルギーの単位で、食品の「kcal」はキロカロリーです。 1 kcal=4.184 kJで、Cal(大文字)は栄養文脈でkcalを指す表記です。日本では栄養用途に限りカロリーの使用が認められています。
- kcalとkJはどちらで考えれば良いですか?
-
日本の日常と食品表示はkcalで十分です。 研究や国際資料ではkJも使われるので換算(kcal×4.184=kJ)を覚えておくと便利です。どちらも同じエネルギー量を示す単位です。
- 糖質・脂質・たんぱく質・アルコールの1gあたりカロリーは?
-
目安は糖質4・たんぱく質4・脂質9・アルコール7 kcal/gです。 これはアトウォーター係数に基づく国際的な換算で、食品ごとの誤差はありますが実務上の標準として広く用いられます。
- 基礎代謝(BMR)の平均はどのくらいですか?
-
成人のBMRは体格や性別で変わります。 例として30〜49歳の基準体格では男性約1570 kcal/日(70kg)、女性約1170 kcal/日(53kg)が目安です。推定は個人差がある点に注意してください。
- 1日の総消費カロリー(TDEE)はどう見積もりますか?
-
基本は「BMR×活動レベル+食事誘発性熱産生(TEF)」です。 活動レベルは座位中心1.50、ふつう1.75、活動的2.00が目安で、これによりTDEEが大きく変わります。
- 年齢で代謝はどれくらい変わりますか?
-
総消費エネルギーは20〜60歳で概ね安定し、その後に低下します。 二重標識水法の大規模データでは、この年齢帯での大きな落ち込みは見られず、60歳以降に緩やかに下がる傾向が示されています。
- 食事誘発性熱産生(TEF)はどの程度を見込めますか?
-
TEFは1日の消費の約10%で、たんぱく質は20〜30%と高めです。 脂質は低く、糖質は中程度です。食事構成によって差が出るため、減量期は高たんぱく食が有利になる場面があります。
- パッケージのカロリー表示に誤差はありますか?
-
あります。原則±20%の許容差が認められています。 低含有の栄養成分や熱量では特例の範囲が設定され、「推定値」等の表記要件も最新ガイドラインで整理されています。
- 筋トレで安静時代謝(RMR)は上がりますか?
-
上がる可能性があります。 系統的レビューでは抵抗運動がRMRを有意に押し上げ(平均+約96 kcal/日)、長期トレーニングで数%の増加が示された報告もあります。個人差は大きいです。
- 減量で最優先すべきことはカロリー収支ですか?
-
はい。まずは摂取<消費を作ることが最優先です。 2014年のメタ分析では食事法の名前に関係なくエネルギー制限量が減量幅を左右する傾向が示され、実務面でもエネルギー収支が基本です。
- NEAT(非運動活動)は体重管理でどれほど重要ですか?
-
NEATは人によって1日あたり最大約2000 kcalも差が出る重要な消費源です。 デスクワークでも立ち歩き・家事・階段などで積み上がります。運動時間が確保しにくい人ほど、座位時間を減らし小さな動きを増やすだけで総消費を底上げできます。
- 調理方法で実際に摂るカロリーは変わりますか?
-
揚げ調理は水分が抜け油を吸うためエネルギー密度が上がりやすいです。 同じ食材でも「茹でる・蒸す」は比較的低エネルギーで、パン粉衣や長時間の油調理は脂質の取り込みが増えます。メニュー設計では揚げ物の頻度と量を抑えるのが実務的です。
- 液体カロリーは固形より太りやすいのですか?
-
液体は固形より満腹感が弱く、エネルギー補償が不十分になりがちです。 系統的レビューでは、半固形・固形の方が次の食事で自然に摂取を抑えやすい傾向が示されます。甘味飲料は特に注意し、たんぱく質や食物繊維を含む固形の前菜で置き換えるのが安全です。
- 睡眠不足は食欲や摂取カロリーを増やしますか?
-
はい、短期でも摂取が約300 kcal/日増えるエビデンスがあります。 逆に睡眠時間を延ばす介入では約−270 kcal/日の自発的減少が見られました。トレーニーでもカロリー設計と同じくらい睡眠衛生が重要です。
- アルコールは7 kcal/g以外に代謝へ悪影響がありますか?
-
飲酒は脂肪酸の酸化を抑え、脂肪の貯蔵を促します。 無作為化試験や代謝室研究では、飲酒時に脂肪酸化が有意に低下しました。熱産生はわずかに上がっても体脂肪減少には寄与しにくいので、減量期は量と頻度を管理しましょう。
- 人工甘味料(NSS)は体重管理に有効ですか?
-
長期の減量目的では推奨されません。 WHOは2023年ガイドラインで、成人・小児とも長期の体脂肪減少に有益性は示されないと結論しました。短期RCTでの体脂肪低下はあっても、前向き研究では体脂肪増加と関連する報告が目立ちます。
- 食物繊維は同じカロリーでも太りにくさに効きますか?
-
可溶性食物繊維は満腹感を高め、体重や腹囲の低下に寄与します。 RCTをまとめたレビューやメタ解析で、胃排出の遅延や血糖・インスリン反応の改善が示されています。減量期は汁物・豆類・海藻・オート麦などで摂取量を底上げしましょう。
- 高たんぱく食は食欲とエネルギー収支にどう効きますか?
-
高たんぱくは満腹感とTEFを高め、総摂取を下げやすいです。 メタ解析や総説で、短期では食欲抑制ホルモンの上昇や摂取量の減少が確認されています。長期効果は個人差があるため、PFCバランスは筋トレ量と体重目標に合わせて微調整してください。
その他の質問はこちらから: