この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「なんであの人、いつもあんなに威圧的なんだ…」
「同僚が常にマウント取ってきて気疲れする」
「取引先の態度が強すぎて、萎縮してしまう」
 カワサキ
カワサキ本当に成熟している人は、そもそも人に威圧的な態度を取りません。
そんな態度を取っている時点でお察し。
威圧的な人の多くは、自己愛・マキャヴェリズム・支配欲といった“ダークトライアド”傾向を持ち、相手をコントロールすることで自尊心を保っている。
タイプごとに対処法は異なるが、共通して有効なのは ①記録を残す ②感情をぶつけない ③孤立せず共有する の3点。
環境が変わらないなら転職は逃げではない。自分を守る選択として、専門家相談や退職手続きも含めた現実的な一手が必要。
職場で威圧的な態度を取る人の心理に興味はありませんか?
本記事では、上司・同僚・取引先などに見られる5タイプの「威圧的な人」の正体を科学的に解説します。



なぜ人は他人を威圧するのか?どんな性格傾向があるのか?
そして、それにどう対応すれば心を守れるのか?というお話です。
メタアナリシスや公的データに基づいた信頼できる内容で、すぐに使える具体的な対処法も紹介します。



理不尽な人間関係で心が削られている方はぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
はじめに
職場における威圧的な人物(上司・同僚・取引先など)は、いじめやパワハラの加害者となりやすく、被害者の心身に深刻な悪影響を与えます。
欧州の調査では、従業員の約3~4%が週1回以上の「深刻ないじめ」を経験し、9~15%が月1回程度の「時折のいじめ」を経験していることが示されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
日本でも同様の規模で、過去6カ月間に約9~15%の労働者がいじめを経験したと報告されていますbmcpsychology.biomedcentral.com。
被害者は抑うつやPTSDなど重度の精神疾患リスクが高く、例えば日本の公務員2194名の調査では、「週1回以上いじめを受けた人」の心理的苦痛リスクは8倍、PTSD症状リスクは12倍に上るという結果が出ていますbmcpsychology.biomedcentral.com。



このように被害者保護や対処法は重要課題です。
ここでは、職場でよく見られる「威圧的な人」の心理的タイプを5つに分類し(権力乱用型・自己中心型・裏切り・妬み型・完璧主義型・外部ハラスメント型)、それぞれの特徴と具体的な対処法を解説します。



また、共通する効果的な対処法として、感情的になりすぎないことや同僚・上司への相談の重要性なども科学的根拠を交えて紹介します。
威圧的な人の心理・正体 5選と対処法
ここでは威圧的な人の心理・正体 5選と対処法について、下記の内容で触れます。
1. 権力乱用型の上司・リーダー
心理・正体
権力乱用型の人物は、自分の立場や権限を最大限に利用して部下や周囲をコントロールしようとします。
研究からは、いじめ加害者はマキャヴェリアニズム(権謀術数的思考)やサイコパシー(良心の欠如)といったダークトライアドの特性が高く、誠実性や協調性が低いことが明らかになっていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
彼らは常に他者との比較で「自分の力」を測り、人間関係でも優位に立つことで自己価値を保とうとしますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



価値観の違いが背景にある場合も多く、「上下関係を重んじる古い慣習」を強く信奉している可能性があります。
具体的な対処法
- 事実の記録:攻撃的な言動や過剰な指示は逐一記録し、日時と状況を明確にしておく(メールやメモを活用)。後から相談・証拠に使えます。
- 落ち着いて応対:感情的に反撃すると逆効果です。言われたことを冷静に受け止め、可能なら相手が何を求めているか明確に質問する。「具体的に次に何をすればいいか教えていただけますか?」など具体的な指示を仰ぎましょう。
- 上司や労働組合への相談:直属の上司が権力乱用型なら、さらに上の管理者や労働組合に相談する。信頼できる先輩・同僚と状況を共有して支援を得ることも有効です。被害者には「強力で支援的なリーダー」が必要だと研究でも指摘されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
- 労働環境を利用:社内にハラスメント相談窓口や産業医がいれば利用する。パワハラ防止措置が法制化されており、会社には防止義務があります。自社の相談窓口を確認し、必要なら利用しましょう。
- 転職・配属替えも視野に:どうしても改善が見込めない場合は、新しい部署や会社を検討するのも手段です。心理的負担が健康に及ぶ前に環境を変える判断もあります。
2. 承認欲求・自己中心型の同僚・上司
心理・正体
自己愛が強く承認欲求の高い人物は、常に自分を中心に物事を考え、他人からの賞賛を求めます。



このタイプは「自分に都合の悪い情報や人間」は排除しようとし、周囲を威圧して自分を際立たせます。
前述の研究でも、いじめ加害者はナルシシズム(自己愛性)や自尊心の高さが指摘されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
なお、ナルシシズムにも「自己顕示型(明るく魅力的だが自己中心)」と「攻撃的サブ型(批判に敏感で攻撃的)」などの側面があり、威圧的になる場合があります。



価値観の違いとしては、「自分へのリスペクトこそ正義」と考える傾向が強いことが挙げられます。
具体的な対処法
- 相手の得意領域で話題を合わせる:自己顕示欲が強い相手には、まずは話を聞いてあげる姿勢を示すと鎮静化する場合があります。その後で「私の意見もお聞かせいただけますか?」と対等な意見交換を試みます。
- 事実ベースで冷静に反論:自己中心型は感情論に弱いため、事実や数字で反論すると効果的です。感情的ではなく「XでYと判断しました」のように論理的に話す練習をしましょう。
- 助けを求める:困ったときはすぐ相談。専門家研究でも、「助けを求める・相談する」スタイルのコーピングは、いじめ被害後の心理的苦痛を軽減する要素になるとされていますbmcpsychology.biomedcentral.com。
- 距離感を保つ:可能なら頻繁に一対一になる場を避ける。グループの中で議論し、他者のサポートを得る形で対処すると孤立を防げます。
- 相手のミスや弱点を指摘しない:自己愛者は批判に敏感です。あからさまに指摘せず、問題があれば「一緒に改善策を考えましょう」と協力的に提案する形を取ります。
3. 裏切り・妬み型の同僚
心理・正体
表面上は友好的でも、裏で陰口を言ったり噂を流したりする「二重人格」的な同僚は、しばしば自尊心の低さや嫉妬心が原因です。



自分より成功している同僚に対して妬みを抱き、攻撃的態度でバランスを取ろうとします。
社会心理学の研究では、いじめのターゲットは「倫理的で優秀」な人が選ばれることが多く、嫉妬深い人ほど加害者になる傾向が示唆されていますempowerwork.org。



価値観の違いとしては、協力より競争を重視し、「他人を蹴落とすことで自分を保つ」という考え方があります。
具体的な対処法
- 秘密・プライベートな情報を控える:自分の弱みや計画は不用意に話さない。信頼できる人以外にはプライベート情報を共有しないようにしましょう。
- 事実確認を徹底する:噂や悪口を聞いたら、一方的に信じず本人に確認する。憶測で行動を起こすと混乱が広がります。
- 仲裁者を立てる:職場の信頼できる先輩や上司に相談し、問題の直接解決を図ってもらう。第三者を介入させることで、当事者同士の感情的対立を防ぎます。
- ポジティブなコミュニケーション:相手が攻撃的でも毅然と対応。「それは誤解ですので、こういう意味でした」と冷静に説明し、ネガティブな言動に同調しない姿勢が重要です。
- 自分の評価を守る:業務成績や客観的な成果を示し、自分の仕事ぶりを周囲に周知する。実績や数字で自分の価値を説明できれば、噂の影響を抑えられます。
4. 完璧主義・コントロール型の同僚
心理・正体
自らに高い基準を課し、他人にも同じレベルを求めるタイプは、細かい指摘や監視的な言動で威圧感を与えることがあります。



完璧主義者はミスを極端に恐れ、安定志向が強いため、部下や同僚に過剰な規則遵守や迅速な報告を要求します。
背景には「自分のミスを他人のせいにしたくない」という不安や「自分だけが正しい」という価値観が潜んでいることが多いです。



自己統制欲が強いため、他者が自分の基準を満たさないと激昂しがちです。
具体的な対処法
- 手順や期限を明確化する:指示内容や期限が曖昧な場合はその場で具体的に確認します。「いつまでに」「どうすればよいか」を具体化し、後々の責任を明確にしましょう。
- 進捗をこまめに報告する:逐一報告することで相手の不安を解消し、批判をかわす効果があります。「中間報告」を習慣にし、相手に余計な疑念を抱かせないようにします。
- 相談を取り入れる姿勢を見せる:自分だけで判断せず、「〇〇さん、ここはどのように進めればよいでしょうか?」と確認すると相手のコントロール欲を和らげ、建設的な指示変更につながる場合があります。
- 自分も基準を守る:相手の求めるレベルをできる範囲で満たす努力を見せる。少なくとも報告や文書提出などでミスを見逃さない姿勢を示すと、威圧感が減ることがあります。
- 境界線を意識する:もし過剰な要求がエスカレートしたら、周囲に「ここまでは自分の役割」「これは自分の管轄外」と客観的に説明して、業務範囲の境界を示すことも必要です。
5. 顧客・取引先など外部からの威圧
心理・正体
職場外の人(顧客・取引先・患者家族など)が見せる威圧的な態度は、社内の人物とは異なり「自分は客だから権利がある」という価値観が背景にあります。
厚労省の調査では、職場で深刻な迷惑行為を受けた際、その82.3%が顧客(患者含む)からであり、うち50.2%で「大声や反社会的発言を伴う威圧的言動」が報告されていますmhlw.go.jp。
これは、日本の職場でも外部からのハラスメント(いわゆるカスタマーハラスメント)が非常に多いことを示します。



外部からの要求は業務範囲を超えることが多く、「断りにくい」という心理も相まって問題化します。
具体的な対処法
- 上司・会社で方針を統一:個人の判断で対応せず、会社の顧客対応マニュアルに従う。厚労省も各社が「顧客要求の妥当性」や「対応方針」を共有し、従業員を守る体制作りを推奨していますmhlw.go.jp。
- 毅然とした対応:誠実かつ礼儀正しく接しつつ、不当要求には「それは会社の方針外です」と明確に断る。エスカレートする場合は、すぐ上司や法務に報告し、警察相談も視野に入れます。
- 証拠記録:暴言や不当要求はメモや録音(職場ルールを守った範囲で)し、あとで上司に提示できるようにします。
- 相手を一人にしない:可能なら複数名で対応する。代理の者(上司など)も同席させ、一人で顧客対応しない体制を取ると安全です。
- 自他の安全確保:理不尽な要求が度を超す場合、「これ以上の対応は難しい」と告げ、早期に現場管理者を呼ぶ。店舗や事務所でも安全確保の手順を確認しておきます。
共通する効果的な対処法
5つのタイプに共通して言える効果的な対処法をまとめると以下の通りです。
記録と共有
威圧的言動があったら日時・発言・状況を簡潔に記録し、信頼できる同僚や上司に相談・共有する。



複数人で事実を確認することで、当事者間の主観的認識のズレを防げます。
助けを求める
先述の研究bmcpsychology.biomedcentral.comも示すように、同僚や上司にサポートを求めたり、ハラスメント外部窓口を利用するなど「助けを求める」スタイルは心理的負担を軽減しますbmcpsychology.biomedcentral.com。



一人で抱え込まず、第三者の協力を仰ぎましょう。
冷静な態度
感情的に反撃すると相手の攻撃性を煽り、自分のストレスも増えます。



深呼吸やトイレ休憩で一度頭をクールダウンするなど、衝動的な反応を避けましょう。
対話と目標共有
可能ならば対話の場を設け、「何が問題なのか」「どうすれば改善できるか」を相手と擦り合わせる。



相手が上司なら目標共有、同僚ならチームワーク強化など、お互いの期待値を明確化します。
逃げではなく正攻法
研究では、愚痴を言う・その場をただやり過ごす感情的・回避的な対処法(例えば「Focus on venting」「Behavioral disengagement」など)は、いじめ被害を増幅させる傾向があると示されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



むしろ、問題の「解決」に向けて動く(必要な場合は上司や第三者に相談する)ことが有効です。
自己防衛スキルの向上
アサーティブ・コミュニケーション(適切かつ尊重を伴った自己主張)やストレス管理法を学び、自己効力感を高めることも大切です。



メンタルヘルスを強化しておくことで、長期的なトラウマ予防になりますbmcpsychology.biomedcentral.com。
下表に、代表的な対処法とその効果・研究例をまとめます。
| 対処方法 | 効果・リスク | 研究例・引用 |
|---|---|---|
| 愚痴・不満を言う(感情任せ) | 被害に遭いやすくなる傾向pmc.ncbi.nlm.nih.gov | Van den Brande et al. (2017)pmc.ncbi.nlm.nih.gov |
| 回避(無視する・逃げる) | 心理的苦痛が増大しやすいbmcpsychology.biomedcentral.com | Tsuno et al. (2022)bmcpsychology.biomedcentral.com |
| 助けを求める(相談・支援要請) | 心理的苦痛リスクが低下するbmcpsychology.biomedcentral.com | Tsuno et al. (2022)bmcpsychology.biomedcentral.com |
| 目標志向・問題解決型 | 明確な統計データは少ないが、自尊感情低下の防止に有効と考えられる | – |
表: 代表的な対処法とその効果。主に「職場いじめと対処法」に関する先行研究よりpmc.ncbi.nlm.nih.govbmcpsychology.biomedcentral.comを参考に作成。
まとめ



いかがでしたでしょうか。
最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
この記事のまとめ
- 威圧的な人のタイプ:
権力乱用型・自己中心型・妬み型・完璧主義型・外部(顧客)型の5つに分類される。 - 共通する心理傾向:
支配欲・自己愛・嫉妬・過剰な不安・価値観の偏りが根底にあることが多い。 - 科学的知見からの示唆:
ダークトライアド傾向(マキャヴェリズム・ナルシシズム・サイコパシー)が加害者の性格と強く関連。 - 効果的な対処法:
感情的に反応しない、記録を残す、助けを求める、距離を取る、信頼できる人と共有する。 - カスタマーハラスメントへの対応:
顧客でも毅然と対応する。会社のマニュアルに従い、エスカレートする前に上司や専門窓口へ相談。 - 限界を感じたときの選択肢:
改善が難しい場合は、転職や退職代行を含む「自分を守る行動」が合理的な選択になりうる。 - 忘れてはいけないこと:
威圧的な人が変わる可能性は低く、自分の行動と選択こそが状況を変える鍵になる。



今回の記事は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 威圧的な人の心理的特徴は何ですか?
-
威圧的な人は、自己愛や支配欲、共感性の欠如といった「ダークトライアド」傾向を持つことが多いです。これらの性格特性は、他人をコントロールしようとする行動に現れます。職場での威圧的な態度は、組織の文化やリーダーシップのスタイルにも影響されるため、個人の性格だけでなく環境要因も考慮する必要があります。
- 威圧的な人に対して、どのように対応すればよいですか?
-
感情的に反応せず、冷静に対応することが重要です。具体的には、相手の発言や行動を記録し、必要に応じて上司や人事部門に相談することが効果的です。また、自分の感情をコントロールし、ストレスを溜め込まないようにするために、リラクゼーションや運動などのストレス対処法を取り入れることも有効です。
- 威圧的な上司の下で働くことがストレスになっています。どうすればよいですか?
-
まずは、自分の感情や体調の変化に気づくことが大切です。威圧的な上司の下で働くことは、心理的なストレスや身体的な不調を引き起こす可能性があります。信頼できる同僚や外部の相談機関に相談し、必要であれば専門家の支援を受けることを検討してください。また、転職を視野に入れることも、自分を守る選択肢の一つです。
- 威圧的な同僚との関係が悪化しています。改善する方法はありますか?
-
まずは、相手とのコミュニケーションを見直すことが重要です。威圧的な同僚との関係を改善するためには、冷静に話し合いの場を設けることが効果的です。また、第三者を交えてのミーティングや、上司への相談も検討してください。自分一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用することが大切です。
- 威圧的な取引先に対して、どのように対応すればよいですか?
-
ビジネスの範囲内で、冷静かつ丁寧に対応することが求められます。取引先との関係では、感情的な反応を避け、事実に基づいたコミュニケーションを心がけてください。また、上司や関係部署と連携し、組織としての対応方針を確認することも重要です。必要に応じて、契約内容の見直しや、取引条件の再交渉を行うことも検討してください。
- 威圧的な人が職場にいると、他の社員にも悪影響がありますか?
-
はい、職場全体の雰囲気や生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。威圧的な人の存在は、他の社員のモチベーション低下やストレスの増加を招くことがあります。また、チームワークの乱れや離職率の上昇にもつながるため、組織全体での対応が求められます。
- 威圧的な人との関係で、自分のメンタルヘルスが心配です。どうすればよいですか?
-
自分の心身の健康を最優先に考え、適切な対処を行うことが重要です。ストレスが蓄積すると、うつ病や不安障害などのメンタルヘルスの問題を引き起こす可能性があります。早めに専門家のカウンセリングを受けることや、信頼できる人に相談することをおすすめします。また、職場環境の改善や転職も検討してください。
- 威圧的な人に対して、法的な対応は可能ですか?
-
はい、場合によっては法的な手段を取ることができます。威圧的な行為がハラスメントやパワーハラスメントに該当する場合、労働基準監督署や弁護士に相談することが有効です。証拠として、相手の発言や行動を記録しておくことが重要です。また、会社の相談窓口やコンプライアンス部門にも報告してください。
- 威圧的な人が上司の場合、異動や部署変更を希望できますか?
-
はい、会社の人事制度によっては異動や部署変更を申請することが可能です。まずは、人事部門や上司の上司に相談し、現在の状況を説明してください。会社によっては、社員の健康や働きやすさを考慮して、異動を検討してくれる場合があります。ただし、異動が難しい場合は、転職も選択肢の一つとして考えてください。
- 威圧的な人との関係で悩んでいる場合、どこに相談すればよいですか?
-
社内の相談窓口や外部の専門機関に相談することをおすすめします。社内に相談窓口がない場合は、労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門機関に相談してください。また、メンタルヘルスの専門家やカウンセラーに相談することも有効です。早めの対応が、問題の深刻化を防ぐ鍵となります。
- 威圧的な人が「自分は正しい」と言い張るとき、どう対応すべきですか?
-
相手の主張に反論せず、客観的な情報や事実を提示する形で冷静に対応するのが効果的です。
威圧的な人は、自分の正しさに固執する傾向があります。直接の否定は火に油を注ぐことになるため、「事実ベース」で会話することが大切です。第三者の視点や数値などを使って対話を組み立てましょう。 - 威圧的な人と毎日顔を合わせる職場で、気持ちを切り替えるコツはありますか?
-
自分の“境界線”を明確にすることが、心を守る第一歩です。
たとえば「これは私の問題ではない」と意識することで、感情の巻き込まれを防げます。通勤時の音楽・筋トレ・深呼吸など、日々の“リセット習慣”も有効です。小さなルーティンが、継続的な心の防壁になります。 - 威圧的な人との関係は筋トレで改善されますか?
-
本人の性格が変わることは難しいですが、あなた自身のストレス耐性は筋トレで高まります。
複数の研究でも、運動によってストレスホルモン(コルチゾール)が減少し、感情コントロール力が向上することが示されています。相手を変えるのではなく、自分の内側を鍛える発想が有効です。 - 職場に複数の威圧的な人がいて板挟み状態です。どう乗り越えればいい?
-
味方を一人でも確保し、孤立しないことが最大のカギです。
人間関係の板挟みはストレスの温床です。中立な第三者や、信頼できる同僚と日常的に会話することで心理的安全性を保ちましょう。社外の相談窓口やSNS上の情報収集も効果的です。 - 威圧的な人に限って上司に気に入られていて、改善が望めません…
-
社内の“構造的問題”だと判断したら、異動や転職を視野に入れて行動しましょう。
権力構造に守られている人は、本人が変わらない限り改善は難しいです。その場合、自分が無理に適応するのではなく「環境を選ぶ」ことが現実的です。情報収集と小さな行動から始めてください。 - 「あなたのためを思って言っている」と言ってくる威圧型上司に悩んでいます…
-
その言葉の裏には“支配欲”が隠れている場合があります。
「善意の装い」はコントロールの常套手段です。内容が自分を傷つけるものであれば、その“言葉の目的”を冷静に見極めましょう。感謝する必要はありません。自分の価値基準を優先してください。 - 威圧的な態度をとる人が、急に優しくなるのはなぜですか?
-
それは“交互強化”と呼ばれる操作的な行動パターンの可能性があります。
一時的な優しさで相手を油断させ、次の支配行動に移るケースがあるため注意が必要です。特に自己愛的傾向が強い人に多く見られます。態度の急変に惑わされず、長期的なパターンで観察しましょう。 - 威圧的な人に反論しても無視されます。どう対処すればいい?
-
“正面突破”ではなく、“戦わずに回避する戦術”が有効な場合もあります。
無視や無反応は、相手が対話する気がない証拠です。こちらが何を言っても変わらないなら、その人を“変えようとすること自体”をやめて、業務上の必要最低限に留めて距離を取りましょう。 - 若手の私が、年上の威圧的な人にどう対処すべきか迷っています…
-
年齢より“役割”にフォーカスして、対等な立場で冷静に対応するのがポイントです。
年齢差があると、つい遠慮しがちですが、職場は対等な契約関係の場です。「私はこの業務を遂行するために働いています」といったニュートラルな立場を意識すると、不要な心理的な従属を防げます。 - 威圧的な人から逃げるのは“負け”ですか?
-
いいえ、“逃げる=負け”ではなく、“戦略的撤退”はむしろ賢明な選択です。
耐え続けることが美徳という考え方は、心と体を壊すリスクを高めます。被害が深刻になる前に離れる判断は、自己を大切にする行動です。逃げた先で、あなたの価値を正しく見てくれる環境があります。 - 威圧的な人の行動をエスカレートさせないために注意すべきことは?
-
相手の“プライド”や“正当感覚”を刺激しない対応がカギです。
否定や反論ではなく、「受け取る」「確認する」姿勢を見せるだけで、攻撃の矛先が逸れる場合があります。具体的には「そういうお考えもあるんですね」「ご指摘の背景を教えてください」と受け止めつつ、巻き込まれない距離感を保つことが重要です。 - 威圧的な態度に慣れてしまい、違和感がなくなってきました。これって危険ですか?
-
はい、“正常化バイアス”が働いている可能性があり、非常に危険です。
暴言や圧力を日常的に受けると、それを「当たり前」と感じる脳の習慣が生まれます。慢性的なストレス状態は、心身に悪影響を与え続けます。自分の感覚をリセットするためにも、信頼できる第三者の意見を聞くことが大切です。 - 威圧的な言動が職場全体に伝播している気がします。これはよくあること?
-
はい、“雰囲気ハラスメント”として知られる現象で、放置すると全体が萎縮します。
強い言動を黙認すると、それが組織の基準になってしまいます。チームリーダーや管理職がそれに気づかず容認していると、若手にも伝染します。職場環境としての“空気”を変える必要があります。 - 威圧的な人は、他人の“弱み”に敏感な気がしますが、それは本当?
-
はい、相手のリアクションや反応を細かく観察して、優位に立とうとする傾向があります。
とくに自信のない人や、断れない人を見抜いてターゲットにしやすいです。逆に、落ち着いた態度や一定の距離感を見せる人には、手出ししにくくなります。堂々と対応することが、予防にもなります。 - 威圧的な人が自分の上司の前では態度を変えるのはなぜ?
-
上位者の前では“評価を気にしている”ため、態度をコントロールしているだけです。
これは“選択的攻撃”と呼ばれるもので、見せたい印象を相手ごとに変えているケースです。外面と内面の差が大きい人物は、自己愛傾向が高いことも多く、根本的な改善は難しいと考えた方が無難です。 - 威圧的な人に筋トレを勧めるのは逆効果ですか?
-
基本的には逆効果です。本人の性格傾向を無視して働きかけると、支配性を強める結果になり得ます。
筋トレは“自分自身を整えるための手段”であって、他人を変える目的で使うべきではありません。筋トレを勧めるなら、あくまで「自分の習慣として続けていることのシェア」という形が好ましいです。 - 威圧的な人に対して謝ってばかりいる自分が嫌です。どうすればいい?
-
“謝って済ませる”のは一時的な安心を得る手段であって、根本的な解決にはなりません。
謝罪を繰り返すと、相手が「自分が正しい」と錯覚し、より攻撃的になります。まずは「申し訳ありません」ではなく「確認いたします」「調整してみます」など、事実ベースの表現に切り替える練習をしましょう。 - 威圧的な言動に反応しないようにするためのセルフケア法はありますか?
-
反応の前に“間”を作る練習が有効です。
深呼吸・短い沈黙・一歩後ろに下がるなど、即反応せず“ワンクッション”置くことで、衝動的な対応を避けられます。加えて、日々の睡眠・運動・朝のルーティンも反応性の低下に役立つとされています。 - 威圧的な人に“言い返せる自分”になりたいけど、怖くてできません…
-
“言い返す”より“言い切る”練習を重ねた方が効果的です。
反論や怒りは逆効果になることが多いため、「私はこのように対応させていただきます」と伝える技術=アサーティブ・スピーキングを身につけましょう。相手に認めさせるのではなく、“自分の意思を宣言する”ことで関係性を変えられます。
その他の質問はこちらから:
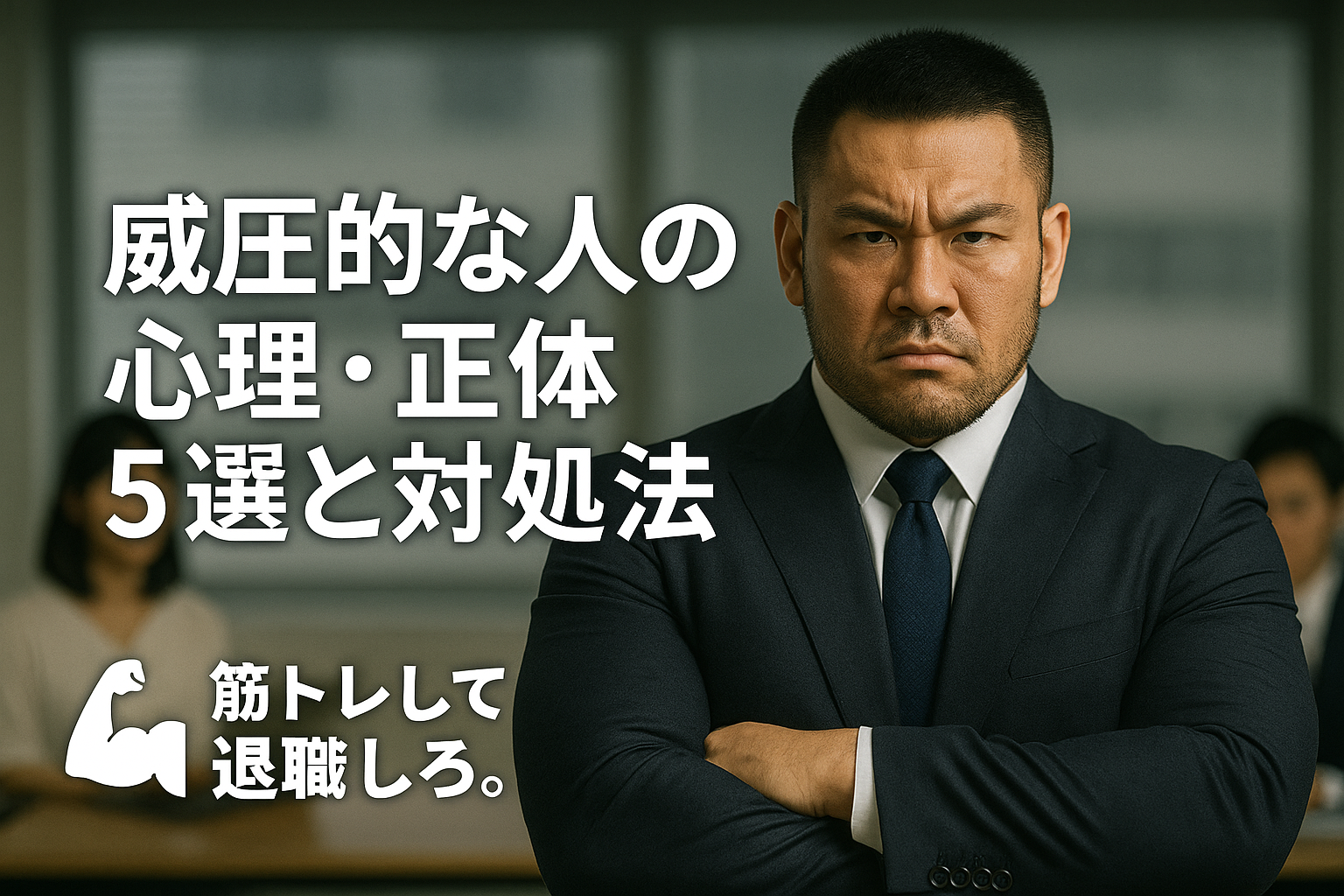



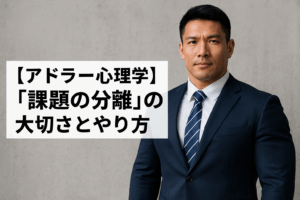
とは?言葉の意味と行う人の心理を徹底解説-300x200.png)

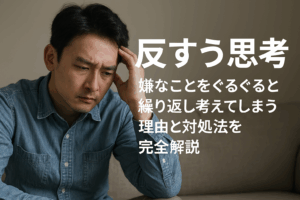


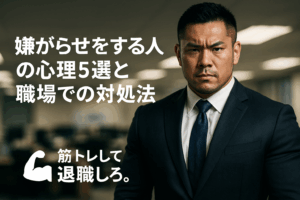
コメント