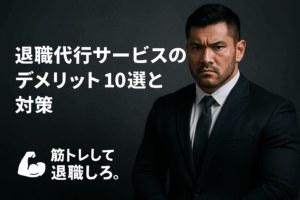この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
 カワサキ
カワサキ『退職代行サービスってそもそも何?』というのをざっくり解説します。
労働者に代わって会社に退職意思を伝えるサービスであり、法律上も有効な手段である。
上司と直接話さず即日退職でき、精神的ストレスを大幅に軽減できる。
費用負担があり、一般業者では有給取得などの交渉ができない場合がある。
退職代行サービスとは何かに興味はありませんか?
いま話題の「退職代行サービス」は、あなたの代わりに退職手続きを進めてくれる心強い味方です。
しかし、サービス内容やメリット・デメリットをよく理解して選ばないと、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクもあります。
この記事では、退職代行サービスの基本から、メリット・デメリット、注意すべきポイントまで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
ブラック企業から確実に脱出し、心身を守るための選択肢を一緒に見ていきましょう。



安心して退職を進めたい方はぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
はじめに:退職代行サービスとは
退職代行サービスは、労働者が会社に退職の意思を伝える際に、本人に代わって第三者がその手続きを行うサービスです。
ブラック企業などでパワハラや過剰労働に苦しんでいる人にとって、直接会社とやり取りをせずに退職できる仕組みとして注目されています。
労働法上、日本の無期雇用労働者(正社員など)は少なくとも2週間前に退職を申し出れば、いつでも辞められると定められていますmhlw.go.jp。
実際、契約ウォッチの解説でも「正社員は2週間前通知で退職可能」であり、法律上の要件(2週間通知など)を満たせば企業は退職を拒否できないとされていますkeiyaku-watch.jpmhlw.go.jp。



つまり、退職意思を伝える方法が規定通りなら、第三者が代理で通知しても違法ではありません。
利用者はまず電話やメールで業者と相談・依頼契約を結び、業者が退職届の提出や会社への連絡を行います。



サービスによっては、依頼当日から出社不要・即日退職が可能です。
退職代行の仕組みと基本の使い方
退職代行サービスの利用手順は一般に次の通りです。
まずウェブサイトや電話で相談し、依頼内容・料金を確認します。
依頼者は業者に必要事項(会社名、部署、退職希望日など)を伝え、サービス利用料(相場で2~3万円程度)を支払います。
担当者が就業規則や労働契約を確認した上で会社に連絡し、退職の意思を伝えてもらいます。
会社にはメールや電話で「○月○日付で退職します」という退職届が送られ、退職手続きに移ります。



依頼者は退職日以降に会社から指示された書類や貸与品を返却するだけでOKです。
退職代行ガーディアンのように労働組合が運営するサービスなら、未払い残業代や有給休暇の取得など退職条件の交渉も依頼できますroudou-pro.com。



労働組合には労働協約締結の交渉権(労働組合法第6条)があり、企業と正式に話し合う法的権限があるためですroudou-pro.comroudou-pro.com。
退職代行利用のメリット
ここでは退職代行利用のメリットについて、下記の内容で触れます。
精神的ストレスの軽減
上司や同僚と直接顔を合わせずに済むため、パワハラや嫌がらせから受ける精神的負担を減らせます。
職場でのいじめ(パワハラ)はうつ病や不安などの精神症状と関連しており、退職意向を高めることが複数の研究で報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



代理人を立てることで自分の代わりに連絡してもらい、安全に環境を変えられます。
即日・確実な退職
正社員は法的に2週間前通知で退職可能mhlw.go.jpなため、スムーズに手続きを進められます。
退職代行業者を介すことで



「会社が拒否するのでは…」



企業側も労働契約法上、合理的な理由がなく一方的に退職させることはできないため、基本的に拒否権はありませんkeiyaku-watch.jp。
手続きの簡便さ
依頼者は退職届の作成や会社への連絡、辞めるタイミングの調整などを業者にまかせられます。
仕事の引き継ぎや退職日までの出勤を休めるケースも多く、最後まで会社に行くストレスが軽減できます。
例えば日本の調査では「週55時間以上」の長時間労働は精神疾患リスクを有意に高めると報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
また、欧州の研究では職場いじめが「退職意向や心理的ストレスに強く結びつく」(β=0.52、p<0.05)ことが示されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



辞めることで過剰なストレス源から離れ、心身の健康回復につなげる効果も期待されます。
退職代行利用のデメリット・注意点
- 費用の負担: サービス利用には数万円の費用がかかります。金銭的な負担を考慮する必要があります。
- 交渉範囲の制限: 一般的な退職代行業者(非弁護士・非組合)は法律的代理権を持たないため、有給休暇消化や未払い賃金の請求など退職条件の交渉はできません。会社との交渉が必要な場合は、労働組合運営や弁護士が対応するサービスを選ぶとよいでしょう。
- 公務員・公務関連職では利用不可: 公務員など国家・自治体職員は、身分上の規則が異なるため退職代行サービスの利用対象外です。また、訴訟を前提とするケース(未払い賃金の裁判など)は、直接弁護士に相談した方が安全です。
- 企業側とのトラブル: 退職通知自体は有効ですが、会社が手続きを怠る場合は最後の給与や退職金の受け取りに時間がかかることがあります。不払いや違法労働の問題があれば、別途労働局や弁護士へ相談してください。
比較:退職手段別メリット・デメリット
下表は「自分で退職」「一般的な退職代行」「労組・弁護士対応型退職代行」の特徴を比較したものです。



自分の状況に合った方法を選びましょう。
退職方法の比較
| 退職方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 本人が直接退職 | ・費用がかからない ・会社ルールに沿った手続き | ・上司との対面が必要 ・辞めるまで精神的負担が大きい |
| 一般の退職代行サービス | ・上司と直接やり取り不要 ・即日退職可能 | ・依頼費用が必要 ・交渉はできない(通知のみ) |
| 労組・弁護士運営型退職代行 | ・有給取得・未払請求など交渉可能roudou-pro.com ・法的サポートが充実 | ・一般より費用が高額 ・手続きがやや複雑になる場合あり |
表をまとめると、単に早く辞めたいだけなら一般業者でも十分ですが、給与や退職条件まで調整したいときは労働組合や弁護士対応のサービスがおすすめです。
法的視点からの留意点
ここでは法的視点からの留意点について、下記の内容で触れます。
退職通知の法的効力
日本では労働契約法に基づき、正社員は2週間前通知で退職可能ですmhlw.go.jp。
退職代行はこの通知行為の代替なので、法律上は有効な退職届けとなりますmhlw.go.jpkeiyaku-watch.jp。



企業は就業規則に規定があっても通知権利を奪うことはできませんkeiyaku-watch.jp。
パワハラ対策
2019年の法改正により、企業にはパワーハラスメント防止の義務が課されましたloc.gov。
厚生労働省の調査では、職場でパワハラを受けた経験者が3割超に上りloc.gov、企業は相談窓口設置などの対応が求められていますloc.gov。
もしパワハラで退職を余儀なくされた場合、企業に安全配慮義務違反を問うことも可能です。



まずは労働局やハラスメント相談窓口、法テラスなどに相談しましょう。
違法労働への対応
長時間労働や未払い残業は労働基準法違反です。
例えば週60時間以上の労働はメンタル不調のリスクを大幅に高めると指摘されておりpmc.ncbi.nlm.nih.gov、法定外労働には割増賃金の支払いが義務づけられています。



会社が違法な労働条件を強いる場合、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーで解決の助けを求めてください。
公的機関や専門家の利用
退職に限らず労働トラブル全般については、法テラス(日本司法支援センター)や弁護士、労働組合が相談窓口を設けています。



特に未払賃金や残業代請求、解雇問題などは専門家のサポートを受けた方が安心です。
まとめ



いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
退職代行サービスはあくまで「退職意思の伝達手段」です。
ブラック企業を逃れる有効な方法の一つですが、会社とのやり取りがなくなると同時に自身で権利を守る意識も必要です。
心身の安全を最優先に考えつつ、公的支援や専門家の助けも積極的に活用しましょう。



今回の記事は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 退職代行サービスは本当に使っても違法になりませんか?
-
退職代行サービスを利用しても、原則違法にはなりません。
退職の意思を第三者が伝えること自体は民法上認められており、労働契約法でも正社員は2週間前の通知で自由に退職できると定められています。弁護士資格がない業者が「交渉」を行った場合には非弁行為となるリスクがありますが、単なる退職の意思伝達にとどまる限り、利用者側が罰せられることはありません。 - 即日退職は本当に可能なのですか?
-
即日で会社に行かずに退職手続きを進めることは可能です。
ただし、法律上は「即日退職できる」わけではなく、正確には「退職の意思を伝えた日から2週間後に退職が成立する」というルールが適用されます。会社との合意が取れれば即日退職も可能ですが、給与支払い日や書類手続きなどには少し時間がかかる場合もあります。 - 退職代行を使ったことが会社にバレて不利益を受けたりしませんか?
-
基本的に、退職後に不利益を受ける心配はほとんどありません。
退職代行を使ったかどうかはプライバシーに属する情報であり、外部に漏らすことは違法となる可能性があります。また、退職後の新たな就職先に「前職の辞め方」が伝わることも通常ありません。ただし、ごく一部の業界では内部情報が共有される例もあるため、心配な場合は個別相談をおすすめします。 - 退職代行を使ったら離職票や源泉徴収票はきちんともらえますか?
-
通常は退職後に必要な書類も問題なく送付されます。
離職票や源泉徴収票は労働基準法上、会社に交付義務があります。退職代行サービスを通じて「書類の送付依頼」まで伝えてもらえるケースが多く、安心して受け取れます。ただし、会社側が書類発行を渋った場合には、労働基準監督署に相談することで解決できます。 - 退職代行を使うと未払い残業代や有給休暇の取得もできるのですか?
-
一般の退職代行業者では交渉できませんが、労働組合や弁護士に依頼すれば可能です。
非弁護士の業者は法的交渉を行えないため、有給取得や未払い賃金の請求交渉はできません。これらを確実に求めたい場合は、労働組合が運営する退職代行サービスや、弁護士による退職代行を選ぶ必要があります。 - ブラック企業でも退職代行は通用しますか?
-
ブラック企業であっても、法的には退職の自由が守られています。
パワハラや違法労働を行う会社でも、労働者には退職する権利があります。会社が「辞めさせない」と主張しても、それは法律違反となります。万一、嫌がらせや引き留めがあった場合でも、退職代行業者や弁護士を通じて対処が可能です。 - 退職代行サービスに支払う料金の相場はどのくらいですか?
-
一般的な相場は2万円〜3万円程度です。
労働組合運営型や弁護士対応型の場合は、4万円〜5万円程度に上がることもあります。価格だけで選ばず、サポート範囲(交渉可能か、即日対応かなど)をしっかり確認して、自分に合ったサービスを選びましょう。 - 自分で退職届を提出するのと退職代行を使うのは何が違いますか?
-
最大の違いは、精神的負担を代行できるかどうかです。
自分で退職届を提出する場合、どうしても上司とのやり取りや説得が必要になります。退職代行を使えば、そうしたやり取りを完全に回避できるため、精神的ストレスを大きく減らすことができます。特にブラック企業の場合、この違いは非常に大きいです。 - 退職代行を使った後、会社から連絡が来たらどうすればいいですか?
-
基本的には無視して構いません。
退職意思を伝えた時点で、労働契約の終了は進行中です。会社から連絡が来ても、個別に応対する義務はありません。心配な場合は、退職代行業者に「連絡が来た」と報告し、指示を仰ぐと安心です。なお、書類の受け取りや貸与品返却のみは忘れずに対応しましょう。 - 退職代行サービスを使って辞めた後、転職に不利になることはありますか?
-
通常、転職活動に直接影響することはありません。
履歴書や面接で「どうやって前職を辞めたか」を細かく聞かれるケースは稀です。仮に質問された場合でも、「やむを得ない事情があった」と簡潔に答えれば問題ありません。むしろ、無理に我慢して心身を壊すより、早期にリスタートを切るほうが長期的にはプラスです。 - 退職代行を使った場合、上司や同僚に悪口を言われたりしないか不安です。
-
一部の悪意ある人から陰口を叩かれる可能性はゼロではありませんが、気にする必要はありません。
退職代行を使うかどうかは個人の自由であり、悪口を言う側のモラルの問題です。あなたが違法行為をしたわけではなく、正当に権利を行使しただけなので、自信を持って大丈夫です。何より、ブラックな環境に残るより、自分を守る選択をしたことが正解です。 - 家族に退職代行を使ったことを知られると怒られるかもと心配です。
-
事前に相談するか、退職後に冷静に説明すれば問題ありません。
家族の世代によっては「自分で言うべき」と考える人もいますが、現代はメンタルヘルス重視の時代です。パワハラやブラック労働から身を守るために必要な選択だったと、冷静に伝えれば理解してもらえる可能性は高いです。無理に隠す必要もありません。 - アルバイトやパートでも退職代行サービスは使えますか?
-
アルバイトやパートでも退職代行サービスは利用可能です。
雇用形態にかかわらず、「退職する自由」は労働者に保障されています。特に、シフト制アルバイトであっても、契約内容によっては2週間前通知での退職が成立します。正社員でないからといって、退職代行が使えないということはありません。 - 退職代行を使ったあとに会社が連絡を無視してきたらどうなりますか?
-
連絡が取れなくても、退職の意思表示が届いていれば問題ありません。
法律上は「退職の通知が会社に到達した時点」で効果が発生します。会社が連絡を返してこなくても、2週間経過すれば退職は成立します。給与や離職票が届かない場合には、労働基準監督署や労働局に相談することをおすすめします。 - 有給休暇を全部消化してから辞めたい場合、退職代行で対応できますか?
-
労働組合型または弁護士型の退職代行なら、有給休暇の取得交渉も可能です。
通常の民間業者では交渉権がないため、対応できない場合があります。すべての有給を消化してから辞めたい場合は、労働組合が運営する退職代行サービスを選ぶと安心です。法的には、退職時に有給休暇の取得を申し出る権利は労働者にあります。 - 退職代行を使ったあと、会社に貸与物をどうやって返すのですか?
-
退職代行業者から指示される方法に従い、郵送などで返却すれば問題ありません。
制服、PC、社員証など貸与物は、速やかに会社へ返送する必要があります。通常は、業者が返却方法や宛先を指示してくれるため、その通りに郵送すればトラブルにはなりません。送付時には「追跡可能な宅配便」を使うのが安全です。 - 退職代行サービスにはどんなトラブル事例がありますか?
-
まれに、追加料金の請求トラブルや、退職完了の連絡ミスが発生することがあります。
信頼できる業者を選べば基本的に大丈夫ですが、契約前に「料金の総額」「対応範囲」を必ず確認しましょう。また、契約書ややり取りの履歴は保存しておき、万が一トラブルが発生した場合に備えておくと安心です。 - 退職代行を使っただけで訴えられることはありますか?
-
正当な退職の範囲であれば、訴えられるリスクは極めて低いです。
労働者には自由に退職する権利があり、これを行使しただけで会社から訴えられることは基本的にありません。ただし、会社に重大な損害を与えた場合(例:機密情報漏洩など)は別問題になるため、通常の退職手続き以外の行動には注意しましょう。 - 退職代行サービス選びで一番重視すべきポイントは何ですか?
-
「交渉できるかどうか」と「サポートの手厚さ」が最重要です。
料金だけで選ぶのは危険です。自分が求めるサポート(即日退職、有給交渉、未払い賃金請求など)が含まれているか、契約前にしっかり確認しましょう。また、運営主体が労働組合や弁護士であるかどうかも、信頼性の大きな指標になります。 - 退職代行を使ったら次の職場で不信感を持たれることはありませんか?
-
基本的に転職先に伝わることはありませんし、持たれることもほとんどありません。
退職代行を使った事実は、前職の会社が外部に漏らす義務も理由もありません。面接時にどう辞めたか聞かれた場合でも、「体調不良」「労働環境の問題」など一般的な理由を伝えれば十分です。重要なのは、次の職場で前向きに働く意欲を見せることです。 - 退職代行を使ったあと、健康保険や年金の手続きはどうすればいいですか?
-
退職後は自分で健康保険と年金の切り替え手続きが必要です。
会社を辞めると社会保険(健康保険・厚生年金)は自動的に喪失します。転職予定がない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。住んでいる市区町村役場で手続きできるので、なるべく速やかに対応しましょう。 - 退職代行に頼んだ後に自分から会社に連絡しても問題ないですか?
-
基本的には、退職代行業者に任せきりにした方がスムーズです。
自分から会社に連絡を入れると、意図せず交渉になってしまったり、業者との連携が乱れる可能性があります。業者がすべての窓口になる前提で動いているため、心配なことがあればまず業者に相談しましょう。 - 離職理由を「自己都合退職」と「会社都合退職」どちらにするか選べますか?
-
基本は「自己都合退職」ですが、特定の条件を満たせば「会社都合退職」も可能です。
例えば、パワハラや長時間労働が原因でやむを得ず退職する場合、条件次第で会社都合扱いが認められるケースもあります。失業保険の給付条件に直結するため、希望がある場合は労働組合型退職代行や弁護士に相談するのがベストです。 - 退職代行を使った場合でも、自己都合退職なら失業保険をすぐにもらえますか?
-
通常、自己都合退職だと失業保険の給付は「3か月の給付制限」があります。
ただし、ブラック企業での勤務実態(パワハラ、長時間労働など)が証明できる場合、ハローワークに申し立てることで給付制限が免除される可能性もあります。証拠(メール、LINE、録音など)があれば提出できるよう準備しておきましょう。 - 退職代行を使ったら懲戒解雇されるリスクはありませんか?
-
通常の退職手続きであれば、懲戒解雇されるリスクはありません。
懲戒解雇は重大な規律違反(横領、暴行、機密漏洩など)があった場合に限られます。退職代行を使って辞めるだけでは懲戒解雇理由にならず、労働法違反にもあたります。安心して手続きを進めましょう。 - 未成年でも退職代行を使えますか?
-
未成年でも退職代行サービスを利用することは可能です。
ただし、契約時に親権者の同意が必要になる場合があります。特に18歳未満の場合は、業者から親権者確認を求められるケースがほとんどです。事前に家族と話し合っておくとスムーズです。 - 退職代行を使った後にアルバイト先から損害賠償を請求されることはありますか?
-
通常の範囲であれば損害賠償を請求されることはありません。
正当な退職は法律で守られており、バイト先で急に辞めても、よほど故意に損害(重要なデータ破壊など)を与えない限り賠償責任は発生しません。仮に請求された場合でも、支払う義務がない場合がほとんどです。 - 退職代行サービスの選び方で、ホームページ以外にチェックすべきポイントは?
-
口コミの質と、問い合わせ時の対応スピード・丁寧さを必ず確認しましょう。
公式サイトだけではわからない「実際の対応力」は、問い合わせ時に見えてきます。返信が遅い、質問に曖昧な回答しかない場合は要注意です。第三者評価サイト(公的なもの)での評判も参考にすると安心です。 - 弁護士が対応する退職代行と、労働組合が運営する退職代行はどう違いますか?
-
弁護士は法的代理権を持ち、裁判も視野に入れた対応が可能です。
一方で、労働組合は交渉権を持つものの、あくまで労使交渉に限定されます。費用面では労働組合型がややリーズナブルな傾向がありますが、トラブルが深刻化している場合には弁護士型を選ぶ方が安全です。 - 退職代行を使って辞めたあとは、どういう心構えで転職活動をすればいいですか?
-
「辞めた自分を責めない」ことが最優先です。
ブラック企業に耐えた経験はむしろ貴重な財産です。次の職場では、労働条件や企業文化をよく見極める意識を持ちましょう。また、過去に縛られず「これから何をしたいか」を前向きに語れるよう、自己分析を進めておくと転職活動でも強みになります。 - 退職代行サービスは地方に住んでいても利用できますか?
-
全国どこからでも退職代行サービスは利用できます。
基本的に電話やメール、LINEなどのオンライン完結で手続きできるため、地方在住でも問題ありません。地域による料金差もほとんどないので、安心して依頼できます。 - 退職代行を使うとき、会社に引き止められたらどうなりますか?
-
退職の意思を代行業者が伝えた時点で、会社の引き止めは無効です。
日本の法律では「退職の自由」が保障されているため、会社側に引き止める法的権利はありません。引き止められても、退職代行業者が適切に対応してくれます。 - 契約社員でも退職代行を利用できますか?
-
契約社員でも退職代行サービスは問題なく利用できます。
ただし、契約期間の途中で辞める場合は、就業規則や労働契約書に記載された条件を確認する必要があります。違約金規定などがある場合は、事前に専門家に相談しましょう。 - 退職代行で辞めた場合、最後の給料はきちんと振り込まれますか?
-
原則として、退職代行利用にかかわらず給料は支払われます。
労働基準法第24条により、労働の対価は必ず支払わなければならないと定められています。もし未払いが発生した場合は、労働基準監督署へ申告することで対処できます。 - 退職代行の相談だけして、実際には使わないのもありですか?
-
相談だけして利用を見送ることも、もちろん可能です。
ほとんどの退職代行業者は無料相談を受け付けています。実際に依頼するかどうかは、相談後に決められます。無理に契約を迫る業者は避けたほうがよいでしょう。 - 退職代行サービスを利用しても会社から訴えられるリスクゼロとは言い切れない?
-
理論上ゼロではありませんが、通常のケースではまずありません。
会社が損害賠償請求を起こすには、労働者側に重大な背信行為があった場合に限られます。単なる退職代行の利用を理由に訴訟されることは、現実には非常に稀です。 - 退職代行を使ったことを履歴書に書く必要はありますか?
-
退職代行を利用した事実を履歴書に書く義務は一切ありません。
履歴書に記載すべきなのは、勤務期間や職務内容のみです。退職の経緯(自己都合、会社都合)は面接で口頭説明すれば十分であり、代行サービス利用の記載は不要です。 - 退職代行を使った後でも、失業保険の手続きに支障はありませんか?
-
退職代行利用後でも、通常通り失業保険の申請は可能です。
離職票がきちんと届き、ハローワークで手続きを行えば問題ありません。申請時に退職理由について説明を求められることがありますが、一般的な退職理由を伝えれば問題なく進みます。 - 「出勤停止命令」を出されたら退職代行は使えないのですか?
-
出勤停止中であっても退職代行の利用は可能です。
むしろ、出勤停止が発令されるような異常な環境なら、早めの退職決断が望ましいケースもあります。会社との連絡を代行してもらうことで、さらに安全に環境から抜け出せます。 - 退職代行を使っても会社から嫌がらせ(誹謗中傷)されたらどうすればいいですか?
-
誹謗中傷を受けた場合は、記録を残して労働局や弁護士に相談しましょう。
違法な名誉毀損や業務妨害にあたる可能性があります。証拠(メール、SNS投稿、録音など)を確保し、必要なら民事訴訟も検討できます。泣き寝入りせず、冷静に対処しましょう。 - 退職代行の料金支払いは現金以外にも対応していますか?
-
多くの退職代行サービスはクレジットカード払いや銀行振込に対応しています。
中にはコンビニ払い、ペイペイなど電子決済に対応している業者もあります。即日対応を希望する場合は、迅速に支払いが完了する方法を選ぶとスムーズです。事前に支払い手段を確認しておきましょう。 - 退職代行を使った場合、社会保険の資格喪失日はいつになりますか?
-
基本的には退職日が社会保険の資格喪失日になります。
退職届に記載された退職日をもって、健康保険や厚生年金の資格も終了します。なお、健康保険証は退職後に速やかに返却する義務があるので注意してください。 - 退職代行利用中に会社から「直接話したい」と連絡がきたらどうすればいい?
-
原則として無視して問題ありません。
退職代行業者に全ての連絡を任せている旨を伝えているため、本人が出る必要はありません。不安な場合は、業者にその旨を報告し、適切に対応してもらいましょう。 - 退職代行を使ったら会社の備品弁償を請求されることはありますか?
-
通常の使用範囲内であれば、弁償を求められることはありません。
貸与品(PC、制服など)を通常使用していた場合は、基本的に返却すれば問題ありません。故意や重大な過失による破損がない限り、賠償責任は問われませんので安心してください。 - 退職代行の相談は何日前からすればいいですか?
-
早ければ早いほどスムーズに進められますが、即日依頼も可能です。
理想は退職希望日の1〜2週間前に相談開始することですが、ブラック企業の場合は「もう限界」というタイミングでも対応してもらえます。まずは気軽に相談することが大切です。 - 退職代行サービスは深夜や早朝でも対応してくれますか?
-
24時間対応の退職代行サービスも増えています。
特にブラック企業勤務の場合、相談できる時間帯が限られることもあります。深夜や早朝でもLINEやチャットで受け付けてくれる業者を選ぶと、安心して依頼できます。 - 退職代行を使うとき、家族にバレずに進めることはできますか?
-
基本的に可能ですが、緊急連絡先に家族が設定されている場合は注意が必要です。
会社によっては、本人に連絡が取れない場合、緊急連絡先に電話することもあります。あらかじめ業者に相談し、対応方法を決めておきましょう。 - 退職代行を使った後、転職エージェントを利用しても問題ないですか?
-
もちろん問題ありません。
転職エージェントは前職の退職方法まで細かく詮索することはありません。むしろ、退職理由を前向きに整理してくれるプロも多いので、積極的にサポートを受けましょう。 - 退職代行を使ったことで将来の信用に影響することはありますか?
-
通常の社会生活に影響することはありません。
退職代行を使った過去がクレジット審査や社会的信用に影響することは一切ありません。自分の心身を守るために正当な方法を選んだだけなので、気にする必要はありません。 - 退職代行サービスを選ぶとき「実績あり」と書かれているのは信用していい?
-
実績の記載は参考になりますが、必ず詳細を確認しましょう。
「実績多数」と書かれていても、具体的な成功事例や対応件数が開示されていない場合は注意が必要です。口コミ評価や運営歴、顧客サポート体制なども総合的にチェックすることが大切です。
その他の質問はこちらから: