この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「なんでいつも、他人の言動に振り回されてしまうんだろう…」
「気分が落ちたとき、どう立て直せばいいかわからない」
「嫌なことがあると、ずっと引きずってしまう」
 カワサキ
カワサキ個人的には、自分で自分の機嫌を取れるのが『成熟している人』の条件の一つ。
わたしも修行中。一緒に頑張りましょう。
自分の感情に気づき、冷静に対処できる力がある人ほど機嫌を自分で整えられる。
物事のとらえ方を切り替える思考習慣が、ストレスを受け流す力につながる。
運動・睡眠・食事などの基本が整っている人ほど、気分も安定しやすい。
自分の機嫌を自分で取れるようになりたいと思いませんか?
ちょっとした一言に傷ついたり、思い通りにいかないことでイライラしたり…。
でも、自分の気分をうまくコントロールできる人たちは、決して特別な存在ではありません。
心理学の研究によって、その人たちに共通する「考え方」や「行動パターン」が明らかになってきています。
この記事では、
- 自分で機嫌を整えられる人の5つの特徴
- 感情の波に飲まれずに生きやすくなるヒント
- ブラック企業やストレスフルな職場でも自分を守る実践法
を、科学的な根拠に基づいてわかりやすく解説していきます。



人間関係や仕事に振り回されず、自分のペースで気持ちを整えたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
はじめに
「自分で自分の機嫌を取る」ことは、過酷な職場環境でも心を安定させるために重要です。
研究によれば、感情を適切に調整できる人ほど生活満足度が高く、不安や抑うつなどの否定的感情が低いことが示されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
職場でのストレスが強いほど、機嫌が他人に左右されるとダメージも大きくなりますが、自分の内部で心のバランスを取る力があれば、どんな状況でも前向きに行動しやすくなります。



次項から、自分で自分の機嫌が取れる人の特徴5選について解説していきます。
自分で自分の機嫌が取れる人の特徴 5選
ここでは自分で自分の機嫌が取れる人の特徴 5選について、下記の内容で触れます。
① 自己認識(メタ認知)が高い
自分自身の感情や思考を客観的に観察する力が高い人は、機嫌の乱れに早く気づけます。



自分が今どんな気持ちか、何が原因で機嫌が悪いのかを冷静に分析できるため、対処しやすいのです。
たとえば自己認識(メタ認知)の高い人は、イライラの原因となっている考え方のクセに気づき、意識して手放すことができます。
心理学的には、認知的再評価(状況の捉え直し)がうまくできる人ほど、生活満足度が高く、抑うつや不安などの否定的な指標が低いことがメタ分析で示されていますpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



具体的には「この失敗は自分を成長させるチャンス」と捉えるような前向きな再評価によって、感情の高ぶりが抑えられるのですjstage.jst.go.jp。
セルフモニタリング習慣
自己認識を高めるために、自分の感情を書き出したり、瞑想や深呼吸で自分の心身の状態に意識を向ける人も多いでしょう。
こうした習慣は、不快な感情を「漠然と抱える」のではなく「現在抱いている感情とその原因」を明確にします。



実際、認知的再評価は他の感情制御法よりネガティブ感情を低減する効果が高く、心身の健康増進にも寄与することが知られていますjstage.jst.go.jp。
② セルフ・コンパッション(自己肯定感)がある
自分に優しい態度を持つ人は、機嫌が悪いときにも自分を責めず、落ち込んだ自分を受け入れることができます。



この「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」が高い人ほど、精神的ストレスが低いことが多数の研究で報告されています。
日本の研究でも、セルフ・コンパッションが高い人ほど不安や抑うつが低く、主観的幸福感が高い相関が確認されていますjstage.jst.go.jp。
また、イギリスのメタ分析(10~19歳の青少年7,049名を対象)では、セルフ・コンパッションの高さが不安・抑うつ・ストレスなどの心理的苦痛の低さと強い負の相関(r=-0.55)を示しましたlink.springer.com。



これは「自分に優しい人ほど精神的に強い」ことを示す結果であり、セルフ・コンパッションは自分の機嫌を自己管理する上で不可欠な要素です。
否定的自己判断を手放す
セルフ・コンパッションを高めるには、自分を責める代わりに「誰でも同じようにつらい」「今は弱っている自分を大切にしよう」と考える癖をつけます。



研究者も「セルフ・コンパッションを高める介入は抑うつや不安の軽減に効果がある」と指摘しておりpmc.ncbi.nlm.nih.gov、実際に自己批判を減らし自分に優しく接する習慣が、精神的な安定感をもたらすのです。
③ 前向きな思考習慣ができる
物事の良い面を見つけられる認知の柔軟性も、自分で機嫌を取る人の特徴です。



困難な経験にも「これが将来の自分の成長につながる」と捉え直せば、ネガティブ感情が薄れやすくなります。
このようなポジティブな再評価を行う人は、感情的な落ち込みから素早く回復しやすいことがわかっています。



実際、先述のメタ分析pubmed.ncbi.nlm.nih.govでも、認知的再評価は精神的幸福度を高める指標と相関し、ネガティブ指標とは負の相関が認められました。
- 比較対照:感情を抑圧して我慢する代わりに、再評価で気持ちを切り替える。この方法では抑圧したときよりもストレス反応が小さいことが示されています(感情抑制は不安増加と関連するのに対し、再評価は不安低下と関連)pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
再評価のコツ
- 苦しい状況に対し「あとで笑い話になるかも」「これを経験できる自分は成長している」といった前向きな視点を意識的に持つ。
- 状況を大局で見て「いまはつらくても、時間が経てば落ち着く」と自分に言い聞かせる。



多くの研究が示すように、こうした認知戦略は心の負担を大きく減らしますjstage.jst.go.jppubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
④ レジリエンス(ストレス耐性)が高い
レジリエンスとは、失敗や困難から立ち直る力のこと。



レジリエントな人は、誰でも挫折経験があることを理解し、自分を責めすぎずに前進できます。
2023年の統計レビューでは、レジリエンスの高さは精神的ストレスの低さと明確に関連していると報告されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
具体的には、COVID-19患者を対象としたメタ分析で「レジリエンスが高いほど不安・抑うつが低い」という結果が得られ、一般労働者でも同様にレジリエンスと低いバーンアウト・不安・抑うつが関係することが確認されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



これらは、レジリエンスの高い人ほどストレス反応が弱く、早く正常状態に戻れることを示しています。
自己効力感の高さ
レジリエンスが高い人は「自分ならできる」という自己効力感(セルフエフィカシー)も高い傾向があります。
自己効力感が高いほど、困難に直面したときにも「小さな成功体験」を積み重ねられるため、結果的にストレス耐性が強まります。



心理学研究でも、自己効力感が高い人ほどストレス時の対処がうまく、精神的健康状態が良好であることが報告されていますjstage.jst.go.jppmc.ncbi.nlm.nih.gov。
⑤ 健康的な生活習慣(運動・休息)がある
規則的に体を動かしたり良質な睡眠を取る人は、自律神経のバランスが整い、感情も安定しやすいです。
2024年のメタ分析によると、運動トレーニングは心拍変動(HRV)など自律神経指標を改善し、特に副交感神経活動を高めることが示されましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。



副交感神経が優位になるとリラックスしやすくなり、ストレス耐性が上がります。
また2018年のメタ分析(33件のRCT、計1877人)では、レジスタンストレーニング(筋力トレーニング)が中等度の効果量(0.66)で抑うつ症状を軽減すると報告されましたpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
睡眠の質も見逃せません。
2021年の大規模メタ分析(RCT65件、計8608人)では、睡眠の質を改善する介入が抑うつや不安、ストレスを中程度以上に軽減することが示されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
具体的な習慣例
- 短時間の運動を習慣化:ウォーキングや筋トレなどを定期的に行う。職場でもエレベーターではなく階段を使うなど小さな運動でも効果がありますkenkou-souken.co.jppubmed.ncbi.nlm.nih.gov。
- 睡眠時間の確保:毎晩同じ時間に寝起きし、就寝前はスマホを控えるなど睡眠環境を整える。睡眠の質向上が精神的ストレスを大きく下げることが示されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
まとめ:あなたもできる!
自分で自分の機嫌を取る力は、特別な才能ではありません。
高い自己認識やポジティブ再評価、セルフ・コンパッション、レジリエンス、健康習慣といった要素は、どれも練習や訓練で少しずつ高められます。



研究でも、これらの能力は学習で伸びるとされていますjstage.jst.go.jppmc.ncbi.nlm.nih.gov。
まずは小さな成功体験――たとえば軽い筋トレでリフレッシュしたり、夜しっかり眠ることで次の日の気分が変わることを実感する――ことから始めてみましょう。
そうした積み重ねによって、やがて「自分の機嫌を自分で取れる人」に近づけるはずです。



今回の記事は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。 それでは。
よくある質問
- 自分の機嫌を取るって、具体的にどういうことですか?
-
自分の機嫌を取るとは、感情の波に流されず、自分で気分を整える力を指します。例えば、イライラや落ち込みを感じたときに、その感情を認識し、適切な方法でリセットできる状態です。これは、感情の自己調整能力とも言われ、心理学では「情動調整」として研究されています。この能力を高めることで、ストレスの多い環境でも冷静に対応できるようになります。
- セルフ・コンパッションって何ですか?自己肯定感とは違うの?
-
セルフ・コンパッションは、自分に対する思いやりや優しさを持つことを指します。自己肯定感が「自分には価値がある」と感じることに対し、セルフ・コンパッションは「失敗や困難に直面したときでも、自分を責めずに受け入れる」姿勢です。研究によれば、セルフ・コンパッションを高めることで、ストレス耐性や幸福感が向上することが示されています。
- 感情の浮き沈みが激しいのは性格のせいですか?
-
感情の波が大きいことは、性格だけでなく、環境や生活習慣、ストレスの影響も関係しています。例えば、睡眠不足や過度なストレスは感情の安定を妨げます。また、感情を適切に認識し、対処するスキルを学ぶことで、感情のコントロールがしやすくなることが研究で示されています。
- ストレス耐性を高めるにはどうすればいいですか?
-
ストレス耐性を高めるためには、以下のような方法が有効です:
- 筋トレはメンタルにどんな影響がありますか?
-
筋トレは、メンタルヘルスに多くの良い影響を与えることが研究で示されています。例えば、定期的な筋力トレーニングは、うつ症状の軽減や不安の緩和、自己効力感の向上に寄与します。また、筋トレによって分泌されるエンドルフィンやセロトニンなどの神経伝達物質が、気分の安定に関与しています。
- 自分の感情に気づくにはどうすればいいですか?
-
自分の感情に気づくためには、以下のような方法が有効です:
これらの方法を継続することで、感情の認識力が高まり、適切な対処がしやすくなります。
- 他人の言動に振り回されない方法はありますか?
-
他人の言動に影響されすぎないためには、以下のポイントが重要です:
- 境界線の設定:自分と他人の感情や責任を区別する。
- 価値観の明確化:自分の大切にしたいことを理解し、それに基づいて行動する。
- 反応の選択:即座に反応せず、一呼吸おいてから対応する。
これらのスキルは、自己理解を深めることで養われます。
- セルフ・コンパッションを高める具体的な方法は?
-
セルフ・コンパッションを高めるためには、以下のような実践が効果的です:
- 慈悲の瞑想:自分や他人に対する思いやりの気持ちを育む瞑想。
- 自分への手紙:困難な状況にある自分に対して、励ましの手紙を書く。
- ポジティブな自己対話:失敗や困難に直面したとき、自分を責めずに励ます言葉をかける。
これらの方法を継続することで、自己への思いやりが深まり、メンタルの安定につながります。
- 感情のコントロールが難しいと感じたときの対処法は?
-
感情のコントロールが難しいと感じたときは、以下のステップを試してみてください:
- 感情を認識する:「今、怒っている」「悲しい」と自分の感情を言葉にする。
- 呼吸を整える:深呼吸を数回行い、心を落ち着ける。
- 視点を変える:状況を客観的に見直し、別の解釈を試みる。
- 行動を選択する:感情に任せた行動ではなく、冷静な対応を選ぶ。
これらのステップを習慣化することで、感情のコントロールがしやすくなります。
- 自分の機嫌を取る力は、仕事や人間関係にどう影響しますか?
-
自分の機嫌を取る力があると、以下のようなポジティブな影響があります:
- 仕事のパフォーマンス向上:ストレスに強くなり、集中力や生産性が高まる。
- 人間関係の改善:感情的な反応が減り、円滑なコミュニケーションが可能になる。
- 自己成長の促進:困難を乗り越える力がつき、自己効力感が高まる。
これらの効果により、職場やプライベートでの満足度が向上し、より充実した生活を送ることができます。
- 「前向きに考えよう」と言われても、どうしても無理なときはどうすればいい?
-
無理に前向きになろうとすると、かえって自分を責めてしまうことがあります。その場合は、「前向きさ」よりも「自分の感情を認めること」が優先です。「今つらいんだな」と一旦受け止めるだけでも、心は落ち着きやすくなります。無理をしないことが、感情の回復にはとても大切です。
- 一度気分が沈むと、なかなか立ち直れません。改善する方法はありますか?
-
気分の切り替えが苦手な人は、視覚・身体・行動を使った“強制的リセット”が効果的です。たとえば、部屋の換気をする・外に出る・筋トレや軽い運動をする・別の作業に手をつけるなど、身体を動かすことが気分の転換につながります。小さな行動で十分なので、まずは1つ試してみましょう。
- そもそも「自分の機嫌を取る力」は、生まれつき決まっているものではないのですか?
-
いいえ、生まれつきの性格だけで決まるものではありません。心理学の研究でも、感情の調整能力やレジリエンス、セルフ・コンパッションなどは後天的に伸ばすことができるとされています。習慣や思考のトレーニング次第で、誰でも少しずつ身につけられる力です。
- 職場で常に気を張っていて、帰宅後に感情が爆発してしまいます。これは異常ですか?
-
異常ではありません。これは「感情の抑圧」が一時的に限界を超えて爆発する、いわゆる“リバウンド現象”です。日中に感情を我慢しすぎると、夜に反動がきやすくなります。休憩中に少しでも深呼吸やストレッチを入れたり、夜は感情を「出してもいい時間」と割り切るのも効果的です。
- 認知の歪みってよく聞きますが、それがあると機嫌を取れなくなるんですか?
-
はい、認知の歪み(思考のクセ)があると、現実以上に自分を追い詰めたり、悪く解釈してしまうため、感情の安定が難しくなります。たとえば「どうせ自分なんて…」という全否定的思考がそれにあたります。認知行動療法ではこの歪みを修正することで感情の安定を目指します。
- 自己効力感ってなんですか?メンタルにどんな影響があるの?
-
自己効力感とは、「自分にはやり遂げる力がある」と信じる感覚のことです。これが高いと、困難にも前向きに取り組みやすく、落ち込んだときの回復力(レジリエンス)も高くなります。小さな成功体験を積み重ねることで、誰でも少しずつ高めることができます。
- 他人と比べて落ち込んでしまうときは、どう気持ちを切り替えたらいいですか?
-
比較は人間の本能でもありますが、「比較の対象を自分の過去」に切り替えるのが有効です。「一年前の自分よりどうか」「昨日より少しマシか」など、比較の軸を変えるだけで心が軽くなります。他人と比べて自分を下げるのではなく、前に進んでいる自分を認めましょう。
- 感情を表に出すことが苦手でも、自分で機嫌を取れるようになりますか?
-
はい、感情を外に出すのが苦手な人でも、内面で整理できれば問題ありません。言葉にできないときは、紙に書く・声に出さずに考える・身体を使って発散する(筋トレやストレッチ)など、自分なりのアウトプット方法を見つけることがカギになります。内向的でも自己調整は可能です。
- 自分で機嫌を取ろうとしても、結局他人に左右されてしまいます。どうしたら?
-
まず、「完全に他人の影響を受けない」ことは不可能だと理解することがスタートです。その上で、自分がコントロールできる範囲(自分の反応や考え方)に意識を向けるようにすると、影響は徐々に小さくなっていきます。環境ではなく「反応の選び方」を練習していきましょう。
- 機嫌を取る力をつけるには、毎日なにをすればいい?
-
おすすめの習慣は3つあります:①1日5分の感情記録(その日一番強かった感情を書く)、②週に2~3回の軽い筋トレや運動、③「自分にやさしい言葉をかける」意識です。どれも小さなことですが、継続すれば大きな効果が出ます。心を整えるのは、毎日の積み重ねです。
- 「気にしすぎ」をやめたいのですが、どうすればいいですか?
-
「気にしすぎ」は、自分の思考パターンに気づくことで改善できます。たとえば「この発言で嫌われたかも」と不安になったとき、それが事実かどうかを問い直すクセをつけると効果的です。また、「完璧でなくていい」と自分に許可を出すことも、気にしすぎを減らす第一歩です。
- 自分に優しくしようとすると、甘えになる気がします。大丈夫ですか?
-
自己への優しさは「甘え」ではなく、むしろ心の回復力を高める力です。セルフ・コンパッションの研究でも、自分に厳しすぎる人よりも、自分を受け入れられる人のほうが行動力や回復力が高い傾向にあります。「甘え」と「いたわり」は別物だと理解しましょう。
- 「怒り」などの強い感情をうまく処理できません。どうすればいいですか?
-
怒りは「二次感情」とも呼ばれ、その下には悲しみや不安などの一次感情が隠れています。まずは「自分は何に傷ついたのか」「本当はどうしてほしかったのか」を自問することで、怒りを正確に理解できます。そのうえで、運動や呼吸法などで身体的な発散も併用すると効果的です。
- 感情のセルフコントロールと我慢の違いがわかりません。
-
セルフコントロールは、感情を抑え込むことではありません。むしろ「感情に気づき、意図的に扱う力」です。一方、我慢は感情にフタをして無理に押し殺す行為で、結果的に心身に負担を残します。「感じないふり」ではなく「感じたうえで選ぶ」ことが真のコントロールです。
- 他人に期待しすぎて落ち込むことが多いです。期待しない方がいいですか?
-
期待そのものが悪いわけではありませんが、「こうあるべき」という期待が強すぎると、裏切られたときに強く傷つきます。相手を変えることはできないと理解し、「期待」ではなく「希望」に切り替えると、気持ちが楽になり、落ち込みにくくなります。
- どんなに頑張っても気分が晴れないときは、どうすればいいですか?
-
まず「無理に気分を上げようとしない」ことが大切です。感情には波があり、調子が悪いときも当然あります。そんなときは「やるべきことを絞る」「最低限だけこなす」「休む勇気を持つ」など、エネルギーを温存する行動が有効です。調子が戻るまで“待つ”のも立派な対応です。
- 毎日バタバタしていて、自分の心と向き合う時間が取れません。どうすれば?
-
1日1分でもいいので、「今どんな気持ちか」を内省する時間を作ってみてください。通勤中、トイレ、就寝前などのスキマ時間でOKです。心との対話に“まとまった時間”は不要です。小さな習慣を継続することで、やがて自分の感情に気づく力が育っていきます。
- 自分の機嫌を取るって、結局「自分勝手」になることじゃないの?
-
まったく逆です。自分の機嫌を自分で整えられる人ほど、他人に感情をぶつけたり、依存したりしません。むしろ周囲との関係も安定しやすくなります。「自分勝手」は相手を無視することですが、「自己調整」は他人を思いやる準備行為でもあるのです。
- マインドフルネスって効果あるんですか?続かない気がして…。
-
マインドフルネスは、感情のコントロールや集中力の向上に効果があると多数の研究で示されています。ただし「瞑想しなきゃ」と構えると続きません。呼吸に意識を向ける・今している作業を丁寧に味わうだけでも立派な実践です。習慣化のコツは“力を抜いてやること”です。
- 精神的に安定している人って、どんな考え方をしているの?
-
精神的に安定している人ほど「コントロールできるもの/できないものを区別する」「失敗=学び」ととらえるなど、現実的かつ前向きな思考習慣を持っています。ネガティブにならないのではなく、「引きずらない工夫」をしているのが特徴です。性格ではなく習慣の問題です。
- 感情を「我慢」しすぎると、どんな悪影響がありますか?
-
感情を抑圧し続けると、心身への悪影響が積み重なります。代表的なのは慢性的なストレス、睡眠障害、頭痛、胃腸トラブルなど。心理学では「情動抑制」と呼ばれ、うつ症状や不安傾向との関連も指摘されています。我慢=美徳ではなく、適切な「発散」や「認識」が必要です。
- 一人でいると落ち着くのに、職場だとすぐに疲れてしまいます。なぜですか?
-
人間関係の中では「気を遣う」「評価を気にする」など、エネルギー消費が激しくなります。特に内向的な人は、他人との距離感に敏感であるため、職場の対人ストレスで機嫌を保つのが難しくなる傾向があります。定期的に“ひとりの時間”を確保することが心の回復に有効です。
- ネガティブ思考をやめたいのに、つい最悪のパターンを想像してしまいます。
-
それは「予期不安」と呼ばれ、脳の生存本能による正常な反応です。むしろネガティブな予測は、準備や安全確保のための重要な機能でもあります。ただし、その思考に“巻き込まれすぎる”と苦しくなるため、「最悪と現実を区別する」習慣が大切です。紙に書き出すだけでも効果的です。
- 「何をしても楽しくない日」があります。これは甘えでしょうか?
-
甘えではありません。心が疲れていると、快楽や達成に対する反応(ドーパミン)が弱くなります。これは「快感喪失」と呼ばれる現象で、無理にポジティブを装わず、休養を優先するのが正解です。筋トレや日光浴などで神経系を刺激することで、回復が早まることもあります。
- ブラック企業で働いていたときのストレスが抜けません。もう辞めたのに…
-
長期的なストレス下にいた場合、脳や神経の反応パターンが「緊張状態」に固定されてしまうことがあります。これは“心の筋肉痛”のようなもので、回復には時間がかかることも。自律神経を整える習慣(呼吸・運動・自然との接触)を日常に取り入れることで徐々に回復していきます。
- 感情的になって後悔することが多いです。どうすれば落ち着いて話せますか?
-
まずは「反応と行動のあいだに“間”をつくる」ことがカギです。たとえば、深呼吸や「少しだけその場を離れる」など、物理的に落ち着く時間を入れることで衝動的な行動を防げます。言葉を発する前に「一拍置く練習」が、感情的なミスを減らす第一歩になります。
- 朝から気分がどんよりしていて何もやる気が出ません。どう立て直せば?
-
朝の気分は「前日の睡眠の質」と「起きてすぐの行動」に大きく左右されます。カーテンを開けて太陽光を浴びる、白湯を飲む、軽く身体を動かすだけでも脳が目覚めます。やる気が出るのを待つのではなく、「体を先に動かす」ことで感情があとからついてきます。
- いつも不安でソワソワしてしまい、落ち着きません。体の使い方で改善できますか?
-
はい、不安には身体アプローチが非常に有効です。たとえば腹式呼吸・背筋を伸ばす・ゆっくり歩くといった動作は、自律神経に働きかけて不安を和らげます。実際、姿勢や呼吸の変化だけで気分が改善する例は多く、筋トレも不安軽減に効果的だと報告されています。
- 日常に感謝しようとしても、心がこもりません。意味あるんでしょうか?
-
感謝は「気分に任せて湧いてくるもの」ではなく、「意識して注目する力」に近いです。たとえば“ありがとう日記”を1日1行つけるだけでも、脳はポジティブな側面を探す回路を強化します。最初は形式的でも構いません。続けることで「感じ方の解像度」が上がっていきます。
- 「自分に厳しく」「もっと努力しろ」と思ってしまいます。それでも自分に優しくするべき?
-
厳しさ=成長とは限りません。自己批判は一時的にやる気を出しても、継続的な努力や心の健康には逆効果です。セルフ・コンパッション研究でも、自分に優しい人ほど継続力が高いというデータがあります。努力をやめるのではなく、“やめないために”優しさが必要です。
その他の質問はこちらから:



の症状・原因と科学的に実証された解決策-300x200.png)
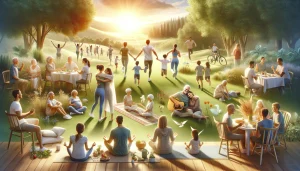
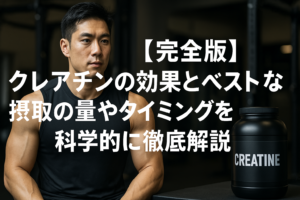
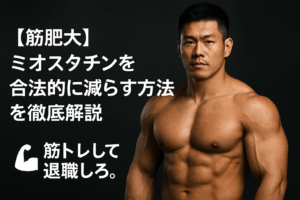

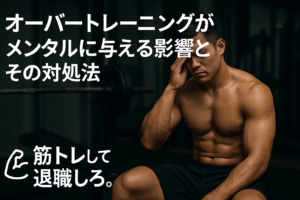


コメント