この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「自分軸で生きるって具体的にどういうこと?」
「自分軸で生きる人ってどんな特徴がある?」
「自分が自分軸で生きている人間かどうかが気になる」
 カワサキ
カワサキ他人の評価より自分の評価。
自分軸で生きる人の特徴に興味はありませんか?
この記事では、自分の感情や思考を深く理解し、確固たる意思決定を行う方法、さらにはリスクに立ち向かう力を養うための実践的な考え方・手段を紹介します。



自己成長ガチ勢の方はぜひ読んでみて下さい。
他人の評価ではなく、自分の価値観を基準に行動することで、幸福度と仕事満足度が上がる。
評価や報酬ではなく、自分がやりたいことに基づいて動く人ほど、メンタルが安定する。
嫌なことには「NO」と言える人ほど、燃え尽きにくく、自分の人生を自分で守れる。
こちらもおすすめ:
自分軸と他人軸の違い
まずは「自分軸」と「他人軸」の違いを確認しましょう。
心理カウンセラーの解説によれば、自分軸とは「自分がどうありたいか、自分がどうしたいか」を大切にする姿勢であり、他人軸とは「相手がどう思うか、相手からどう見えるか」を大切にする姿勢のことですdiamond.jp。
つまり、自分軸の人は意思決定の基準が自分の内側にあり、他人軸の人は基準が自分の外側(他者の目)にあると言えます。



以下に、具体的な違いを比較表にまとめました:
| 状況 | 他人軸の人の反応 | 自分軸の人の反応 |
|---|---|---|
| 上司から理不尽な残業を頼まれた | 評価が下がるのを恐れてイヤと言えずに従う | 自分の限界を考え、必要なら理由を伝えて断る |
| 友人との予定が体力的にきつい時 | 無理してでも付き合いを優先してしまう | 自分の体調を優先し、丁寧に事情を説明して断る |
| 仕事の目標設定 | 周囲の期待や世間体を基準に目標を決める | 自分が成長できるか、納得できるかで目標を決める |
| 成功や幸福の判断 | 他者からの評価や肩書き・収入で幸不幸を判断する | 自分の充実感や達成感で幸福度を感じる |



他人軸が強い人は、他人の期待に応えようと無理をして心身をすり減らすことが少なくありません。
それに対し、自分軸で生きる人は自分の信念に照らして行動するため、たとえ周囲と意見が違っても「自分は自分」と割り切る強さがあります。



この違いが具体的にどんな特徴となって現れるのか、科学的根拠をもとに見ていきましょう。
自分軸で生きている人の特徴 5選
ここでは自分軸で生きている人の特徴 5選について、下記の内容で触れます。
自分らしくいられる
自分軸で生きる人の大きな特徴の一つは、自分らしさを大切にしていることです。



他人の期待に合わせて自分を偽ったりせず、ありのままの自分でいようとします。
研究によれば、こうした「自分に正直な生き方」は幸福度や仕事への熱意と密接に関係しています。
例えば、2020年にニュージーランドのワイカト大学の研究者が75件・計35,500人分のデータをまとめたメタ分析では、「自分らしくあること(オーセンティシティ)」と「主観的な幸福度・仕事への熱意」にはともに中程度に強い正の相関関係(統計的な関連の強さ r = 0.4)があると報告されていますdrannasutton.wixsite.com。



これは、自分軸を持つ人ほど幸福で仕事にも前向きに取り組めている傾向の裏付けと言えます。
一方で、職場環境によっては自分を押し殺して働かざるを得ない場合もあります。
実際、イギリスの研究では上司の圧力や評価への不安から職場で本当の自分を隠してしまう人も少なくないことが指摘されていますbmcpsychology.biomedcentral.com。
自分軸で生きる人は、そのような場面でも必要以上に自分を偽りません。
適切に自分の意見や感情を表現し、「自分らしさ」を損なわない範囲で職場の要求と折り合いをつけることができるのです。



要するに、自分軸の人は自分に嘘をつかないのが特徴です。
これは長期的に見るとメンタルヘルスにプラスに働きます。
自分らしくいられる人ほど仕事や人生に対する満足度が高い傾向がデータで示されていますdrannasutton.wixsite.com。



ブラック企業から抜け出そうとする皆さんにとっても「自分らしさを取り戻すこと」は重要な鍵と言えます。
内発的な動機と価値観を持つ
自分軸で生きる人は、自分の内なる価値観や興味に沿って動く傾向があります。
他人軸の人が「周りから評価されたい」「お金や肩書きが欲しい」といった外発的な目標に引っ張られがちなのに対し、自分軸の人は



「自分が成長したい」
「良い仕事をして達成感を得たい」
など内発的な目標を重視します。



この違いは幸福度やメンタル面にも表れます。
心理学者の研究によれば、外発的な目標ばかり追い求める人は幸福度が低くなりがちです。
たとえば、米国の一連の研究では「お金・容姿・人気」といった外発的価値に執着している人ほど、主観的幸福感や自己実現感が低いことが示されていますselfdeterminationtheory.org。
逆に、「自己成長や人とのつながり」など内発的な目標を大切にする人は幸福度が高い傾向がありましたselfdeterminationtheory.org。



これは文化を超えて共通する現象で、ドイツの大学生を対象にした研究でも同様の傾向が確認されていますselfdeterminationtheory.orgselfdeterminationtheory.org。
さらに職場においても、内発的な動機づけは重要です。
2021年にベルギーのルーヴェン大学などが124件の研究を統合したメタ分析によると、社員の幸福度や仕事態度に最も強くプラスの影響を与えるのは「内発的動機づけ」であることが明らかになりましたselfdeterminationtheory.org。
この分析では、内発的に「仕事そのものが好き・やりがいがある」という気持ちを持って働く人ほど、仕事に対する満足感が高くポジティブな態度や行動が見られるとされていますselfdeterminationtheory.org。



逆に言えば、他人軸的に「お金のために我慢して働く」「評価のために嫌な仕事をする」状態では幸福度が上がりにくいのです。
ブラック企業で苦しんでいる人は、つい「周りに認められたい」「怒られたくない」という外発的要因で頑張りすぎてしまうかもしれません。
しかし、自分軸で生きる人の特徴から学べるのは、「自分が本当に大事にしたいものは何か」を見極めることの大切さです。



他人の期待ではなく、自分の価値基準で目標を設定し直すだけでも、仕事や人生の満足度は大きく変わってきます。
自己効力感が高い
自分軸で生きる人は、自分の人生を自分でコントロールできているという感覚(自己効力感)が強いことも挙げられます。
心理学では「内的統制」とも呼ばれる概念で、簡単に言えば



「起こる物事は自分の行動次第だ」
と感じる傾向です。
他人軸の人は反対に「自分の人生は周りの状況や他人によって左右される」と感じやすい(これを外的コントロール感と言います)。
この違いも科学的な証拠がはっきりしています。
2001年に米国で169件の研究結果をまとめたメタ分析では、「自分で物事をコントロールできる」という感覚が強い人ほど仕事の満足度が高いことが示されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
数値で言うと、自己効力感と仕事満足度の相関は約r = 0.32(中程度の強さ)であり、これは統計的に有意な関連です
職場で感じる理不尽さやストレスに対しても、「自分で状況を変えられる」と考えられる人ほど不満を溜めにくいのかもしれません。



さらに人生全般に目を向けると、自分軸の人は主観的な幸福度やメンタルヘルスも良好な傾向があります。
オーストラリアで行われた大規模パネル調査(15〜75歳の約17,000人を長期追跡)でも、自己効力感が高い人ほど人生の満足度や精神的健康度が高いと報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
具体的には、統計モデル上自己効力感が1標準偏差高まるごとに、人生満足度が約0.11標準偏差向上するという有意な効果量が示されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
また、自己効力感の高い人は健康的な行動(運動や禁煙)を取る率が高くpmc.ncbi.nlm.nih.gov、積極的に人間関係を築く傾向もありpmc.ncbi.nlm.nih.gov、そうした行動がさらに幸福感を高める好循環に入っていることも示唆されています。



要するに、自分軸で生きる人は「自分の人生の舵取りを自分でしている」という意識が強いのです。
ブラック企業で働いていると、自分の裁量がない環境から「何も変えられない…」と感じてしまうことも多いでしょう。
しかし、自分軸志向を持つ人はたとえ困難な状況でも



「自分にできることは何か」
「この先どう舵を切るか」
と主体的に考えます。



そうした姿勢が結果的に状況を好転させる行動につながり、より良い環境へ抜け出す原動力になるのです。
適切に自己主張し、境界線を守れる
自分軸で生きる人は、必要な場面で適切に自己主張し、自分の限界に境界線を引けるという特徴もあります。



つまり、嫌なことは「NO」と言える勇気があり、自分にとって譲れないものは守ろうとします。
ただしそれはわがままに振る舞うという意味ではなく、お互いを尊重しつつ自分の意見やニーズをきちんと伝えるコミュニケーションスキルを持っているということです。



この「適度な自己主張(アサーティブネス)」は、メンタルヘルスや職場での燃え尽き防止に効果があることが研究からわかっています。
例えば、2025年に中国・甘粛省の大学職員を対象に行われた研究では、自己主張力が高い人ほど仕事での燃え尽き(バーンアウト)症状が少ないことが示されましたlink.springer.com。
自己主張力と燃え尽きの関係はかなり強い負の相関(相関係数r = 0.74)が報告されておりlink.springer.com、これは統計的にも非常に顕著な傾向です。



言い換えれば、自分軸を持ちしっかりものが言える人は、そうでない人に比べて圧倒的に燃え尽きにくいということです。
また、自己主張のスキルはストレスの軽減にも直結します。
アメリカ心理学会(APA)の報告によれば、アサーティブネス(自己主張)訓練を行うことでストレスが有意に減少し、幸福感が高まることが確認されていますacrpnet.org。
実際、2016年にイランで高校生126人を対象にした実験的研究では、8週間の自己主張トレーニング後に参加者のストレスや不安レベルが有意に低下しましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
高校生の例ですが、「嫌と言えない」性格を訓練で改善したところ心の健康が向上したというわけです。



この結果は、年代や環境が違っても自己主張能力がメンタルヘルスに与えるプラス効果を示唆しています。
ブラック企業で働く人にとって、「NOと言ったら評価が下がるのでは」「自己主張したら人間関係が悪化するのでは」と不安になる気持ちは当然あります。



しかし自分軸で生きる人は、その場しのぎで他人に合わせるのではなく長期的な視点で自分の心身を守ることを優先します。
例えば



「これ以上残業すると自分が壊れてしまう」
と感じたら、勇気を持って上司に相談したり、場合によっては退職も検討します。
それは決して甘えではなく、自分の人生に責任を持つ態度と言えるでしょう。



結果的に、そのような人の方が健康的に働き続けられたり、より良い職場に巡り合える可能性が高くなるのです。
安定した自己肯定感
自分軸で生きる人は総じて自己肯定感が安定しており、他人からの評価に一喜一憂しにくいという特徴もあります。
自分の価値を自分で認めているので、周囲からの賞賛や批判に振り回されにくく、冷静に受け止めることができます。



このような安定した自己評価は、他人軸の人と対照的。
他人軸タイプの人はどうしても他者からの評価に自分の気分や行動を影響されがちで、周囲と比較して落ち込んだり嫉妬したりしやすくなります。
現代ではSNSも他人軸を助長する要因と言われます。
SNS上で他人の華やかな生活を見て自分と比べてしまうと、自分の幸せまで小さく見えてしまうことがありますよね。



気持ちはわかる。
実際、2020年に韓国で20代〜30代を中心とした236人を対象に行われた調査研究では、他人と比較しがちな人ほど自己肯定感が低く、心理的な幸福度も低いことが報告されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
この研究ではSNS上での比較傾向がメンタルに及ぼす影響を分析しており、「自分は他人より劣っているのでは」という思いが強い人ほど、社会的な支えを感じにくくなり自己評価が下がり、その結果として幸福感も損なわれるという悪循環が示唆されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
さらに別の研究では、SNSの過度な利用が羨望(エンヴィ)によるネガティブ感情を生み出し、幸福感を減少させることも指摘されていますpmc.ncbi.nlm.nih.gov。
Facebookの利用者は他人との比較が増えるほど自己評価や幸福感が下がり、Instagramでは投稿を見るだけでも直接的に幸福度が下がる傾向が観察されましたpmc.ncbi.nlm.nih.gov。



つまり、他人軸が強い人ほどSNSで他人の充実ぶりを見ては落ち込み、自分に自信が持てなくなるリスクが高いのです。
それに対し、自分軸で生きる人は「人は人、自分は自分」という割り切りができるため、周囲と自分を過度に比較しません。
例えばSNSの使い方一つとっても、自分軸の人は他人の投稿に過敏に反応せず、



「あの人はあの人、自分には自分のペースがある」
と冷静です。
自己肯定感が安定しているので、他人の成功を見ても焦燥感で自分を見失うようなことが少なく、むしろ素直に賞賛したり参考にしたりできます。



結果として、メンタルの安定度や満足感も高く保てるのです。
研究データから見ても、他人と比較しすぎない方がメンタルは健全に保たれる傾向があります。
ブラック企業で周りと競わされたり、「自分はダメだ」と否定され続けたりすると自己肯定感が低下しがちですが、自分軸で生きる人の特徴にならって自分の良いところを認め、他人の評価とは距離を置くことが重要です。



それが結果的にストレス耐性を高め、どんな環境にいても自分を見失わずに済む秘訣と言えるでしょう。
まとめ



いかがでしたでしょうか。最後に今回の記事の内容をまとめて締めたいと思います。
自分軸で生きることができている人には、以下のような特徴が科学的にも裏付けられています。
- 自分らしさを大切にしている
→ 自分に正直で、自分を偽らずに生きる姿勢。幸福度・仕事の熱意と強い相関あり。 - 内発的な動機に従って行動している
→ 「他人からの評価」よりも「自分の成長」や「達成感」を優先。幸福感が高まりやすい。 - 自分の人生を自分でコントロールしているという感覚がある
→ 困難な状況でも「自分にできること」に意識を向けるため、精神的な安定感が強い。 - 自己主張ができ、必要な境界線を引ける
→ 無理な要求に「NO」が言える。燃え尽き症候群の予防やストレス耐性にもつながる。 - 他人の評価に一喜一憂しない、安定した自己肯定感がある
→ 他人と比較しすぎないことで、SNSや職場の人間関係でも心を保ちやすい。
また、自分軸と他人軸の違いは日々の行動や判断の基準にも表れます。



自分軸で生きることは、わがままではなく「自分の人生に責任を持つ」ための選択です。
今回紹介した研究や実例をもとに、「自分の軸はどこにあるのか?」を見直すきっかけになれば嬉しいです。



今回の記事は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よくある質問
- 自分軸と他人軸の違いは何ですか?
-
自分軸とは、自分の価値観や信念に基づいて行動や判断を行う生き方です。
周囲の期待や社会的な評価に左右されることなく、自己の目標や考えを中心に据えた生き方といえます。
一方、他人軸は他人の価値観や期待に合わせて行動するスタイルで、自分の本心よりも外部の意見に従いがちです。
- 自分軸で生きるためには何から始めれば良いですか?
-
まず自己認識を高めることが重要です。
日々の行動や感情を振り返り、自分が何を望んでいるのか、どのような価値観を持っているのかを明確にすることから始めましょう。
マインドフルネスやジャーナリングを活用し、日常の中での内省を深めることで、自分軸の基礎が作られます。
焦らず一歩ずつ進めることが、習慣的な自分軸の実践に繋がります。
- 自分軸で生きることのメリットは何ですか?
-
自分軸で生きることは、メンタルの安定やストレス耐性の向上に大きく寄与します。
自己認識が深まることで、自分の行動や感情をコントロールでき、外部の影響に左右されにくくなります。
また、自己決定に基づいた生活は幸福度を高め、日々の充実感や達成感を得やすくなります。
長期的に見ると、人生の満足度を向上させ、自己成長を促進します。
- 自己決定能力を高めるために有効な方法は?
-
目標の明確化やリフレクション(振り返り)の実施が効果的です。例えば、短期的な目標と長期的な目標を分け、それぞれに具体的な行動計画を立てましょう。
また、定期的に自己反省を行うことで、過去の選択が自分にとってどのような影響を与えたかを確認できます。
さらに、フィードバックを取り入れることで、視野が広がり自己決定力が向上します。
- 自分軸で生きると職場で浮いてしまうことはありますか?
-
確かに、自分軸を重視すると他人と異なる意見や価値観を持つことが増えるため、周囲から孤立することもあります。
しかし、自分軸を持つことは必ずしも他者との対立を意味しません。
自己の価値観に基づきつつも、他者の意見も尊重することで、職場でのバランスを保ちながら自己実現を目指すことが可能です。
適度に自己主張を行いながら、他者との協調も大切にしましょう。
- 内発的動機づけとは何ですか?
-
内発的動機づけとは、自分の内部から生じる欲求や興味に基づく行動意欲を指します。
外部の報酬や評価に依存せず、自己成長や自己実現を目指す際のモチベーションとなります。
内発的動機づけが強い人は、充実感や満足感を得やすく、日々の目標達成に向けた集中力が増します。
自分の価値観に沿った目標設定を行うことが、内発的動機づけを高めるコツです。
- リスクに対処するための心構えはありますか?
-
リスクを恐れずに受け入れるためには、リスクの正確な評価が大切です。
リスクの可能性と影響を理解し、予備プランを考え、万が一に備える心構えが必要です。
また、過去の経験から学び、同様の状況に対応するスキルを蓄積しておくことも有効です。
ポジティブ思考を取り入れ、変化や不確実性を受け入れる姿勢がリスク管理能力を強化します。
- 自分軸を持つことがメンタルヘルスにどう影響しますか?
-
自分軸を持つことで、外部からのプレッシャーを減らし、精神的な安定を得やすくなります。
- 自己認識力を高める具体的な方法はありますか?
-
自己認識力を高めるには、マインドフルネスや日記を書くことが効果的です。
マインドフルネスを取り入れると、自分の感情や思考に対する意識が高まり、自己理解が深まります。
日記に感じたことや考えたことを記録することで、自分の行動パターンや感情の起因を振り返ることができ、自己認識力が向上します。
- 他人軸から自分軸に移行するにはどのようなステップが必要ですか?
-
他人軸から自分軸に移行するには、まず自分の価値観や目標を明確にすることから始めましょう。
他人の期待に応える習慣が強い場合、自分にとって本当に大切なものを見つけることが難しいかもしれませんが、日常の小さな選択から自己決定を意識することで、自分軸への移行がスムーズに進みます。
その他の質問はこちらから:




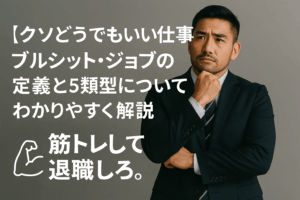
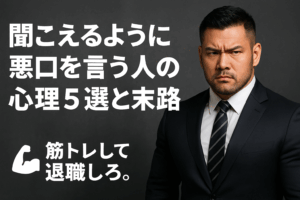
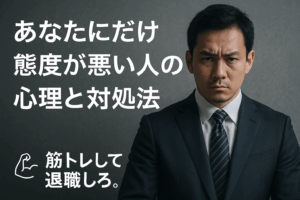
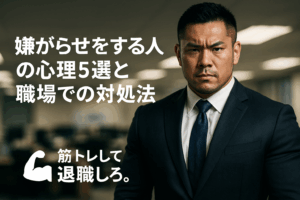

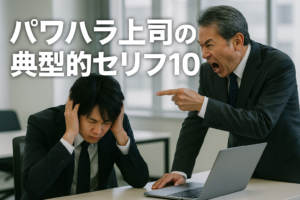
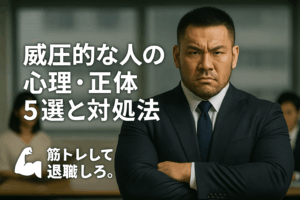

コメント