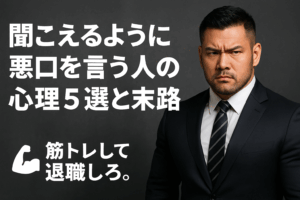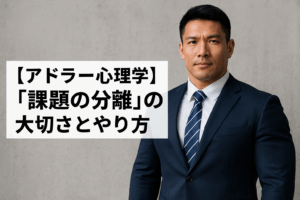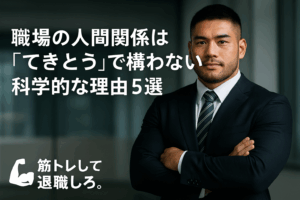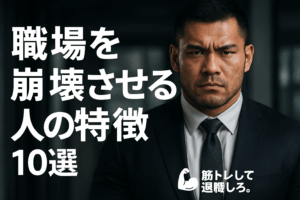この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「また怒鳴られた…なんで自分ばっかり…」
「こんな言い方されて、やる気なくなるのも当たり前じゃない?」
「指示どおりにやったのに『勝手なことするな』ってどうすればいいの?」
 カワサキ
カワサキ「そもそも、上司はなんであんな変なことを言うのか?」を知りましょうというお話です。
あと、この記事で書いている「対処法」のほとんどは、上司がNPD(自己愛性パーソナリティ障害者)だった場合は無意味です。
とっとと退職して離れるのがベスト。
真面目に相手するだけ時間の無駄。あなたの人生から締め出して下さい。
パワハラ上司の典型的なセリフ10選を完全解説
なぜ上司はその言葉を使うのかを心理学で読み解く
実践的な会話例とともに、効果的な対処法を提示
理不尽な叱責や嫌味に悩んでいませんか?



「常識でしょ」「やる気あるの?」そんなパワハラ上司の暴言に心をすり減らしていませんか?
職場での言葉の暴力は、メンタルとパフォーマンスの両方をむしばみます。
本記事では、パワハラ上司がよく口にする10のセリフを徹底的に洗い出し、心理学・法律・会話術の観点から「賢い切り返し方」を紹介します。
すべてのセリフに「冷静に反論する方法」と「メンタルを守るヒント」を添えているので、現場で即活用できます。
「怒鳴られても黙るしかない…」そんな状況から抜け出すために、まずは言葉の暴力の正体を知りましょう。
ブラックな環境でもあなた自身の尊厳は守れます。



パワハラに怯えず、自分を守り抜くスキルを身につけたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
はじめに
職場で上司から心ない言葉を浴びせられ、 「自分が悪いのだろうか…」 と悩んでいませんか? いわゆる パワーハラスメント(パワハラ) は、日本の職場でも深刻な問題です。
厚生労働省の調査によれば、5人に1人が過去3年以内に勤務先でパワハラを受けた経験 を持ち、その内容でもっとも多いのは「脅迫・侮辱・暴言」など精神的な攻撃でしたnews.ntv.co.jp。
パワハラは被害者のメンタルヘルスを損ない、仕事への意欲や生産性を低下させることが多く、研究でも 職場いじめ(パワハラ)はストレスや燃え尽き症候群の増加、仕事満足度の低下と有意に関連 すると報告されていますjournals.plos.org。
また、パワハラ加害者側の心理的特徴として、「気が小さい」「自信がない」「高圧的でないと人を動かせないと思い込んでいる」 などが挙げられます。
こうした背景にもかかわらず、20代〜30代の若手社員の中には



「上司のパワハラ発言にどう対処すればいいか分からない」
「反論したいけど悪化しそうで怖い」
と悩む方も多いでしょう。
しかし2022年の『パワハラ防止法全面施行』により、 企業にはパワハラ防止策を講じる義務 も課されています。



つまり、法的にも不当な言動に怯える必要はなく、適切に対処・相談することは労働者の正当な権利です。
とはいえ日々の現場では、まず その場での上手な切り返し によって上司の暴走を和らげたり、自分の心身を守ったりするスキルも役立ちます。



以下では、パワハラ上司が部下によく浴びせる典型的なセリフ10選 を取り上げます。
それぞれの発言の心理的背景や意図を心理学的観点から分析し、効果的な切り返し方 を法的・心理的根拠にもとづいて提案します。
若手の社会人が萎縮せずに対処するヒントとして、具体的な会話例も交えて解説します。



自分の上司に該当する箇所を重点的に読んでみて下さい。
パワハラ上司によくあるキツいセリフ・トップ10
実際に多くの部下を傷つけている上司の発言には、どのようなものがあるのでしょうか。
『東京で働くビジネスパーソンの疲れの実態に関する調査 2018』では、「上司の言葉で疲れが倍増した経験がある」人が41%にも上り、具体的な言葉として次のようなセリフが挙げられました。



順位とともに見てみましょう。
| 順位 | 上司のセリフ | 回答率(複数回答) |
|---|---|---|
| 1位 | 「常識でしょ」/「当たり前でしょ」 | 24.4% |
| 2位 | 「前にも言ったよね?」 | 23.9% |
| 3位 | 「まだ終わらないの?」/「仕事遅いね」 | 21.0% |
| 4位 | 「そんなこともできないの?」 | 20.7% |
| 5位 | 「やる気あるの?」 | 17.3% |
| 6位 | 「自分で考えてやれ」&「勝手にやるな」 | 15.9% |
| 7位 | 「仕事だから」/「プロなんだから我慢してやって」 | 15.4% |
| 8位 | 「暇そうだね」 | 14.9% |
| 9位 | 「忙しいから後にして」&「なんで早く言わないの?」 | 13.4% |
| 10位 | 「前例がないから」/「慣習だから」 | 10.7% |
上記のように、部下のやる気をくじき、精神的負担を与える発言 が多数ランクインしています。



ろくでもねぇ。
これらはいずれも部下にとっては嫌味や侮蔑と受け取れる言い方であり、実際に こうした発言を繰り返すことで上司と部下の信頼関係は崩れていく と指摘されています。



では、これら10のセリフについて一つひとつ詳しく見ていき、その裏にある心理と対処法を考えてみましょう。
1. 「常識でしょ」/「当たり前でしょ」
心理的背景・意図:
上司が部下に対して



「こんなの常識だ」
「当たり前だ」
と言うとき、そこには



「そんなことも知らないのか」
という侮蔑 が込められています。
経験豊富な上司にとっては容易なことでも、部下にとっては初めてだったり難しかったりするかもしれません。
本来であれば教えるべき場面で



「常識でしょ」
と突き放すのは、自分の知識・価値観が絶対だという思い込み や、部下の未熟さへの苛立ちが原因と考えられます。



「常識でしょ」
「前にも言ったよね」
といった言葉は部下に



「もう上司に頼りたくない」
という思いを抱かせ、相談や報告をためらわせてしまいます。
上司自身は



「自分で考えさせるため」
と正当化するかもしれませんが、心理学的には相手の自尊心を傷つけ萎縮させる発言であり、建設的な指導とは言えません。
効果的な切り返し方:
ポイントは、感情的に反発せず冷静に質問し直すこと です。
上司の



「常識でしょ」
という叱責に対して萎縮して黙り込んでしまうと、上司は



「理解したのだな」
と解釈し、以降も具体的な指導をしなくなる恐れがあります。
代わりに、一度受け止めつつ具体的な指示を仰ぐ ようにしましょう。
例えば



「申し訳ありません。次回から気をつけますので、具体的にどうすれば良いかご教示いただけますか?」
と尋ねます。
謙虚な姿勢を示しつつ質問することで、上司はただ



「常識だ」
と繰り返すだけでは済まなくなり、具体的な説明をせざるを得ません。



「否定的な指摘に対する質問返し」は、相手の発言の真意や根拠を問いただす効果があります。
また、上司の叱責を真正面から否定せず一部受け入れる(「そうですね、自分の勉強不足でした」)ことで相手の攻撃感情を和らげつつ、本題に引き戻す効果もあります。



このように冷静に対応すれば、上司も感情的になりにくくなり、単なる嫌味から建設的な会話にシフトできる可能性が高まります。
会話例:



上司:「こんなの常識でしょ?」



部下:「失礼いたしました。私にはまだ難しく感じました。次回うまく対応できるように、注意すべき点を教えていただけますか?」
このように尋ねれば、上司も



「当たり前だ」
で終わらず具体的な指導に乗り出すでしょう。



そもそも、『やるのが当たり前』ではなく具体的な指示や期待を伝えるべきですからね。
常識だと一蹴されてもめげずに次につなげる質問を投げかけることが効果的です。
2. 「前にも言ったよね?」
心理的背景・意図:



「この前も教えたはずだが?」
というこのセリフには、



「なぜ覚えていないんだ」
という苛立ちが表れています。
上司からすると二度手間に感じて怒っているのかもしれません。
しかし、業務上の指示は一度言っただけでは浸透しない場合も多く、本来は 部下が理解できるまで伝えるのが指導者の役割 のはずです。
それを放棄し、



「前にも言ったよね?」
で済ませる背景には、上司自身のコミュニケーション不足や「一度で理解させられない自分の指示力の低さ」への無自覚があると考えられます。
また、この言葉をかけられた部下は委縮してしまい、以降わからないことがあっても質問をためらうようになります。



結果としてミスや誤解が増え、人間関係も悪化してしまう恐れがあります。
効果的な切り返し方:
一度指摘を受けたら二度と確認してはいけない…そんなプレッシャーを感じて黙り込む必要はありません。
冷静に事実を確認し、必要なら記録に残す姿勢を示しましょう。
例えば上司に



「前にも言ったよね?」
と言われたら、



「ご指摘ありがとうございます。前回伺った内容は〇〇という理解でしたが、念のため再確認させてください」
と返します。
一度は自分が聞き漏らした可能性を認めつつ、認識のすり合わせを申し出るのです。
ポイントは、責任転嫁しないこと。



「聞いていません」
「説明不足では?」
などと返すと上司の機嫌を損ねてしまいます。



代わりに「自分の理解が足りなかったので確認したい」という形にすることで、上司も応じやすくなります。
また、メモを取る・メールで復唱する といった対応も有効です。
口頭指示だけだと記憶違いや伝達ミスが起こりえますので、再度確認した内容は
「○○の件、以前もご指示いただいていたのに確認不足で失礼しました。△△の対応で進めます」
とメールで送るなど形に残しましょう。



こうすることで上司も真剣に伝えねばと思いますし、後日「言った/聞いてない」の水掛け論を避けることができます。
会話例:



上司:「これ、前にも言ったよね?」



部下:「申し訳ありません。前回は〇〇という認識でしたが、念のためもう一度要点を確認させてください。 次回以降は確実に対応いたします。」
このように 事実確認を求める姿勢 を示せば、上司も単に部下の失念をなじるだけでなく具体的な説明に戻りやすくなります。



結果的にミスの防止にもつながり、上司部下双方にメリットのある対応と言えます。
3. 「まだ終わらないの?」/「仕事遅いね」
心理的背景・意図:
進捗が思わしくない部下に対し、苛立ちや焦りから出る言葉です。
上司の心情としては納期や上層部のプレッシャーに追われ、



「早く終わらせて成果を出してほしい」
という思いがあるのでしょう。
しかし



「まだ終わらないの?」
と急かすだけでは、具体的な改善策の提示も支援もないままプレッシャーだけを与える ことになります。



「仕事遅いね」
という言葉には、部下の能力や努力を軽視し見下すニュアンスも含まれています。
心理学的にはこれは動機づけに逆効果であり、急かされ萎縮した部下はかえってミスを増やしたりパフォーマンスを悪化させたりする恐れがあります。



上司自身も余裕がなく感情的になっている証拠で、部下への配慮が欠けている状態です。
効果的な切り返し方:
まず、感情的に



「遅くないです!」
と反論するのは逆効果です。
客観的な進捗状況を報告し、必要なら助言を仰ぐ 形に切り返しましょう。
具体的には、



「現在○割ほど完了しております。残りは△時頃までに終わる見込みです」
と定量的に進捗を伝えることです。
上司は単に遅いと感じて不安になっている可能性が高いので、数字や時間で伝えることで安心感を与えられます。
また、



「もし急ぎであれば優先順位の指示をいただけますか?」
「効率を上げるために何か良い方法があればご教示ください」
といった 前向きな提案 も有効です。
ただ萎縮するのではなく、問題解決思考を示すことで上司も建設的に考えざるを得なくなります。
さらに、業務量が明らかに過大で遅れが出ている場合には、上司にリソース配分の見直しを相談することも必要です。



「仕事遅いね」
と批判するだけではパワハラになりかねず、適切な目標設定や支援をせずに過度な要求をするのは厚労省の定めるパワハラ類型(④過大な要求)に該当し得ますnews.ntv.co.jp。
そのため、



「◯◯の対応と並行しているため時間がかかっています。
優先順位を付け直してよろしいでしょうか?」
などと打診し、現状を共有しましょう。
会話例:



上司:「ちょっと、まだ終わらないの? 本当に仕事遅いね。」



部下:「申し訳ありません。現在全体の7割まで完了しており、あと1時間ほどで仕上がる見込みです。(必要であれば)より迅速に進めるために優先度の調整などご指示いただければ対応いたします。」
このように答えれば、上司も



「遅い!」
という漠然とした不満から具体的な時間感覚を持てます。



「自分も急ごう」
と前向きに受け取られ、叱責よりも進捗共有と協力のムードに変えられるでしょう。
また、ハラスメント防止の観点からも「どうして遅いんだ」と責める代わりに「どうすれば効率的にできるか一緒に考えよう」といった声掛けが推奨。



部下の側からそのきっかけを作ることで、上司の意識も前向きに切り替えさせる効果が期待できます。
4. 「そんなこともできないの?」
心理的背景・意図:
これは部下の能力不足を直接的に非難する言葉です。



「こんな簡単なこともできないのか」
というニュアンスには、上司の失望や怒り、そして見下しが含まれています。
背景には、上司自身が当たり前にできることなので



「努力不足だ」
「センスがない」
と感じてしまう心理があるでしょう。
しかし、このような人格や才能を否定する叱責は、指導というより侮辱に近い行為です。
実際、過去の裁判例でも「『あんたは実力がない』『あんたなんかいなくてもいい』といった人格否定の暴言は違法なパワハラ」と判断されていますkigyobengo.com。
上司が



「そんなこともできないのか」
と吐き捨てるとき、そこには部下を育てようという意識の欠如が見られます。
『そんなこともできないの?』と言うだけで放置するのは部下の心を傷つけるだけで誰も得をしません。



つまり、この発言は上司自身の指導放棄であり、部下への侮辱以外の何物でもありません。
効果的な切り返し方:
露骨に能力を否定されるとカッとなってしまいがちですが、ぐっとこらえて冷静さを保つことが重要です。
効果的な切り返し方は、不足部分の具体化と改善意欲の表明です。
例えば



「至らず申し訳ありません。次回までに〇〇を習得し、できるようにいたしますので、ご指導いただけますでしょうか」
と返してみましょう。
まず自分の不十分さを認めつつ、次回までに改善する意思を示します。
そしてポイントは、上司にも具体的な指導を促すことです。
ただ



「すみません…」
で萎縮して終わるのではなく、



「どの部分を改善すべきかご教示ください」
と伝えることで、上司は建設的なフィードバックを返さざるを得なくなります。
この切り返しには心理学的な効果もあります。
上司が感情的に部下を叱責するとき、部下がしおらしく前向きな姿勢を見せると、上司の中にある 「教育しなければ」という責任感 が刺激され、頭ごなしの暴言を続けにくくなるのです。
また、部下が素直に学ぶ姿勢を示すと、上司も自分の指導力不足を自覚しやすくなります。



「できないなら教えるのが上司の役目」という視点を取り戻させる効果があるということですね。
会話例:



上司:「お前、そんなこともできないの?情けないな。」



部下:「ご期待に沿えず申し訳ありません…。次はできるように改善したいので、差し支えなければどの点を重点的に学ぶべきかご指導いただけますか?」
このように返せば、上司も



「できないのか!」
と突き放した手前、何かしらアドバイスをせざるを得ません。
仮に



「全部だ!」
と乱暴に言われても、



「では△△の点から取り組んでみます」
などと冷静に受け答えしましょう。
その態度に上司が冷静さを取り戻せば、「そんなこともできないのか」という暴言は次第に影を潜め、具体的な指導へと会話が移行していくはずです。



本来あるべき指導は「何が難しいのか一緒に見てみよう」といった姿勢ですから、部下側からそれを引き出すよう促すわけです。
5. 「やる気あるの?」
心理的背景・意図:
これは部下の勤務態度やモチベーションを疑問視する発言です。
思うような成果が出ていないときや、指示に対する反応が鈍いと感じたとき、上司は



「お前、本当にやる気あるのか?」
と問い詰めることがあります。
この背景には、成果が出ない原因を部下の意欲不足のせいにしたい心理があります。
本来、成果不振の原因は業務プロセスや環境、人員配置など様々ですが、上司がそれらを精査せずに部下の「やる気」の問題にしてしまうのです。
また、自分が若い頃は上司に言われなくても必死でやったという自負や、「甘えているのではないか」という世代間ギャップも影響しているかもしれません。
しかし



「やる気あるの?」
と疑われた部下は理不尽な思いを抱き、強い無力感やモチベーション低下につながります。



努力しているのにそう言われれば不満が募り、逆に本当にやる気がなくなってしまう「自己成就予言(悪い予言の成就)」に陥る危険もあります。
効果的な切り返し方:
自分のやる気・熱意はしっかり持っていることをまず伝えましょう。
ただし感情的に



「やる気はあります!」
と食ってかかるのはNGです。
上司の叱責を一度受け止めつつ、事実と意思を冷静に述べることがポイントです。
例えば



「ご心配をおかけして申し訳ありません。決してやる気がないわけではなく、日々全力で取り組んでいます。ただ結果が伴っておらず、自分でももどかしく感じています。○○の部分で改善を試みます。」
というように返答します。
まず「やる気がないわけではない」ことを明言し、次に「結果が出ず悔しい」という自己開示をすることで上司の誤解を解きます。



そして具体的な改善策や次の目標に言及することで、前向きな意思を示しましょう。
心理学的に、叱責に対して前向きな目標を語る姿勢は セルフアファーメーション(自己肯定的な主張) にもなり、周囲にも「この人はやる気がある」という印象を与え直す効果があります。
一方で、本当に業務意欲が低下している場合もあるでしょう。
その場合でも



「はい、実はモチベーションが下がっています…」
と正直に言うのは避けたほうが無難です。
なぜなら上司との信頼関係が十分でない状況でそれを伝えると、



「じゃあ辞めろ」
という風に、さらなる叱責や圧力などにつながりかねないからです。
※「やる気がないなら辞めてしまえ」は典型的なパワハラ発言で、脅迫的な退職強要とみなされる恐れがあります。



絶対に言ってはいけない言葉です。
したがって、たとえ今モチベーションが低くとも、「やる気あるのか?」と問われた場面では「ある」という前提で対処するのが賢明です。



その上で後日、信頼できる別の上司や人事に現在の悩みを相談するとよいでしょう。
会話例:



上司:「お前さ、本当にやる気あるの?」



部下:「ご心配をおかけしてすみません。決してやる気がないわけではなく、むしろ成果を出そうと努力しています。 ただ、まだ結果が伴っておらず自分でも歯がゆいです…。明日からは△△のやり方を工夫してみようと思います。」
このように 落ち着いて自己の意欲と課題を説明 すれば、上司も頭ごなしに



「(やる気)ないだろう」
と決めつけづらくなります。



「やる気がない」とレッテルを貼られてしまうと、その後何をしても色眼鏡で見られがち。
誤解は早めに解消し、こちらの本気度を伝えることが大切です。
その姿勢を見せ続ければ、上司の方も



「もしかしたら仕事の割り振りやサポートの問題かもしれない」
と気づくかもしれません。
6. 「自分で考えてやれ」&「勝手にやるな」
心理的背景・意図:
この2つのセリフは一見逆の意味ですが、組み合わさると非常に厄介な状況を生みます。
最初に



「自分で考えてやれ(いちいち聞くな)」
と言われたので自主的に判断して動いたら、



「なんで勝手にやった!」
「報告しろと言っただろ」
と叱られる――このようにどう振る舞っても叱責される二重拘束のことを心理学では「ダブルバインド(二重拘束)」と呼びますhealth.eonet.jp。



パワハラ上司は意図的か無意識か、このダブルバインドを部下に突きつけてしまうことがあります。
一つには上司自身が明確な指示のビジョンを持っておらず、部下に丸投げした挙句に結果だけ見て文句を言うケースがあります。
または、上司が常に部下を否定・支配しておきたいという心理から、どちらに転んでも部下を責められる状況を作り出している場合もあります。
いずれにせよ、部下にとっては



「聞けば怒られ、勝手にやっても怒られる」
という理不尽極まりない状態であり、強いストレスを感じますhrmos.co。



このようなコミュニケーションは当然ながら健全ではなく、繰り返されればパワハラの一種と判断され得ますjinjibank.jp。
効果的な切り返し方:
ダブルバインド状況に陥ったときは、上司の矛盾をやんわり指摘して整合性を取ってもらうことが必要です。
ポイントはあくまで冷静かつ丁寧に行うこと。



「でも前は◯◯と言ったじゃないですか!」
と感情的にぶつけるのは火に油を注ぎます。



代わりに次のように対応しましょう。
ケースA: 「自分で考えてやれ」と言われた場合:
一旦素直に了承しつつ、後で確認の機会を残すようにします。
例えば



「承知しました。それでは〇〇については自分の判断で進めてみます。途中で確認いただきたいポイントが出ましたらご相談してもよろしいでしょうか?」
と返すのです。
こう言っておけば、完全に丸投げされたわけではなく上司にも関与の余地を残すので、後で



「なんで勝手にやったんだ!」
という叱責をある程度予防できます。
上司も



「自分でやれと言った手前、任せるしかないが大丈夫かな」
という気持ちになるので、むしろ適度に気にかけてもらえる可能性があります。
重要なのは、「自分でやれ」という指示を受けた事実を会話の中に明示しておくことです。



「承知しました。では自分で進めますね」
とこちらが復唱するだけでも効果があります。
ケースB: 「勝手にやるな」と怒られた場合:
まずは謝罪しつつ、前回の指示との齟齬を冷静に説明します。



「失礼しました。以前ご報告せず進めてしまった際にご注意いただいたので、今回は確認すべきか悩んだ末に動いてしまいました。」
といった具合です。
ポイントは「前回注意されたからこそ、今回はこうした」と 過去の上司の指示を尊重した結果である ことを伝えることです。
こう言われれば上司も強く責めにくくなります。



「勝手に判断してすみません。ただ、指示を仰ぐ時間が取れず緊急だと思い進めました。次回からはお忙しくても要所で確認するようにいたします。」
と続け、今後の対策も示しましょう。



過去の経緯と今後の改善策をセットで述べることで、上司は単に感情的に怒鳴るモードから状況を整理して考えるモードに切り替わりやすくなります。
会話例:



上司:「おい、なんで俺に確認もなく勝手に進めてるんだ!」



部下:「申し訳ありません!前回、確認せず動いてしまった際にご注意を受けたので、今回はまず手を動かして早めに形にした方が良いかと考えてしまいました。 今後は進め方について必ず要所で報告いたします。」
この発言には、「確認せずに進めて叱られた前例があったため今回の判断に至った」というロジックが含まれています。
上司は自分の指示の矛盾に気づけば、



「そうか、前はそう言ったな…」
と納得し、頭ごなしの叱責を収めて指示スタイルを改めるきっかけになるかもしれません。
実際、産業カウンセラーの大野萌子氏も「ダブルバインド上司には部下側から整合性を求める防衛策」を推奨していますhealth.eonet.jp。



理不尽な命令に振り回されそうになったら、丁寧に疑問を呈することで軌道修正を働きかけましょう。
(※補足:ダブルバインド状態が解消されない場合、部下は深刻なストレスを抱えます。「どうせ何をしても怒られる」との学習性無力感に陥り、心身に不調をきたす恐れもあります。そのような場合は職場の他の信頼できる上司や人事部に相談し、必要なら社内異動や専門機関のカウンセリングを検討してください。パワハラ防止法のもとでは会社にハラスメント相談窓口の設置が義務付けられているのでhealth.eonet.jp、泣き寝入りせず活用しましょう。)
7. 「仕事だから」/「プロなんだから我慢してやって」
心理的背景・意図:
部下が業務上の不満(長時間労働や無理な要求など)を口にしたときに、上司が



「嫌でもやるのが仕事だ」
「プロなら文句言うな」
と返すケースです。
この発言の背景には、
「仕事は苦しくて当たり前」「自分も我慢してきたのだからお前もやれ」
という古い価値観や、自分が受けた苦労を他人も味わうべきだという心理があるでしょう。
また、



「労働には対価が払われているのだから従業員は何でも言うことを聞くべきだ」
という権威的な思い上がりも見え隠れします。



上司自身が過酷な環境で耐えてきた場合、それを正当化するために同じ苦労を部下にも強いる傾向が指摘されています。
いずれにせよ、「仕事だから我慢しろ」という言葉は相手の感じている苦痛や負担を軽視・否定するものであり、コミュニケーションとしては望ましくありません。



これを言われた部下は「この上司に何を言っても無駄だ」と感じ、相談する気力を失ってしまうでしょう。
効果的な切り返し方:
このような発言には、真正面から反論すると対立が深まる恐れがあります。



一旦受け止めつつ、現実的な提案や自分の状況説明を織り交ぜることがポイントです。
例えば残業が続いて辛いと訴えたのに



「仕事なんだから我慢しろ」
と一蹴された場合、



「おっしゃる通り、プロとして責任を全うしたいと考えています。ただ、現状は〇〇の理由でパフォーマンスが落ちかねません。より良い成果を出すために△△の調整をご検討いただけないでしょうか?」
と切り返せます。



一度「プロとしてやり遂げます」という姿勢は示しつつ、このままでは生産性や健康に悪影響がある可能性を冷静に伝えるのです。
「我慢しろ」に対し「はい我慢します」だけでは自分が潰れてしまいますから、上司に状況を直視させる情報提供が必要です。
具体的には、



「現在連日○時間の残業が続いており、さすがに集中力が低下しています。このままではミスが発生するリスクが高いと感じます」
と事実とリスクを伝えます。
その上で



「○○の期限延長をクライアントに交渉できないでしょうか」
「他のメンバーにも一部手伝ってもらえないでしょうか」
と代替案や解決策を提案します。
これにより、上司も「仕事だからやれ!」と根性論を繰り返すだけではなく、現実的な判断をせざるを得なくなります。
法的な観点からも、業務上明らかに不要な長時間労働の強要や、過度な我慢の強制はパワハラに該当し得ますnews.ntv.co.jp。
上司がそれを理解していれば、



「このままだと労基法に触れる可能性があります」
といった一言も効くかもしれません。



しかし実際の会話で法律を直接持ち出すのは角が立つため、「安全」「効率」「リスク管理」といったビジネス上の合理性に訴える方が受け入れられやすいでしょう。
会話例:



上司:「仕事なんだから文句言わずに我慢してやれ。プロなんだからできるよな?」



部下:「承知しました。プロとして責任をもってやり遂げたいです。 ただ正直申し上げて、ここ数日ほとんど休みなく業務が続き、少し判断ミスが増えてきている自覚があります。より確実に成果を出すために、明日は午前中休息をいただいてリフレッシュし、午後に重要な案件に取り組ませていただけないでしょうか?」
この返答ではまず「やります」という姿勢を見せつつ、自分のコンディションの問題を冷静に伝え、具体的な提案をしています。



上司も頭ごなしに否定しづらく、検討せざるを得ないでしょう。
「仕事だから我慢しろ」という抽象的な圧力に対し、具体策を提示して理詰めで切り返すことで、上司も感情論から降りてきやすくなります。
万一、



「うるさい!とにかくやれ!」
と取り合わない上司であれば、その場では



「承知しました」
と従いつつ、後日改めて上司の上司や人事に相談することも視野に入れてください。
労働には適正な範囲があり、社員の健康や安全を無視した「我慢の強要」は企業にとってもリスクとなる行為です



法的にも守られるべき権利がありますので、無理を重ねて心身を壊す前に周囲を巻き込んで改善を図りましょう。
8. 「暇そうだね」
心理的背景・意図:
皮肉混じりに



「きみ、暇そうだね?」
と声をかけるのは、部下が十分に忙しく働いていないように見えるときの嫌味です。
上司の心理としては、



「自分(あるいは他のメンバー)はこんなに忙しいのに、お前は余裕そうでけしからん」
という不公平感や嫉妬がある場合があります
例えば上司自身が抱えている仕事量が多かったり、常にバタバタ働くのが美徳だと思っていると、余裕のある態度=サボっていると短絡的に捉えてしまうのです。
また単に部下へのあてつけで、「もっと働け」という圧力をかける意図もありえます。
いずれにせよ、



「暇そうだね」
と言われた側は



「自分はサボっていないのに…」
と理不尽さを感じますし、下手に動くと



「勝手なことをするな」
と叱られる恐れもあるため困惑します。
効果的な切り返し方:
この場合、皮肉には皮肉で返さず、事実を淡々と伝えるか前向きに申し出る返答が有効です。
まず、自分が決して何もせずボーッとしていたわけではないなら、その事実を簡潔に示しましょう。
例えば



「いえ、先ほどまで△△の対応をしておりまして、ちょうど完了したところです。」
と説明します。
その上で、



「もし他にお手伝いできることがあればお申し付けください。」
と付け加えます。
これにより、上司の



「暇そうだ」
という指摘を受け流しつつ、自発的に動く意欲があることを示せます。
大事なのは、防御的・否定的にならないことです。



「暇ではありません!」
とムキになったり、



「仕事下さいよ」
と嫌味返しをしたりすると、上司との関係が悪化します。
逆に、「暇と言われた=助けが必要と思われた」と前向きに捉えて、



「おかげさまで一段落しました。他に急ぎの仕事があればぜひお手伝いさせてください」
と提案すれば、上司の方も調子が狂うはずです。



本当に仕事があるなら任せざるを得ませんし、なければ皮肉自体が的外れになるのでそれ以上言ってこなくなるでしょう。
会話例:



上司:「なんかお前、暇そうだねぇ?」



部下:「いえ、先ほどまで〇〇の作業対応を行い、つい今完了したところです。 他に急ぎの案件や手が足りない業務がありましたら、ぜひお手伝いさせてください。」
この返答では、「暇そう」と言われた部下が直前までちゃんと働いていた事実をさらりと述べ、さらに 前向きな協力の意思 を示しています。



上司が本当に忙しくて手が回っていないのなら、「じゃあ○○を頼む」となるかもしれませんし、単なる嫌味で言っただけならそれ以上突っ込めなくなります。
心理学的にも、このように嫌味を受け流しポジティブな提案に転換することを「Fogging(霧吹き)技法」や「積極的傾聴からの提案」と呼ぶことがあります。
相手の攻撃的な言葉にまともに反応せず、霧に巻くように受け流しつつ建設的な方向に持っていくことで、自分のペースに巻き込む効果があります。



もし本当に暇なのであれば、これはチャンスです。
自分から仕事を探す姿勢を示せば、上司の評価も上がるでしょう。



「では◯◯の件で資料整理しましょうか?」
など具体的に提案しても良いです。
重要なのは、 上司に「暇」と思わせてしまった原因が何かを考え、次に活かすことです。



自分のタスクが早く終わったなら報告して指示を仰ぐ、忙しそうな同僚を手伝うと申し出るなど、主体的に動けば「暇そうだね」などと言われる隙はなくなっていきます。
9. 「忙しいから後にして」&「なんで早く言わないの?」
心理的背景・意図:
こちらも組み合わせ型の厄介なケースです。
上司に報告・相談しようとしたら



「今忙しいから後にしてくれ」
と後回しにされ、その指示に従って時機を伺っていたら、後になって



「どうしてもっと早く言わなかったんだ!」
と怒られるパターンです。



典型的な理不尽。
これは上司が自分の都合で優先順位をコロコロ変えているか、部下の報告を真剣に受け止めていなかったことに起因します。
上司の心理としては、忙しいときは余裕がなく部下の話を遮り、後になって問題が顕在化すると責任転嫁的に



「早く言わないお前が悪い」
と叱ってしまうのでしょう。
要するに、上司自身のマネジメントミスを部下に押し付けている状態です。



この矛盾した対応に対し、部下が不満や不信感を抱くのも無理はありません。
効果的な切り返し方:
このケースでは 「事実」を淡々と伝えて上司の矛盾を解消してもらう 必要があります。
ポイントは感情的にならず、あくまで確認のために事実を述べる姿勢です。
具体的には、



「恐縮ですが、◯時頃に一度ご相談に伺った際『後にして』と伺いましたので、その後タイミングを見計らっておりました。ご報告が遅くなり申し訳ありません。」
と伝えます。
これにより、



「忙しいから後にして」
と言われた事実を上司に思い出させ、「早く言わなかった」という非難を和らげる効果があります。
そしてすかさず、



「以後はたとえお忙しくても、緊急の情報はすぐ共有するようにします。」
と付け加えましょう。
自分の落ち度として謝りつつ、再発防止策を示すのです。
そうすることで、上司も



「忙しいときに自分が後回しにさせたから今回遅れたのだ」
ということに気づき、責めるトーンが和らぐことが期待できます。



注:相手がまともな人間なら。
また、今後同じことが起きないよう、報告手段を工夫する提案も有効です。
例えば、



「次回からは口頭で難しければメールやチャットですぐに要件だけお伝えしますがよろしいでしょうか?」
と伺います。
上司が



「それでいい」
と言えば次から報告遅れの言い訳が立ちますし、上司自身も



「忙しくてもメールで報告は受け取っていた」
という状況を作れるので、お互い安心です。



なお、こういった矛盾を繰り返す上司には、部下側も自衛策が必要です。
最初に



「後にして」
と言われた際、



「承知しました。では◯時頃に再度伺います」
と念押ししたり、可能ならメールで



「本日◯時に△△の件ご報告に伺いましたがご多忙とのことで後ほどとなりました。緊急度は高くありませんので終業前までに再度ご連絡いたします。」
など記録を残したりしておくと、後で責められたときに落ち着いて説明できます。
会話例:
(※一度「後にして」と言われた後、改めて報告したときのやり取り)
上司:「だから言っただろ、『なんでもっと早く言わないんだ!』って!」
部下:「申し訳ありません。朝一でご報告に伺った際は『後にして』とのご指示でしたので、一旦見合わせておりました。 確認が遅れたのは私の落ち度ですので、今後はたとえお忙しい時でも要点だけすぐ共有するようにします。」
このように事実関係を冷静に伝え、こちらの非も認めつつ改善策を示せば、上司の勢いも次第に収まるでしょう。
実際、



「『後にして』と言われたのに『なぜ早く言わない』と叱られる…」
矛盾に部下が不満を感じるのは当然です。



カオス。
とにかく、もし上司がその矛盾に気づかない様子であれば、こちらから丁寧に思い出させてあげることが肝心です。
10. 「前例がないから」/「慣習だから」
心理的背景・意図:
若手社員が新しい提案や改善策を示したときに、年配の上司がよく使うのがこのセリフです。



「今までそういう例はないからダメだ」
「うちは昔からこのやり方だから」
と、思考停止的に変化を拒む態度が表れています。
心理的背景には、リスク回避の傾向や現状維持バイアスがあると考えられます。



人は未知のことにチャレンジするより、慣れ親しんだ方法に固執しがちですarmg.jp。
上司自身が過去の成功体験や前任者からの引き継ぎを重視するあまり、



「前例のないことは失敗するかもしれない」
「自分の代で余計な冒険はしたくない」
という保守的な心理に陥っているのでしょう。
また、



「若い部下如きの提案で慣習を変えるなんてプライドが許さない」
という権威主義的な発想も潜んでいるかもしれません。
いずれにせよ、このセリフを安易に使う上司の下では、組織の停滞や 若手の士気低下 が起こりやすくなります。
せっかく意欲をもって提案したのに頭から否定された部下は、



「どうせ何言っても無駄だ」
と感じてしまうでしょう。
効果的な切り返し方:
まず大前提として、真正面から論破しようとしないことです。



「前例がないからダメ」
に対し



「前例がなくてもやるべきです!」
と食い下がると、上司も意固地になり議論は平行線を辿ります。



効果的なのは、上司の懸念を理解しつつ提案のメリットを冷静に示すことです。
例えば



「前例がない」
と言われたら、



「確かに御社(我が社)では前例がありません。ただ業界全体を見渡すと△△などでは成果を上げている事例があります」
と、他社の事例やデータを引き合いに出します。
自社になくても世の中には前例があると示せれば、上司も少し受け入れやすくなります。
また



「慣習だから」
に対しては、



「慣習の良い点は残しつつ、さらに効率を上げるために改善案をご提案しました。リスクとメリットを整理しておりますので一度ご覧いただけないでしょうか」
と持ちかけます。



つまり、完全否定ではなく、伝統を尊重しつつ改良する提案だと強調するのです。
さらに、小さな範囲で試験導入してみる提案も有効です。



「いきなり全てを変えるのはリスクがあると思いますので、まずは〇〇部門で試験的に実施し、効果を検証してはいかがでしょうか?」
と切り出せば、上司も



「それならまあやってみても…」
と思いやすくなります。



人は大きな変化には抵抗しますが、小さな実験には寛容になりやすい心理を利用した方法です。
法的・組織的な視点から言えば、前例や慣習だけを理由に合理的な提案を拒むのは、企業の成長機会を失わせるリスクがあります。
最近では 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス) の一つとして「過去に前例のないプロジェクトは認められない」といった思考が挙げられておりarmg.jp、多様な発想を取り入れる研修なども行われています。
従って若手であるあなたの提案にも十分価値があるはずです。



粘り強くデータや論理で説得を試みましょう。
会話例:



上司:「君の提案は前例がないからね。うちではやったことがないし難しいんじゃないか。」



部下:「おっしゃるとおり、自社内では前例がありませんね。ただ、他社では似た取り組みで成果を上げている例があります(※資料に業界他社の事例データ)。 今回の提案は従来の慣習の良い点は残しつつ、新しい方法で効率アップを狙ったものです。 まずは小規模でテスト運用し、問題がないか確かめることも可能ですので、ぜひ一度詳細をご検討いただけませんでしょうか。」
このように 上司の懸念(前例のなさ)を認めつつ、データや具体策を提示 してお願いすれば、上司の心も動きやすくなります。
上司も頭から否定はしたものの、提案の利点が理解できれば



「じゃあ試しにやってみるか」
と前向きに捉え直してくれる可能性があります。
もしそれでも



「ダメなものはダメだ。以上!」
と取り付く島もない場合、無理に押し通そうとせず 一旦引いて様子を見る のも手です。



「承知しました。では今回の件は現行どおり進めます。また機会を見て提案させてください。」
と潔く引き下がれば、上司も深追いされずに済んだことで安心し、時間が経てば提案を思い直してくれることもあります。



提案自体は資料に残し、しかるべきタイミングで再提起できるよう準備しておきましょう。
まとめ
以上、パワハラ上司の典型的なセリフ10例について、その心理と対処法を解説しました。



大切なのは、どのケースでも自分を必要以上に卑下したり怯えたりせず、かといって感情的に反発せず、 冷静かつ毅然とした態度を貫くことです。
今回ご紹介した切り返し方はいずれも、相手の言葉を受け止めつつこちらの主張や事実を伝える 「アサーティブ(自己主張的)・コミュニケーション」 の一種です。
これは相手への尊重と自分の尊厳を両立させるコミュニケーション手法で、パワハラのような不当な状況下でも有効性が示されています。



しかし、どんなに工夫しても改善しない悪質なパワハラ上司も残念ながら存在します。
精神的苦痛が限界に達する前に、信頼できる同僚や上司、人事部、社外の労働相談(労働局の総合労働相談コーナーなど)に相談しましょう。
「録音」は最強の証拠になるので、日頃からパワハラ発言の日時・内容をメモや録音で記録しておくと後々役立ちます。



法的にはあなたを守る制度が整いつつあります。
実際、2020年のパワハラ防止法施行以降、企業への相談体制整備が義務化され、2024年の調査ではパワハラ加害を指摘・自覚した人の割合は5.2%と加害者側の意識も高まりつつありますnews.ntv.co.jp。
追い詰められていると感じたら、



「自分だけじゃない、きっと解決できる」
と信じ、然るべきアクションを起こしてください。
最後に、ブラック企業からの「脱出」を考えている方へ。自分の心と体は何にも代え難い大切な資本です。



どんな言葉の暴力も、あなたの価値を損なうものではありません。
パワハラ発言の裏にある上司の未熟さや心理を見抜き、今回紹介したような対処法で切り抜けつつ、必要なら新天地を求める勇気を持ってください。
あなたが安心して働ける環境は必ず存在しますし、健全な職場では今回挙げたような暴言そのものがあり得ません。



普通に普通のホワイトな環境は普通にあります。
私もそこに勤務しています。
科学的データも示すように、パワハラは組織にとってマイナスでしかなく、防止・是正されるべきものですjournals.plos.org。



どうか自分を責めず、適切に対処し、明るいキャリアを切り拓いていってください。
よくある質問
その他の質問はこちらから: