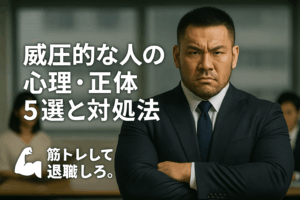この記事は、以下のような人に向けた記事となっています。
「なんでアイツ、俺のこと嫌いなくせに絡んでくるんだよ…」
「正直、怖い。何考えてるのか分からない」
「無視してるのに、わざわざ近くに寄ってくるの意味わからん」
 カワサキ
カワサキ嫌いならそもそも寄ってこなければいいのに、なぜかわざわざ寄ってくる奴いますよね?
そいつの心理と対処法について解説します。
実はそいつは結構なガラスメンタル。
自信のなさを隠すために他人を攻撃し、優越感を得ようとする。
相手を思い通りに動かしたくて、嫌いでも関わろうとする。
自分の欠点を認めたくないがために、他人に映し出して責める。
嫉妬や競争心、恨みなどから対象に異常なこだわりを見せる。
被害妄想や思い込みによって、敵意を抱いて付きまとう。
あなたのことを嫌いなはずなのに、なぜか職場であなたにつきまとってくる人に興味はありませんか?



でもその人、明らかにあなたを嫌っているはずですよね。
それなのに、なぜ?というお話。
この記事では、そんな「意味不明な絡み」の裏にある心理を科学的に解き明かします。
劣等感や支配欲、認知の歪みなど、実は全て“相手の問題”なんです。



知ることで、怖くなくなります。
さらに、自衛のテクニックや「逃げる=退職」という選択肢まで、全部まとめました。



人間関係に疲れた方はぜひ最後まで読んでみてください。
こちらもおすすめ:
はじめに
職場には、なぜか自分のことを嫌っているはずなのに、やたら絡んできたり近くに居座ったりする人っていますよね。
社会人やってると、そうした人間関係の悩みを抱える方は少なくありません。



もちろん私もです。
実際、ある調査では 「約3人に1人が職場でいじめ(嫌がらせ)を受けた経験がある」 と報告されており、さらに 「そのうち約20%(5人に1人)がそれが原因で仕事を辞めている」 というデータもありますinterface.williamjames.edu。
まずは安心してください。
あなたのせいで相手がつきまとうわけではなく、多くの場合は 相手自身の心理的な問題 に原因があります。



よっぽどのことがない限り、あなたに非はない。
というか、逆にあなたが凄い人という可能性も。
ここでは、「嫌いなくせにつきまとってくる人」の考えられる心理を5つ紹介します。
それぞれ、専門家による研究結果(メタ分析や統計)をもとにしているので信頼性は折り紙付きです。
嫌いなのにつきまとう人の主な心理 5選
ここでは嫌いなのにつきまとう人の主な心理5つについて、下記の内容で触れます。
1. 劣等感
一つ目の理由は、相手が深い劣等感を抱えている可能性です。
自分に自信がない人ほど、他人を攻撃したり束縛したりすることでしか自分の価値を確認できないことがあります。



「自分より弱い人をいじめれば安心する」
といった心理で、嫌いな相手につきまとい批判することで、自分のほうが上だと感じたがっているのです。



いわゆる「自分が傷ついている人が、他人を傷つける」状況ですね。
科学的根拠
自尊心(セルフエスティーム)が低い人ほど攻撃的になりやすいことが、多くの研究で示されています。
例えば、中国の研究チームが 82,358人もの学生データを分析したメタ分析では、自己評価の低さと攻撃性には中程度の負の相関関係(相関係数r=-0.21)があると結論付けられましたresearchgate.net。
つまり、自信のない人ほど他者に攻撃的になる傾向が統計的に確認されています。
ポイント
相手の暴言や意地悪は、あなたの欠点を指摘しているように見えて、実は相手自身の弱さの裏返しです。



そう理解するだけでも、「自分が責められるのは自分がダメだからではないんだ」と気づけて、不安や恐怖が和らぐはずです。
2. 支配欲
二つ目の理由は、相手が強い支配欲や権力欲を持っている可能性です。
簡単に言うと



「人を自分の思い通りに動かしたい」
「マウントを取りたい」
という心理です。
このタイプの人は、自分が優位に立っていると感じるために、わざと嫌いな相手につきまとって指図したり粗探ししたりします。
実際、職場いじめの加害者は上司であるケースが非常に多く報告されていますbmcpublichealth.biomedcentral.com。



こうした人は、自分が相手より力があると示すことで安心感を得ようとしているのです。
科学的根拠
職場いじめ研究では「いじめの目的の一つは権力欲求を満たすため」とも言われていますdeepblue.lib.umich.edu。
米ミシガン大学のDolanらの研究(2018年)では、いじめ加害者は客観的に見た自分の地位以上に「自分は力が足りない」と感じている傾向があると報告されていますdeepblue.lib.umich.edu。



その不足感を埋めるために、いじめという手段で他者より優位に立とうとするわけです。
またイギリスの大規模調査では、職場いじめ加害者の約53.6%が上司、42.8%が同僚だったとの結果が出ていますbmcpublichealth.biomedcentral.com。



このことからも、職場いじめは上下関係やパワーバランスと深く関わっていると言えます。
ポイント
相手は「自分が上だ」と示したいだけで動いている可能性が高いです。
あなた個人に重大な落ち度があるわけではなく、相手の権力欲に振り回されているだけと分かれば、



「なんだ、自分の問題じゃないんだ」
と気が楽になるでしょう。



むしろ支配欲に負けて行動に出してしまっている相手こそが小物。
3. 自己投影
三つ目の心理は、「自己投影」です。



これは、自分の中にある認めたくない欠点や嫌な感情を、他人の中に見出してしまう心理現象です。
例えば、実は自分が怠け者であることに後ろめたさを感じている人が、それを認めたくないばかりに他人に「お前は怠けている!」と執拗にからんでしまう、といったケースです。



本当は自分自身に向けるべき怒りや嫌悪感を、ターゲットとなる他人に投影し攻撃しているのです。
科学的根拠
心理学では古くから防衛機制の一つとして「心理的投影(projection)」が知られていますen.wikipedia.org。
例えば心理学専門誌の解説によれば、「ある人が他人の不安な点をしつこくいじめたり嘲笑している場合、その人(いじめる側)は自分自身の自尊心の問題を相手に投影している可能性が高い」とされていますpsychologytoday.com。



要するに、いじめる側が相手に対して抱く攻撃的な評価は、その人自身の中にある不安やコンプレックスを映し出しているということです。
ポイント
それは相手自身の心の中身を映す“鏡”にすぎないからです。
たとえば



「使えない奴だ」
と言われても、



「この人は自分自身が使えない人間だと思われたくなくて必死なんだな」
くらいに受け流してOKです。



そう考えると、相手の言動もどこか滑稽に思えてきて怖さも和らぐでしょう。
4. 執着
四つ目に考えられるのは、相手が何らかの理由であなたに執着してしまっているケースです。
普通は嫌いな人には近づきたくないものですが、心理的に極端な執着があると



「嫌いだけど離れられない」
という矛盾した行動をとることがあります。
たとえば、相手があなたに対して強い嫉妬心や競争心を抱いている場合、



「負けたくない、一挙一動を監視してやる」
といった具合に、嫌いなのにかえって目が離せなくなるのです。
また過去の些細な揉め事をずっと根に持っていて、恨みや復讐心から異常に絡んでくる人もいます。



このように執着心が暴走すると、ストーカーまがいに付きまとわれるケースも残念ながら存在します。
科学的根拠
心理学者のスピッツバーグとクパックは、他人への一方的な執着によるつきまとい行為を「強迫的関係侵入(ORI: Obsessive Relational Intrusion)」と名付けていますen.wikipedia.org。
ORIとは「親しい関係になりたい、あるいは相手を支配下に置きたいという欲求から、相手のプライバシーや空間に繰り返し不当に侵入する行為」と定義されていますen.wikipedia.org。



特徴的なのは、相手から明確に拒絶されても追及をやめない点です。
研究によれば、このような加害者はターゲットに異常なほど固執し、頭の中がその人でいっぱいになっている傾向があるといいますen.wikipedia.org。



いわば常軌を逸した執着が行動を支配しているのです。
ポイント
相手の過剰な執着はもはや相手自身の問題であり、あなたがどうこうできるものではありません。



「なぜこんなに絡まれるのか?」
と悩むよりも、



「この人は何かに取り憑かれたように固執しているんだな…」
と客観視しましょう。



そうすれば少し距離を置いて状況を見ることができ、必要以上に怖がらずに済むはずです。
5. 認知のゆがみ
最後の理由は、相手のものの見方・考え方に歪みがあるケースです。



専門用語では「認知のゆがみ」や「認知バイアス」と呼ばれますが、要は 「相手が勝手に思い込んでいる」 状態です。
たとえば、あなたは全く悪意なくした行動なのに、相手は



「自分にケンカを売っているに違いない!」
などと曲解しているかもしれません。
こうした人は他人の言動をネガティブに解釈しがち(被害妄想気味)なので、常に攻撃の口実を探して付きまとってくるのです。



「自分は悪くない、悪いのはあいつだ」
という思い込みを強めるために、嫌いな相手に執拗に絡むケースもあります。



『どっちが悪くてもいいから、とにかく関わらんでくれ』って思いながら元上司を見てた。
科学的根拠
認知のゆがみが攻撃的行動につながることは、多くの研究で実証されています。
特に有名なのが「敵意帰属バイアス(Hostile Attribution Bias)」という現象で、これは他人の行動を不必要に敵意的だと解釈してしまう癖のことですen.wikipedia.org。
2019年の体系的レビュー研究(25の研究を分析)では、調査対象の約80%の研究で「敵意帰属バイアスが強い人ほど攻撃的行動をとりやすい」という関連性が確認されていますplus.cobiss.net。
さらに、このバイアスは一般人から犯罪者まで一貫して見られることから、人間に普遍的な認知の歪みであることが示唆されていますplus.cobiss.net。



要するに、物事の受け取り方が歪んでいると、それだけで攻撃的・粘着的な言動が引き起こされるということです。
ポイント
相手の言動が理不尽に感じられるとき、実際相手の頭の中では都合のいい物語(思い込み)が展開しているものです。
あなたとしては身に覚えがなくても、相手は勝手に悪者を作り上げて怒っているだけかもしれません。



「何か誤解してるんだな」
「被害妄想をぶつけられてるだけかも」
と考えると、少し冷静に対応できるでしょう。
知れば怖くない:不当な干渉への対処法
ここまで見てきたように、嫌いなのにつきまとってくる人の心理は 相手自身の内面の問題 に起因することがほとんどです。



そう理解できれば少し気が楽になりますよね。
では、実際にそういう人に絡まれたとき、どのように自衛すれば良いのでしょうか?いくつか対処法のポイントを挙げます。
境界線を引く
まずは毅然とした態度で



「それは迷惑だ」
「そういう言い方はやめてほしい」
と自分の境界を相手に伝えましょうverywellmind.com。
嫌がらせ行為が発生したその場で、



「今の○○という発言は受け入れられません」
と冷静に指摘するのも効果的です。



感情的にならず短く伝えるのがコツですverywellmind.com。
参考:BIFF法
- Brief:手短に
- Informative:事実を伝え
- Friendly:穏やかに
- Firm:しかし断固として
記録を残す
相手の言動が改善しない場合に備えて、日時・内容・周囲の目撃者などをメモして記録しておきましょうverywellmind.com。
メールやチャットでの嫌がらせは保存します。



客観的な証拠を蓄えておくことで、いざというとき第三者(人事や労基署)に相談しやすくなります。
周囲に相談・報告
信頼できる同僚や上司に相談してみましょう。
同僚に味方がいれば心強いですし、上司や人事に正式に報告すれば会社として対応してもらえる可能性がありますverywellmind.com。



社内のハラスメント相談窓口があれば利用も検討してください。
ただし、残念ながら組織によっては対応が不十分な場合もありますverywellmind.com。



その場合は社外の労働相談機関や法律の専門家に助けを求めても良いでしょう。
自分を大切に
最も大事なのは、あなた自身の心身の健康を守ることですverywellmind.com。
嫌な相手にエネルギーを奪われすぎないよう、仕事の外でリラックスできる時間を持ったり、信頼できる人に愚痴を聞いてもらったりしましょう。
必要であれば専門のカウンセラーやメンタルヘルス科に相談することも検討してください。



あなたが安心して働けることが何より大切です。
退職も選択肢
最後に、「逃げるが勝ち」も時には大切です。



日本では仕事を辞めることに抵抗を感じる人も多いですが、心を壊してまで我慢する必要はありません。
実際に冒頭で紹介した調査のように、職場いじめが原因で退職する人は珍しくありませんinterface.williamjames.edu。
あなたが泣き寝入りで去るのは悔しいかもしれませんが、決して弱いわけではなく 自分を守るための賢明な決断 です。



次の職場で心機一転がんばればいいだけの話ですから、追い詰められる前に「環境を変える」選択肢もあると覚えておいてください。
まとめ
職場で付きまとってくる嫌な人の心理として、「劣等感」「支配欲」「自己投影」「執着」「認知のゆがみ」といった理由を見てきました。



どれも相手の中の問題であり、あなた自身の価値とは無関係です。
心理を知れば怖くありません。相手の言動に必要以上に怯えず、しかし油断もせず、適切に対処していきましょう。



あなたが安心して働けるよう応援しています。
よくある質問
- なぜ嫌いな人に依存してしまうのですか?
-
嫌いな人に依存してしまうのは、心理的な理由が背景にあります。
特に、自己評価が低かったり、孤立感が強い場合、人はたとえ嫌な相手でも何かしらのつながりを維持しようとする傾向があります。
職場環境が原因であれば、ストレスマネジメントやフィットネスを取り入れて自分を高めることで、徐々にその依存を軽減できます。
- 嫌いな人と距離を置くための効果的な方法は?
-
嫌いな人と距離を置くためには、まずは自分自身に集中することが大切です。
筋トレやメンタルエクササイズなど、自分の体や心に向き合う活動を取り入れることで、他人に対する過度な依存を減らし、精神的な距離を保つことができます。
また、コミュニケーションを必要最低限にし、理性的に対応することも効果的です。
- なぜ嫌いな人と共存することが難しいのでしょうか?
-
嫌いな人と共存することが難しい理由には、ストレスや感情のぶつかり合いが関与しています。
特に職場では逃げ場がないことから、常に相手の存在を感じることがストレスを引き起こします。
このような状況では、自己改善やリラックス法を学び、感情的に距離を保つ方法が有効です。
- 嫌いな人に対して感情的に反応してしまうのはなぜですか?
-
嫌いな人に対して感情的に反応してしまうのは、自己防衛のメカニズムが働くためです。
特に、過去に嫌な経験があったり、ストレスが溜まっていると、無意識に相手を拒絶しようとする反応が強まります。
こうした状況では、運動やリラクゼーションを活用してストレスを軽減することが、冷静な対応の手助けとなります。
- 自分を傷つける人との関係を断つにはどうすればいいですか?
-
自分を傷つける人との関係を断つには、まず自分の限界を知ることが重要です。
感情的に巻き込まれないためには、自分自身を大切にし、外部の助けを求めることも検討するべきです。
筋トレやカウンセリング、友人との時間など、自分を取り戻すための活動を日常に取り入れることで、関係を断つ決意が固まります。
- 嫌いな人を無視するのは効果的ですか?
-
嫌いな人を無視することは一時的には効果的かもしれませんが、根本的な解決策にはなりません。
相手を無視することで一時的にストレスは軽減しますが、内面的な不安が残る可能性があります。
冷静に相手との距離を保ちつつ、自分のメンタルケアやストレス管理を優先することで、長期的な安定を目指しましょう。
- 嫌いな人との関係がメンタルヘルスにどんな影響を与えますか?
-
嫌いな人との関係は、ストレスや不安感を引き起こし、メンタルヘルスに悪影響を与えることがあります。
特に、長期間にわたってその人との関係が続く場合、自己評価が低下したり、焦りを感じることが増えます。
- なぜ嫌いな人を避けることが難しいのですか?
-
嫌いな人を避けるのが難しい理由には、職場や家庭などの環境要因が関係しています。
多くの場合、物理的に距離を取ることが難しく、避けたいと思っても関わらざるを得ない状況にあります。
このような場合には、自分の心を強く保ち、ストレス解消法を取り入れることで、精神的なバランスを取ることが有効です。
- 嫌いな人との関係を修復することはできますか?
-
嫌いな人との関係を修復することは可能ですが、両者の努力が必要です。
冷静な対話を心がけ、互いの立場を理解しようとすることで、関係が改善されることがあります。
ただし、全ての関係が修復できるわけではないため、自分自身を大切にし、無理に修復しようとしないことも重要です。
その他の質問はこちらから:





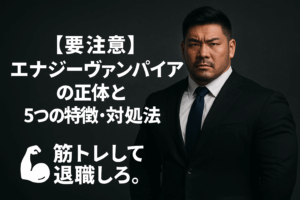


とは?言葉の意味と行う人の心理を徹底解説-300x200.png)